いとこが遺産を相続する方法とは?遺贈や特別縁故者への財産分与を解説
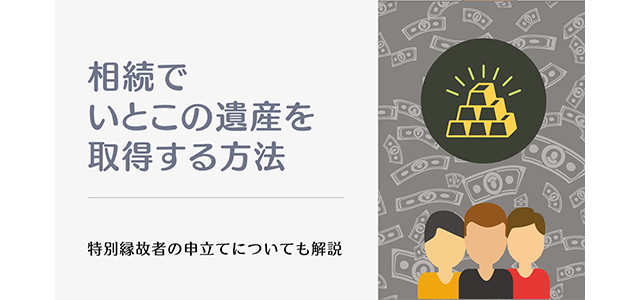
通常、いとこ同士の間柄では遺産を相続することができません。
しかし、故人が遺言に「いとこに財産を残す」と記載していた場合や、いとこが家族同然に故人の生前の身の回りの世話をしていたような場合は、いとこでも遺産を相続できることがあります。
この記事では、いとこが遺産を相続する方法について解説します。必要な手続きや生前対策のほか、注意点を知っておくことで、いとこがスムーズかつ確実に遺産を受け継ぐことができるでしょう。
この記事の目次 [表示]
1.いとこに身寄りがなければ遺産はどうなる?
亡くなった人の遺産は、以下のいずれかの方法で引き継がれます。
故人に身寄りがない場合は、遺産はそのまま放置されるわけではなく、相続財産清算人が行う手続きによってしかるべき引き継ぎ先に引き継がれます。
1-1.【遺言あり】遺言の内容に沿って遺産が分け与えられる
故人が遺言を作成して、遺産を誰に与えるかを指定していれば、遺言の内容に沿って遺産が分け与えられます。
遺言では、相続人以外の人にも遺産を与えることができます。
1-2.【遺言なし】法定相続人が遺産を相続する
故人が遺言を作成していない場合は、法定相続人が遺産を相続します。相続人が2人以上いる場合は、相続人全員で協議して遺産を分配します。
故人の遺産を相続できる人は、民法でその範囲が決められています。
| 相続順位 | 相続人の範囲 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 必ず相続人になる | 配偶者 | なし |
| 第1順位 | 子 | 子が亡くなっている場合は孫 孫も亡くなっている場合はひ孫 |
| 第2順位 | 直系尊属 (父母など) | なし |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪 甥姪が亡くなっている場合の代襲相続はなし |
故人の配偶者は必ず相続人になります。その他の親族は、故人との続柄によって相続人になれるかどうかの優先順位があります。
「代襲相続」とは、相続人になる子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、代わりに孫(子の子)や甥姪(兄弟姉妹の子)が相続人になることをいいます。
第2順位の相続人は「直系尊属」であり、父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合は、祖父母が相続人になります。
1-2-1.いとこは法定相続人ではない
故人に配偶者や子、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合は、法定相続人はいないことになります。
このように身寄りがない人でも、親族としていとこがいる場合はあるでしょう。しかし、先ほど解説したとおり、法定相続人の範囲にいとこは含まれていません。
生前にどれだけ親しかったとしても、故人のいとこは法定相続人になりません。
1-3.【法定相続人なし】遺産は特別縁故者に与えられる
故人に法定相続人がいないときは、「特別縁故者」に該当する人が家庭裁判所に申し出ることで遺産を与えられる場合があります。
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの故人と特別な関係にあった人のことです。例えば、故人と生計を共にしていた人や、生前に故人の看病をしていた人などが当てはまります。
このように、家族と同様に親密な関係にあると認められる人には、特別に遺産が与えられます。
1-4.誰にも引き継がれない遺産は国に納められる
法定相続人もおらず特別縁故者に該当する人もいない場合、遺産は国に納められます。
以下の要件をすべて満たすとき、故人の財産は国に納められることになります。
故人の財産が国に納められる要件
- 遺言書がない
- 法定相続人がいない
- 故人に債権者がいない(または債権者に支払いを済ませている)
- 特別縁故者がいない
- 財産の共有者がいない(または財産の共有持分を共有者に移している)
このほか、特別縁故者に与えてもなお故人の財産が残るときは、その残りの財産は国に納められることになります。
2.身寄りのない人の遺産をいとこが相続できるケースとは?
亡くなったいとこに身寄りがいなかったとしても、通常は、いとこ同士の続柄では法定相続人にはあたらず、遺産を相続することができません。
しかし、次のいずれかに当てはまる場合は、いとこが遺産を相続できる可能性があります。
身寄りのない人の遺産をいとこが相続できるケース
(上記の方法はいずれも厳密な定義では「相続」ではありませんが、ここでは故人から遺産を受け継ぐという意味で「相続」という用語を使います。)
実際にいとこが遺産を受け継ぐのは、遺言によるケースが多いようです。
2-1.故人が遺言書を残していた
故人が遺言で遺産を誰に与えるか指定していれば、そのとおりに遺産が引き継がれます。法定相続人ではないいとこでも、遺産を受け継ぐことができます。
遺言書があれば、その内容にもとづいて財産の名義変更などの相続手続きができます。
2-2.故人の特別縁故者にあたる
身寄りのない人が遺言を残していなかった場合は、遺産は国に納められることになります。
しかし、生前に故人の看病をしていたり故人と生計を共にしていたりしたなど、「特別縁故者」に該当すれば、いとこが遺産を受け取れる可能性があります。
特別縁故者に該当するには、単にいとこ同士で仲が良かったというだけでは不十分です。法律で定められた3つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。
3つの要件とは、「故人と生計を共にしていた」、「故人の療養看護に努めていた」、「その他特別の縁故があった」ことです。
2-2-1.特別縁故者にあたる3つの要件
特別縁故者にあたる3つの要件について内容をまとめると、以下のとおりです。
| 要件 | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 故人と生計を 共にしていた | 内縁関係の夫婦、養子縁組をしていない事実上の養子・養親、同居していたいとこなど | 故人と同居していなくても、事情によっては生計を共にしていたとみなされる場合がある |
| 故人の療養看護に 努めていた | 長期間にわたって、故人の看護、介護、生活の世話などに努めていた人 | 看護師、介護士、ヘルパーなど仕事として相当な報酬を得ていた場合は該当しない(例外あり) |
| その他特別の 縁故があった | 生計を共にしていた場合や療養看護に努めていた場合と同様の密接な関係があり、遺産を与えることが故人の意思に合致するといえる場合 | 単に「仲が良かった」「一緒に行動することが多かった」ことだけでは該当しない |
上記の例はあくまでも目安です。要件を満たすかどうかは、家庭裁判所が個々のケースに応じて判断します。
看護師や介護士、ヘルパーなど、仕事として相当な報酬を得ていた場合は、特別縁故者にはあたりません。ただし、受け取った報酬の程度を超えて献身的に療養看護をしていたと認められる場合は、例外的に特別縁故者になれることもあります。
2-2-2.特別縁故者にあたらないケース
故人とかかわりがあっても、以下のようなケースに当てはまる場合は特別縁故者には該当しません。
特別縁故者にあたらないケース
- 故人の葬儀を行い費用も負担したが生前は疎遠であった
- 報酬を得てその範囲内で療養看護をしていた
故人の葬儀を取り仕切り、葬儀や埋葬の費用を負担しても、そのことだけで特別縁故者になることは難しいでしょう。故人と生計を共にしていたか、故人の療養看護に努めていたなど、生前に深い関わりがあったことが求められます。
また、先ほどお伝えしたように、看護師や介護士、ヘルパーなどとして相当の報酬を得て、その範囲で故人の療養看護をしていた場合は、特別縁故者として認められないのが原則です。
3.いとこが遺言で遺産を相続する方法
身寄りのない人の遺産をいとこが相続できる方法の一つ目として、遺言で遺産を相続する方法(遺贈)について解説します。
故人の遺言があれば、法定相続人ではないいとこでも遺産を受け継ぐことができます。遺言は、故人の意思を尊重する制度であるため、法定相続人による相続よりも優先されます。
3-1.生前に遺言書を作成する
遺贈をするには、財産を残す人が生前に法的に有効な遺言書を作成し、誰に何を与えるかを指定します。
法定相続人がおらずいとこに財産を継いでもらいたい人や、お世話になったいとこにお礼として財産をあげたい人は、遺言で財産を与えるとよいでしょう。
また、法定相続人がいないことで財産が国に納められるぐらいであればと考える人は、親族であるいとこに財産を与えることも選択できます。
3-2.確実に実行してもらうには公正証書遺言を作成
遺言は大きく分けて「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットは以下のとおりです。
| 種類 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者が自分で記述 |
|
|
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 |
|
|
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま遺言の存在だけを公証役場で認証 |
|
|
いとこに財産を与えるためには、公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言は公証人が作成するため、確実性が担保されています。公証人とは、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。自筆証書遺言や秘密証書遺言のように、内容が無効になったり改ざんされたりする心配がありません。
4.いとこが特別縁故者となって遺産を相続する方法
次に、身寄りのない人の遺産をいとこが相続できる方法の二つ目として、特別縁故者への財産分与について解説します。
実際にいとこが遺産を受け継ぐのは遺言によるケースが多いようですが、全員が必ず生前に遺言書を作成するわけではありません。
故人に身寄りがなく、遺言書を残していなかった場合は、遺産は国に納められることになります。しかし、国に納められるのであれば、いとこが自ら特別縁故者として申し出て、財産分与を受けることも一つの方法です。
4-1.特別縁故者への財産分与の流れ
特別縁故者として遺産を受け継ぐためには、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」をする必要があります。
ただし、故人が亡くなってからすぐに相続財産分与の申立てができるわけではありません。
法定相続人がいない人の財産は相続財産清算人によって清算されますが、一連の清算手続きの最後の段階になってはじめて、相続財産分与の申立てができるようになります。
特別縁故者として遺産を受け継ぐためには、以下の手続きを経る必要があります。
- 相続財産清算人選任の申立て
- 相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告(6ヵ月以上)
- 故人に債権者や受遺者がいれば請求を申し出ることを求める公告(2ヵ月以上)
- 相続人不存在の確定
- 特別縁故者に対する相続財産分与の申立て(3ヵ月以内)
- 特別縁故者もいなければ遺産は国庫へ帰属
令和5年4月1日施行の民法改正では、従来の「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称が変更されました。
また、別々に行われていた「相続財産管理人の選任の公告」と「相続人の捜索の公告」は一つの公告に統合され、この公告と同時に「債権者や受遺者がいれば請求を申し出ることを求める公告」を行うようになりました。
相続財産清算人選任の申立てから特別縁故者として遺産を取得するまでには、最低でも6ヵ月以上かかります。
4-2.相続財産清算人選任の申立て
特別縁故者として遺産を受け継ぐためには、まず、故人の財産の清算手続きを行う相続財産清算人を選任しなければなりません。
相続財産清算人の選任は、故人の最後の住所地(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
申立てが受理されると、家庭裁判所は申立書などの内容をふまえ、調査や書面照会などを経て相続財産清算人を選任します。相続財産清算人に選ばれた人は、相続財産の一切を管理する責務を負うことになります。
相続財産清算人選任の申立てに必要な書類と費用は、以下のとおりです。
相続財産清算人選任の申立ての必要書類
- 相続財産清算人選任の申立書
- 故人に法定相続人がいないことがわかる戸籍謄本など
(故人および故人の父母の出生から死亡まで連続した戸籍謄本など) - 故人の住民票除票または戸籍附票
- 財産の内容がわかる資料
(不動産登記事項証明書、預金通帳の写しなど) - 利害関係人からの申立ての場合、故人との利害関係が確認できる資料
(いとこであることがわかる戸籍謄本など)
相続財産清算人選任の申立ての費用
- 収入印紙(800円分)
- 官報公告料(5075円)
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なる)
相続財産清算人の選任の申立ては、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできますが、着手金や報酬が必要です。
4-3.相続人不存在の確定
家庭裁判所によって選任された相続財産清算人は、故人の財産状況の調査を開始します。
これと同時に、法定相続人の捜索を行います。捜索は、官報で情報を広く一般に行きわたらせる「公告」により行います。公告の満了までの期間は最低6ヵ月です。
公告期間の満了までに法定相続人が現れなければ、故人に法定相続人がいないことが確定します。
4-4.特別縁故者に対する相続財産分与の申立て
特別縁故者として相続財産分与を受けたい場合は、法定相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に、家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行います。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立てに必要な書類と費用は、以下のとおりです。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての必要書類
- 特別縁故者に対する相続財産分与の申立書
- 申立人の住民票もしくは戸籍附票
- 財産目録
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ての費用
- 収入印紙(800円分)
- 連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なる)
特別縁故者からの申立てがあれば、家庭裁判所は審理を行います。申立人が特別縁故者にあたり、財産分与をすることが相当であると認められれば、財産分与をする審判が下されます。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立ては、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもできますが、着手金や報酬が必要です。
5.いとこに財産を与える生前対策
いとこに財産を与えるのであれば、相続まで待たずに元気なうちにできる対策もあります。
生前にいとこに財産を与える対策には、以下のものがあります。
いとこに財産を与える生前対策
5-1.贈与税の基礎控除の範囲内でいとこに生前贈与する
いとこ同士で合意すれば、生前に財産を贈与することができます。生前贈与とは、生きているうちに個人から個人へ無償で財産を渡すことです。渡す相手は法定相続人でなくても構いません。
贈与を受けた財産には贈与税が課されますが、年間に受けた贈与財産の合計が基礎控除額(110万円)までであれば、課税されません。毎年少しずついとこに生前贈与をすれば、贈与税がかからずに、いとこに財産を与えることができます。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
ただし、毎年同じ金額を規則的に贈与する定期贈与に当てはまる場合では、数年分の贈与の合計に贈与税が課される恐れがあるため注意が必要です。
参考:定期贈与(連年贈与)とみなされない3つの回避方法とは?
5-2.死因贈与契約を結ぶ
死因贈与とは、財産を与える人が「自分の死後に遺産を与える」という意思表示をし、受け継ぐ人がこれを了承する意思表示をすることです。
遺言で財産を与える「遺贈」と似た方法ですが、死因贈与と遺贈には以下の違いがあります。
| 死因贈与 | 「死後に財産を与える」ことについて、与える人と受け継ぐ人で意思が合致している契約 |
|---|---|
| 遺贈 | 「死後に財産を与える」ことについて、与える人の一方的な意思表示のみでできる |
死因贈与は遺言と違って、当事者の口約束のみでも成立します。ただし、財産を与える人が死亡すれば贈与の約束があったことを証明することは困難で、トラブルになる恐れがあります。死因贈与の契約内容は書面に残しておくようにしましょう。
6.いとこから遺産を受け継ぐときの注意点
いとこから遺産を受け継ぐことになったときは、遺贈による場合でも、特別縁故者として財産分与を受ける場合でも、あとで困らないように注意点を押さえておく必要があります。
いとこから遺産を受け継ぐときの注意点
このあと、それぞれの内容について解説します。
6-1.行方不明の法定相続人がいる場合は失踪宣告の申立てが必要
亡くなったいとこに身寄りがいないと思っていたものの、よく調べると、長らく連絡が取れず行方不明になっている法定相続人がいる場合もあります。
たとえ行方不明や音信不通であっても、故人に法定相続人がいる限り、特別縁故者に財産は与えられません。
ただし、あまりに長期にわたって生死不明の状態が続くときは、家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができます。失踪宣告とは、生死不明の人について法律上死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告が行われるための要件は、以下のとおりです。
失踪宣告が行われるための要件
- 不在者が従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みがないこと
- 不在者の生死が7年間明らかでないこと
- あるいは、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ったあとその生死が1年間明らかでないこと
参考:失踪宣告|裁判所
法定相続人の失踪が宣告され法定相続人がいなくなれば、特別縁故者は財産分与を受けられるようになります。
6-2.包括遺贈された場合はマイナスの財産も受け継ぐ
遺産相続は、現預金や財産などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も対象になります。
いとこが作成した遺言の内容が包括遺贈であった場合は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け継ぐことになります。
包括遺贈とは、遺贈する財産を具体的に指定するのではなく、割合を定める方法です。例えば、遺言書には以下のように記載します。
包括遺贈は与える財産を特定していないため、プラスの財産であるかマイナスの財産であるかにかかわらず、指定された割合の財産を取得します。
包括遺贈では、「マイナスの財産を除いてプラスの財産だけを受け取る」ということはできないため注意しましょう。マイナスの財産を受け取らないようにするには、相続人の場合と同様に相続放棄を行うことになりますが、相続放棄をするとプラスの財産も受け取ることができません。
6-3.相続財産分与の申立ては相続人がいないと確定してから3ヵ月以内
特別縁故者として財産分与を受ける場合は、家庭裁判所への申立てができる期間に注意しましょう。
相続財産清算人が行う手続きにより法定相続人がいないことが確定してから、「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」ができます。
ただし、申し立てには期限があります。法定相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に申立てる必要があるため注意しましょう。
3ヵ月以内に特別縁故者が財産分与の申し立てを行わなかった場合は、故人の財産は国に納められることになります。国に納められたあとに、特別縁故者が財産分与を受けることはできません。
特別縁故者として財産分与を受ける手続きの流れは、「4.いとこが特別縁故者となって遺産を相続する方法」をご確認ください。
6-4.いとこは相続税が2割多くかかる
法定相続人でない人でも、遺贈や特別縁故者への財産分与などで故人の遺産を受け継いだ場合は相続税の申告義務があります。
また、故人の一親等の血族(代襲相続する孫も含む)および配偶者以外の人は、相続税額に2割相当の金額が加算されます。
いとこが遺産を受け継いで相続税が課税されるときは、通常の2割増しの税額を支払う必要があるため注意しましょう。
なお、相続税の課税対象となる金額は、遺産の総額から基礎控除額を引いた金額です。算式で表すと「遺産の総額-基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」となります。
故人に法定相続人がいない場合は、法定相続人の数をゼロとするため、基礎控除額は3000万円となります。したがって、相続税がかかるのは取得した遺産の総額のうち3000万円を超えた部分です。そして、その財産に対する相続税額に2割相当の金額が加算されます。
なお遺産の総額は、遺産を取得した方法に応じて以下のとおり計算します。
| 遺産取得の方法 | 遺産総額の計算方法 |
|---|---|
| 特別縁故者への財産分与 | 遺産を取得した時の価額をもとに計算 |
| 遺言による遺贈・死因贈与 | 故人の死亡時点の価額をもとに計算 |
7.いとこへの遺産相続のサポート事例
最後に、いとこへの遺産相続について弊社グループがサポートした事例をご紹介します。
(実際の事実関係を変えて掲載しています。)
7-1.遺言により相続した事例
- 被相続人:Aさん Aさんは独身で子はいない。両親はすでに死亡。姉が1人いたが、すでに死亡しており子はいない。したがって、法定相続人はいない。
- 相談者:Bさん(Aさんのいとこ)
Aさんには身寄りがおらず、ただ一人の親族であるいとこのBさんとは大変仲が良かったそうです。こうした事情から、AさんはBさんに遺産をすべて遺贈する旨の遺言書を残していました。
Aさんが亡くなったことで、Bさんは相続手続きを専門家に依頼したいと思い、弊社グループに相談に来られました。
弊社グループでは、財産の名義変更などの手続きをお手伝いしたほか、相続税申告のサポートも行いました。
この事例では、他に親族がおらず、法的に有効な遺言書もあったため、スムーズに相続手続きを進めることができました。いとこに遺産をすべて遺贈する包括遺贈であったため、相続財産清算人を選任する必要もありませんでした。
7-2.特別縁故者の財産分与を受けた事例
- 被相続人:Cさん Cさんは独身で子はいない。両親はすでに死亡。兄弟姉妹はいない。したがって、法定相続人はいない。
- 相談者:Dさん(Cさんのいとこ)
CさんとDさんは、いとこという間柄でありながら、幼少期から実の姉妹と同じように親しくしていました。
やがてCさんが亡くなりましたが、遺言書は残されていませんでした。Dさんはどうしていいかわからなかったそうですが、知人の助言を受けて、弊社グループに相談に来られました。
弊社グループの専門家はDさんに、これまでのCさんとの関わりを丁寧にお伺いしました。その結果、Dさんは、Cさんの病院の送り迎えや見舞いのほか、家の整理整頓を行い、精神的な支えにもなっていたことがわかりました。
これだけの関わりがあれば特別縁故者として財産分与を受けられると判断し、「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」の手続きをお手伝いしました。申立ての結果、Dさんは特別縁故者として認められ、財産分与を受けることができました。
特別縁故者として財産分与を受けるためには、家庭裁判所でさまざまな手続きが必要ですが、専門家のサポートにより、いとこの遺産をスムーズに受け継ぐことができました。
8.いとこへの相続対策は専門家にご相談ください
いとこは法定相続人にはあたらないため、通常の手続きではいとこが遺産を相続することはできません。
身寄りのない人の遺産をいとこが相続するには、財産を残す人が生前に遺言書を作成しておく必要があります。遺言書がない場合は、いとこが自ら特別縁故者として申し出て財産分与を受けることもできます。
いとこへの遺産の承継について不安がある場合は、司法書士法人チェスターにご相談ください。経験豊富な司法書士が手続きを代行いたしますので、いとこの遺産の承継に関する手間や労力を省きつつ、円満な承継を実現します。
また、生前贈与にかかる贈与税や遺産を受け継いだときの相続税に不安がある場合は、税理士法人チェスターにご相談ください。相続に詳しい税理士が的確なアドバイスをいたします。
また、チェスターグループは法律事務所とも連携しておりますので、いとこの遺産分割で他の親族とトラブルが生じてしまった場合の解決もお任せいただけます。法律のプロが親族同士で納得のいく円満な解決へと導きます。
チェスターグループではあらゆる士業が全ての相続業務に対応しています
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































