いらない土地だけ相続放棄はできない│手放す方法をプロが解説
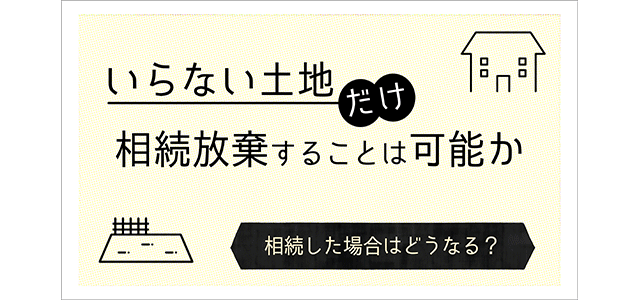
いらない土地だけを相続放棄することはできません。では不要な土地を相続した場合には、どうすればよいのでしょうか?不要な土地の手放し方や、2023年4月までに開始される予定の『相続土地国庫帰属法』について見ていきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.不要な不動産を相続した場合、どうなる?
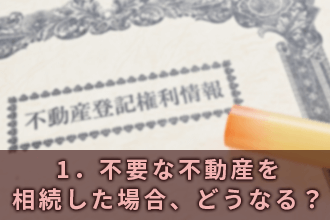
相続財産の中には不要な土地が含まれる可能性もあります。例えば都市部に暮らしているなら、遠く離れた場所にある実家は使い道がないかもしれません。そのような場合、不動産はどのように扱われるのでしょうか?
1-1.不要な不動産にも固定資産税がかかる
不要な土地であっても、相続すれば『固定資産税』が課されます。固定資産税は所有しているだけでかかる税金だからです。
東京の場合、『土地の固定資産税評価額×1.4%』で計算した税金を払わなければいけません。詳細な金額は、自治体から毎年送られてくる、固定資産税の課税明細書で確認できます。
参考:固定資産税・都市計画税(土地・家屋) | 税金の種類 | 東京都主税局
1-1-1.更地や特定空き家の場合は税額が上がる
固定資産税には住宅用地の特例措置があり、建物が建っている住宅用地であれば税金の負担が軽減される仕組みです。住宅1戸につき200平米までは課税標準が1/6に、200平米を超えた部分は1/3に減額されます。
そのため建物に住まないからといって取り壊すと、固定資産税が増額する可能性があるため注意しましょう。また建物があったとしても『特定空き家』に指定され改善の勧告を受けると、住宅用地の特例措置は受けられません。
その場合は更地とほぼ同等の固定資産税がかかります。
1-2.管理の手間や費用がかかる
相続した土地は定期的に管理しなければいけません。放置しておけば草木が生い茂り、荒れた状態になってしまいます。植木の枝が隣の土地へ侵入することもあるでしょう。
また荒れた土地はポイ捨てやいたずらなどが起こりやすくなります。周辺環境の悪化にもつながる事態です。近隣の人々に迷惑をかけ、トラブルが起こることもあるでしょう。
自分で管理できないときには、『空き家管理サービス』などの利用も検討しなければいけません。全く使っていない土地でも、管理のために手間や費用がかかります。
1-3.放置による他人への損害などリスク大
不要な不動産の管理を怠っていると、時間とともに建物が劣化します。万が一建物が倒壊し、近隣住民がけがを負った・隣地の建物を傷つけてしまったという事態になれば、損害賠償を請求されるかもしれません。
賠償金額はケースバイケースですが、数千万円から数億円といった高額になることもあるでしょう。このようなリスクを避けるためにも、不動産の管理が必要です。
2.期限内に相続放棄をして土地を手放そう

いらない土地を手放す方法の一つに『相続放棄』があります。相続放棄はできるタイミングが決まっている点に注意しましょう。また相続放棄したからといって、管理が不要になるわけではないことも要注意です。
2-1.他の財産含めて相続の権利を放棄する
相続放棄をすれば不要な土地を手放せます。ただし土地だけではなく、全ての相続財産を手放さなければいけません。相続放棄では相続人になるかならないかを決めるため、手続きをしたら他の資産も引き継げないからです。
そのため後から思わぬ財産が見つかったとしても引き継げません。不要な土地以外に引き継ぐ資産がない場合や、他にも負債があるようなケースでは、相続放棄をしてもよいでしょう。
ただし手続きできるのは、相続の開始があったことを知ったときから『3カ月以内』です。期限を過ぎると相続放棄をすることはできません。
2-2.相続放棄をしても管理義務が残る
相続放棄を選べば、固定資産税の納税義務はなくなります。ただし土地の『管理義務』自体は残ります。
放棄した土地の新たな管理者が決まるまでは、相続放棄をした人が管理責任者として手入れをします。責任を持って管理する立場になるため、土地が荒れて近隣に損害が発生すると、損害賠償請求の対象です。
放棄したとしても、当面は相続したときと同じように、管理し続ける必要がある点に注意しましょう。
3.不要な不動産以外を相続することは可能?
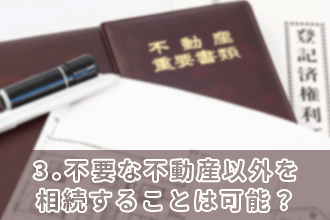
いらない不動産だけを相続しないで済む方法はあるのでしょうか?相続では財産を選んで引き継ぐといったことはできません。相続するなら全てを引き継ぎ、相続放棄するなら全てを放棄します。早い段階で情報収集を始めれば、自分たちに合う方法で不要な土地を処分できるはずです。
3-1.一切の権利義務を承継するため不可能
不要な不動産は引き継がず、その他の資産だけを引き継ぎたいと考える人は多いでしょう。しかし相続人が財産を引き継ぐときには、被相続人の相続財産全てを承継する決まりです。
そのため不要な不動産だけを引き継がないという選択肢はありません。『限定承認』という方法もありますが、この制度を利用して対策できるのは相続財産に負債があるケースです。
使い道のない土地は不要なものですが、負債ではなくプラスの財産です。そのためいらない土地への対策に使える制度ではありません。
3-2.相続する場合、引き継ぐのは誰?
いらない土地を相続する人は決まっていません。相続人同士で話し合い、まずは誰かが引き継いで遺産分割を終了させるケースが多いでしょう。
例えば長子が引き継ぐケースや、売却できる不動産を引き継いだ人が一緒に相続するケースが一般的です。不要な不動産を相続すると、将来にわたり管理コストが発生します。
そのため相続時には管理コストをまかなえるよう、分割割合を相談するとよいでしょう。遺産分割協議が難航した場合、相続人全員の共有にするケースもあります。
共有は登記上は可能ですが、購入を検討している人にとって複数人が登記されているのは懸念点です。また売却が決まったときの手続きも煩雑になるため、避けた方が賢明でしょう。
3-3.早いうちから情報収集を開始しよう
相続財産にいらない土地があることは、早い段階から分かっているケースが多いでしょう。時間に余裕があるうちに、さまざまな情報を集めておけば、自分たちにぴったりの選択肢を見つけやすくなるはずです。
税理士や司法書士などの専門家へアドバイスを求めることもポイントといえます。税理士であれば相続税対策に関する相談ができますし、司法書士であれば相続放棄や不動産登記に関する相談が可能です。
4.土地を手放すための「相続土地国庫帰属法」

これまでの制度では、相続した土地を完全には手放せませんでした。しかし『相続土地国庫帰属法』により、要件を満たし費用を負担すれば、土地を手放せるようになります。
2023年4月までには開始される予定の本制度の概要を確認しておけば、相続時の参考になるはずです。
4-1.所有者不明土地対策として生まれた新制度
相続土地国庫帰属法を利用すると、法務大臣の承認を受けることで、相続した土地の所有権を国庫に帰属させられます。これまでは1度相続した土地を手放すのは難しいことでした。
その結果、いらない土地を遺産分割せずそのまま放置するケースが発生しています。相続登記は義務ではないため、しなくても不利益が生じるわけではありません。
そのまま放置され続けると、相続人の死亡時にさらに相続が発生し、所有者はどんどん増え、最終的に不明になってしまうでしょう。このような事態を防ぐために作られた制度です。
うまく活用すれば、いらない不動産を手放し、次の世代へ負担を残さずに済みます。
4-2.法務局の審査、負担金などに注意
ただしどのような土地でも相続土地国庫帰属法の対象になるわけではありません。法務局が実施する要件審査に通過しなければ、対象にならない点に要注意です。
いらない土地が下記の特徴を満たしている場合には、審査に通過できません。
- 建物や通常の管理・処分を阻害する工作物がある
- 土壌汚染や埋設物がある
- 崖がある
- 権利関係争いがある
- 担保権等が設定されている
- 通路など他人によって使用される
加えて10年分の土地管理費用に相当する『負担金』も支払わなければいけません。国有地の宅地の管理費用には、柵や看板の設置費用・草刈り費用・巡回費用などが含まれます。10年分は200平米で約80万円が目安です。
5.寄付や無償譲渡で手放す方法

負担金が必要な相続土地国庫帰属法が利用しづらい場合、『寄付』や『無償譲渡』を利用してもよいでしょう。ただし必ずしも譲渡できるとは限りません。また譲渡の相手によっては、お互いに税金の負担が必要なケースもあります。
5-1.国や自治体へ寄付することを相談する
国や自治体へ土地を寄付して手放す方法もあります。ただし自治体がうまく扱えない土地では、基本的に寄付を受け付けてもらえないでしょう。
土地にかかる固定資産税は、自治体にとって重要な収入源だからです。不要な土地の寄付に全て応じていたのでは、自治体は土地の管理費用ばかり増え、税収は落ち込んでしまいます。
自治体にとって有用な土地であれば、寄付を受け付けてもらえる可能性があるため、まずは土地のある自治体へ連絡し相談してみるとよいでしょう。
5-2.近隣の住民など個人へ譲渡する
地方にある両親から相続した土地は、都心部に住む人にとっては不要です。しかしその近くに住む人は、あればうれしいものの可能性もあります。近隣に土地を必要としている人がいるなら、譲渡してもよいでしょう。
ただし、時価よりも著しく低い価額での譲渡は、低額譲渡として贈与にあたるため、譲り受ける人は時価との差額に対する贈与税を負担しなければいけません。対価の支払いを求めず贈与する場合は、権利関係をはっきりさせられるよう、贈与契約書を作成し内容を明確にしておくことも重要です。
贈与の手続きは不動産会社による仲介を受けられません。トラブルを避けるには弁護士や司法書士のサポートを受けるのがおすすめです。
譲渡する相手が法人の場合、無償譲渡であっても所有者は対価を受け取ったとみなされます。譲った側も所得税を課される点に要注意です。
6.少しでも手元にお金を残すには
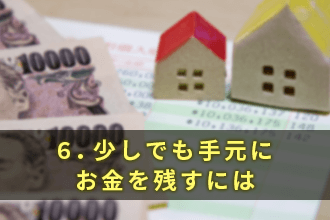
せっかく相続した不動産を有効活用したいと考える人は多いでしょう。少しでもお金を残したいなら『不動産会社』や『空き家バンク』を利用して売却するとよいかもしれません。手放さずに貸し出し、収益化するのも一つの方法です。
6-1.不動産屋に仲介を依頼して売却する
土地を売却してお金を残すには、不動産会社へ仲介を依頼する方法があります。自力で土地の買い手を見つけるのは難しいため、不動産会社を窓口として売却する方法です。
まずは信頼できる不動産会社を探し、土地の測量や境界の測定をしてもらいましょう。買い手が付いたら売買契約を結び、手続きへ進みます。買い手との売買契約が成立したら、不動産会社へ仲介手数料を支払います。
寄付や無償での譲渡でもいいから手放したいという状態であれば、思い切って相場より安い価格設定で売り出すのも一つの方法です。
6-2.空き家バンクに登録
地方への移住を促すための制度の一つに、空き家バンクがあります。自治体へ登録された空き家の情報を、Web上で公開して買い手を探すサービスです。
利用するには、不動産のある自治体で空き家バンクの登録を申請しましょう。自治体の担当者が現地調査で状態を確認したら、空き家の情報がWeb上で公開されます。
買い手が表れたら条件交渉をして、合意の上で売却する流れです。空き家バンクへ登録するときには、所有権移転登記をしておくとトラブル防止に役立ちます。
6-3.手放さずに活用して収益を得る
売却せず収益を得るのも一つの方法です。例えば下記のように活用すれば、収益を得られる可能性があります。
- 土地を貸し出す
- 駐車場経営
- 太陽光パネルの設置
- 市民農園の運営
- トランクルームの設置
- アパート経営
立地によって土地活用の方法はさまざまです。その場所に合った方法で活用できれば、安定収入につながるかもしれません。
土地活用の相談先は、活用方法により異なります。アパート経営であれば、ハウスメーカーや工務店などへ、駐車場経営であれば専門の業者か不動産会社へ相談するのが一般的です。
相続は次の世代へも続きます。自分の死亡時に相続が発生したとき、相続人が困るような状態は避けなければいけません。土地が大き過ぎるなら分筆し扱いやすい大きさにしておくのも有効です。
7.専門家に相談して最善の選択をしよう
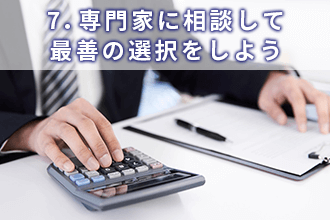
相続が発生するまで時間があるなら、いらない土地をどのように扱うのがよいか、専門家へ相談しましょう。相続放棄だけでなく、土地の売却や活用といった選択肢を教えてもらえるかもしれません。
今後は完全に土地を手放す、相続土地国庫帰属法も実施されます。早めに相談しておけば、複数の選択肢の中から、自分たちにぴったりの方法を選びやすいはずです。
土地の相続にまつわる税金についての相談は『税理士法人チェスター』へ問い合わせるとよいでしょう。
『不動産の相続』について詳しく知るには、下記もご覧ください。
土地・家屋の相続に必要な手続き・費用を専門家が詳しく解説|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































