相続登記の期限は3年!令和6年4月から義務化、放置すると10万円の罰則も
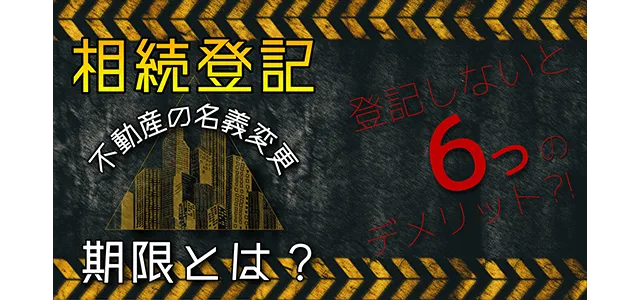
不動産の相続登記は今後義務化され、3年の期限が設けられます(令和6年4月1日施行)。
これまでは相続登記に期限がなく手続きを先送りするケースもありましたが、今後は速やかに相続登記をすることが求められます。
さらに、施行日より前に相続した不動産も登記が義務づけられるため、相続登記ができていない不動産がある場合は対応を急がなければなりません。
この記事では、相続登記に期限を定めることになった不動産登記法の改正点や、相続登記をしないことのデメリットについて解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続登記の期限は?
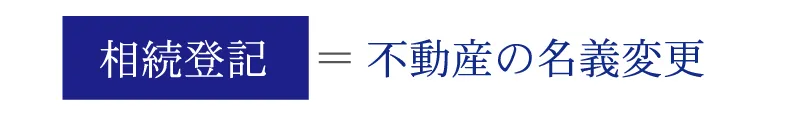
相続登記、つまり不動産の名義変更は、これまで義務づけられているものではありませんでした。
法律上の義務ではなかったため、いつまでに相続登記しなければならないという期限がなく、相続登記をしないで放置していても罰せられることはありませんでした。
不動産を相続したにもかかわらず、相続登記をしない人もいます。
しかし、相続登記がされていないと、所有者が亡くなって代替わりしたときに実質的に誰のものかがわからなくなってしまいます。このような経緯で実際の所有者がわからなくなった不動産が全国的に増えていて、再開発や災害復興の妨げになるケースもあります。
そのため、令和6年4月1日から相続登記が義務づけられ、3年の期限が設けられることになりました。
2.改正された不動産登記法の内容
令和3年4月に不動産登記法の改正法案が成立し、不動産を相続したときの登記が義務づけられることになりました。
この章では、法改正によって不動産登記がどのように変わるかをご紹介します。
「相続登記の義務化・期限の設定」と「相続人申告登記の新設」は令和6年4月1日に施行されますが、その他の改正は令和8年4月までに施行される予定です。
2-1.相続登記の義務化・期限の設定
令和6年4月1日以降、不動産を相続した相続人は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。
相続した場合のほか、遺言で遺贈された場合も同様です。
相続登記の義務化については、下記の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
相続登記の義務化はいつから?違反者への罰則/新制度に備える方法も解説
2-2.相続人申告登記の新設
相続登記が義務づけられることにあわせて、相続人が簡単な方法で登記申請の義務を果たせる制度ができます。
相続人申告登記は、相続人が自ら「登記上の名義人の相続人であること」を法務局に申し出る制度です。
正式な相続登記ではありませんが、申し出をした相続人の氏名や住所などが登記簿に記載されます。
相続人であれば1人で申し出ることができ、相続登記に比べて提出資料は簡素化されています。
相続争いが起こったなど3年の期限までに相続登記ができない場合に、ひとまず相続人申告登記をするといった利用方法が考えられています。
相続人申告登記をしたのち、遺産分割が成立して不動産の所有者が確定したときは、その日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2-3.所有不動産記録証明制度の新設
簡単な方法で登記申請の義務を果たせる制度としてもう一つ、所有不動産記録証明制度ができます(令和8年2月2日施行)。
これは、ある特定の人が登記上の名義人となっている不動産の一覧表を発行する制度です。
これまで不動産の登記記録は土地や建物など物件ごとに作成されていて、ある特定の人の名義の物件を一覧できる仕組みはありませんでした。そのため、不動産の所有者が亡くなったときに、相続人がどの不動産を相続登記すべきか把握しきれないという問題がありました。
所有不動産記録証明制度のもとでは、故人が所有していた不動産を一覧表で確認できるため、相続登記の申請漏れを防ぐことが期待されます。
2-4.登記名義人の死亡情報の表示
不動産の登記上の名義人が死亡したときに、その事実が登記簿に記載される制度も始まります(令和8年4月1日施行)。
法務局が住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)などから登記名義人の死亡を把握した場合は、職権で名義人の死亡を登記簿に記載できるようになります。
死亡の事実は符号で表示されますが、登記簿を見れば名義人が存命かどうかを確認できるようになります。
ただし、この手続きは名義人が死亡したことを登記簿に表示するだけで、正式な相続登記ではありません。相続人は別途、相続登記を申請する必要があります。
2-5.住所変更登記の義務化
登記名義人の転居に伴う住所変更も登記が義務づけられます(令和8年4月1日施行)。
相続登記の義務化は、土地の所有者を明らかにすることが目的です。しかし、登記上の名義人が転居してしまうと、連絡が取れなくなってしまいます。
制度に実効性を持たせるため、名義人の住所に変更があった場合は、2年以内に登記を申請することが義務づけられます。
2-6.不動産所有者の生年月日等の提供
新たに不動産を所有する個人は、氏名・住所のほか生年月日等の提供が義務づけられます(令和8年4月1日施行)。
個人の生年月日等は、法務局が住基ネットから登記名義人の異動情報を取得するために利用されます。
法務局が登記名義人の氏名・住所の異動を把握した場合は、職権で変更登記ができるようになります。ただし、名義人が個人である場合は、名義人に意向を確認したうえで変更登記が行われます。
なお、氏名・住所以外の生年月日等は法務局内でデータとして保持するものであり、登記簿には記載されません。
3.法改正前に相続した不動産も相続登記しなければならない
相続登記の義務化は令和6年4月1日に施行されますが、対象は施行日以降に相続する不動産だけではありません。
令和6年3月以前に相続してまだ相続登記をしていない不動産も、相続登記が義務づけられます。
法改正前に相続した不動産にもさかのぼって適用しなければ、所有者がわからない不動産の発生を抑えることができず、相続登記を義務化する意味がなくなってしまうためです。
法改正前に相続した不動産は、次のいずれか遅い日から3年以内に登記を申請する必要があります。
- 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日
- 改正法の施行日
ほとんどの場合、改正法の施行日(令和6年4月1日)の方が遅いため、施行日から3年以内に登記申請をする必要があります。
ただし、何らかの事情で施行日より後に不動産を相続したことを知った場合は、その知った日から3年以内に登記の申請をすればよいことになります。
4.相続登記しないことによって生じる6つのデメリット!
相続登記が義務づけられた後でも申請の期限は3年後であるため、申請を先送りする人もいるかもしれません。
しかし、不動産を相続したときは、期限まで待たずにできるだけ早く相続登記することをおすすめします。相続登記をしていなければ、土地の売却ができないなどさまざまなデメリットがあるからです。
この章では、相続登記をしないことによって生じるデメリットを6つご紹介します。
4-1.不動産が売却できない
不動産を相続したにもかかわらず相続登記をしなければ、その不動産を自由に売却することができません。
相続登記をしていない不動産の登記上の名義は亡くなった被相続人のままであり、相続したことを他の人に証明することができないからです。
4-2.不動産を担保にできない
不動産を売却できないことと同じ理由で、相続登記されていない不動産を担保にしてお金を借りることはできません。
4-3.後で登記するときに費用が高くなる
速やかに相続登記をしなければ、費用の面でもデメリットが生じます。
相続登記をしていない不動産は、相続人全員で共有している状態になります。
相続登記を先送りしている間に相続人が亡くなった場合は、その亡くなった人の相続人が共有者に加わります。
共有者が増えてから相続登記をしようとすると、必要な書類の取得費用が高くなります。
また、手続きが複雑になると司法書士に依頼する場合がありますが、司法書士に依頼すると報酬が必要になります。
4-4.登記の手続きが困難になる恐れも
相続登記を先送りしている間に相続人が認知症になると、手続きが増えてしまいます。
認知症などで相続人の判断能力が低下した場合は、成年後見人を立てなければなりません。成年後見人を立てるには家庭裁判所への申し立てが必要であり、手続きに時間がかかります。
このほか、相続登記に必要な書類が入手できず手続きが困難になる場合もあります。
相続登記の申請では、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票が必要になることがあります。これらの書類の保存期間は、令和元年6月20日以降は150年となりましたが、それ以前は5年でした。
したがって、過去に亡くなった人については、住民票の除票や戸籍の附票がすでに廃棄されていて入手できない場合もあります。
必要書類がすでに廃棄されていて提出できない場合の登記手続きは、個人で対応することは困難であり、司法書士に依頼することになります。
4-5.一部が売却・差し押さえされる可能性もある
相続登記をしていない不動産は相続人全員で共有している状態であり、他の相続人が勝手に自分の持分を売却する可能性があります。
そのほか、相続人が借金をしていて返済が困難になっている場合は、債権者に持分を差し押さえられる恐れもあります。
4-6.法施行後は期限を過ぎると罰則を受ける
相続登記や住所変更登記が義務づけられると、罰則が適用されます。
正当な理由がなく相続登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科されます。また、正当な理由がなく住所変更登記を怠った場合は、5万円以下の過料が科されます。
5.相続登記の手続きの方法と必要書類
相続登記の申請は法務局で行います。この章では、相続登記申請手続きの方法と必要書類について解説します。
5-1.必要書類を準備する
まず、相続登記に必要な書類を準備します。準備する書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 相続登記申請書 | 様式と記載例(法務局ホームページ) |
| 故人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、 相続人全員の戸籍謄本 | 法定相続情報一覧図の写しでもよい |
| 故人の本籍の記載がある住民票の除票または戸籍の附票 | 故人の最後の氏名及び住所が登記記録と異なる場合や本籍が登記記録の住所と異なる場合に提出 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税算定の根拠として使用 |
| 相続関係説明図 | 提出すれば手続後に戸籍謄本が返還される |
| 不動産を相続する人の住民票の写し | 相続登記申請書に住民票コードを記載した場合は不要 |
| 遺言書 | 遺言書がある場合に提出 |
| 検認済証明書 | 検認が必要な遺言書がある場合に提出 |
| 遺言執行者の印鑑証明書 | 遺言執行者がいる場合に提出 |
| 遺産分割協議書の写しと相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議をした場合に提出 |
これらの書類の取得方法は下記の記事をご覧ください。
相続登記の必要書類とは?取得の仕方・有効期限も一覧でわかりやすく紹介
5-2.法務局の窓口で申請
必要書類が準備できれば、不動産がある場所を管轄する法務局の窓口で申請します。
法務局の管轄は、法務局ホームページで調べることができます。
法務局ホームページ 管轄のご案内
わざわざ法務局に出向くのは面倒かもしれませんが、窓口で相談しながら手続きができる点は郵送やオンライン申請にないメリットです。
5-2-1.郵送やオンラインでの申請も可能
相続登記は、郵送やオンラインで手続きすることもできます。
郵送で申請する場合は、管轄の法務局に書留郵便で送付します。提出書類の返還を希望する場合や、登記完了証を受け取りたい場合は、返送用の封筒と切手を同封します。
オンラインで申請する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要で、パソコンの初期設定などを行う必要があります。
具体的な申請方法は、下記の記事や法務局ホームページをご覧ください。
法務局ホームページ 不動産の所有者が亡くなった(相続の登記をオンライン申請したい方)
6.相続登記するにはどれくらいの費用がかかる?
相続登記にかかる費用は、不動産の価格や手続きに必要な書類の数によって変わりますが、不動産1件あたり数十万円を見込んでおくとよいでしょう。
相続登記では、登録免許税、司法書士報酬、必要書類の取得費用などが必要です。
登録免許税は、登記する不動産の固定資産税評価額の0.4%(相続人以外が取得する場合は2.0%)で、不動産の価格によって大きく変わります。
司法書士報酬は10万円程度と考えておくとよいですが、登記する不動産の数や手続きの難易度に応じて報酬が高くなることもあります。
必要書類の取得費用とは、戸籍謄本や住民票の交付手数料、登記する不動産の登記事項証明書の取得費用などです。これらの費用も、相続人の数や不動産の数などによって変わります。
相続登記にかかる費用については、下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
7.面倒な手続きは司法書士に依頼がおすすめ
相続登記の申請手続きは自分で行うこともできます。しかし、手続きが複雑になる場合や時間が取れない場合は、司法書士に手続きを依頼するとよいでしょう。
特に次のような方は、司法書士に依頼することをおすすめします。
- 何代にもわたって相続登記をしていなかった
- 相続登記の期限が迫っている
- 相続する不動産が遠方にある
- 相続する不動産の数が多い
- 不動産の権利関係が複雑である
- 遺産分割協議書も同時に作成したい
相続登記の申請を司法書士に依頼すると、必要書類の準備や申請書の記入についてサポートを受けることができます。
提出書類の不備で手続きが滞ることがなく、相続登記の申請をスムーズに進められるでしょう。
8.まとめ
ここまで、不動産登記法の改正点や、相続登記をしないことのデメリットなどについて解説しました。
令和6年4月1日から相続登記が義務づけられることになり、不動産を相続した場合は3年以内に登記申請をしなければなりません。
不動産を相続したときは、期限を待たずに速やかに相続登記することをおすすめします。相続登記を先送りすると、不動産を売却できないなどのデメリットがあります。
司法書士法人チェスターでは、相続登記の申請手続きだけではなく、相続不動産に関する遺産分割協議書や相続関係説明図の作成なども、追加料金なしでご依頼いただけます。(ただし、相続登記に必要な各種書類の代行取得は別料金となります。)
また、チェスターグループに所属している専門家と協力関係にあるため、相続税申告の依頼や、相続した不動産の売却まで、ワンストップで対応いたします。
すでに相続が発生したお客様は、初回相談(60分)が無料となります。まずはお気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































