ビルを相続しても大丈夫!相続税の計算シミュレーションと節税対策
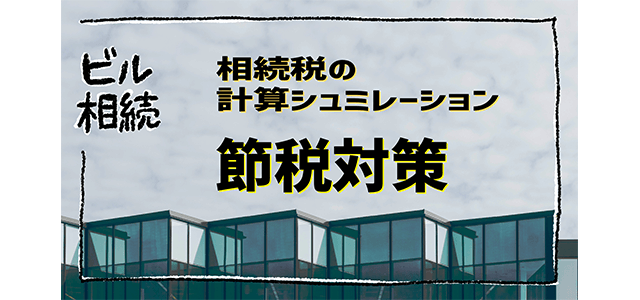
ビルを相続したときの相続税額は、固定資産税の評価額に左右されます。ビルのように評価額の高価な物件は、一般的に相続税が高額です。税金が高額となるからこそ、節税対策により評価額を抑えることが大切です。
そのためにはビル相続時における相続税の計算方法や利用できる節税対策を知っておく必要があります。相続時の注意点も確認しながら、ビルの相続で支払う相続税額をシミュレーションしてみてください。
この記事の目次 [表示]
1.ビルの相続税計算シミュレーション
不動産の相続税を計算する方法は複雑なため、4つのステップに則って順番に計算しましょう。相続税の計算手順は、下記のとおりです。
不動産の相続税を計算する4ステップ
- 土地の評価額を割り出す
- 建物の固定資産税評価額を調べる
- 課税総額を計算する
- 相続税額を計算する
不動産の相続税は、税額を計算する前に評価額の割り出しが必要です。複雑な計算でも、一つずつ順番に計算することで正確な相続税額を割り出せます。
1-1.ステップ1‐土地の評価額を割り出す
相続税の計算で考慮すべき土地の価額は「相続税評価額」です。売買時の時価とは異なるので注意しましょう。
土地の相続税評価額は、路線価方式にて割り出します。路線価とは、路線沿いの土地1平方メートル当たりの価額です。詳細は国税庁のサイトで検索できます。
路線価方式で土地の価額を割り出す計算式は「路線価×相続した土地の面積」です。相続した土地上の貸しビルにテナントが入っている場合は、借地権割合も考慮します。また土地の形状や用途によっては、例外的に一定割合の補正をかけた計算が必要です。
なお路線価がない地域にある土地は、相続した土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じることで相続税評価額を計算できます。
1-2.ステップ2‐建物の固定資産税評価額を調べる
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額の1.0倍とします。まずは建物の固定資産税評価額から確認しましょう。
家屋
固定資産税評価額に1.0を乗じて計算します。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。
(引用:No.4602 土地家屋の評価|国税庁)
固定資産税評価額とは、各市町村が管轄区域内の建物に固定資産税を課税するための評価額です。固定資産税評価額は、市区町村から送られる固定資産税の納税通知書に記載されています。
固定資産税評価額は、建築価格のおよそ50%~70%が目安です。さらに相続した家屋が貸家の場合は、相続税評価額が低下します。なぜなら他人に貸している家屋は、自宅用より制約があり、流動性がないと評価されるためです。貸家の場合は、全国一律で30%が差し引かれます。貸家の相続税評価額は、下記の計算式で算出します。
貸家の相続税評価額計算式
固定資産税評価額×(1-30%)=貸家の相続税評価額
固定資産税評価額から30%を差し引いた額が貸家の相続税評価額となります。
1-3.ステップ3‐課税総額を計算する
相続税を計算する前に、相続財産の合計を調査しましょう。基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額の割り出しが必要です。相続財産は現預金や不動産以外に、みなし相続財産(死亡保険金など)がある可能性についても留意しましょう。
相続財産の合計額が判明したら、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を計算します。
今回は、被相続人の死亡により配偶者と2人の子が8000万円の遺産(土地5000万円、家屋等その他の財産3000万円)を相続するケースについて計算します。
相続財産の合計8000万円に対して相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。課税遺産総額は、以下のように計算します。
| 項目 | 計算式 |
|---|---|
| 基礎控除額 | 3000万円+600万円×3人=4800万円 |
| 課税遺産総額 | 8000万円(相続財産総額)-4800万円(基礎控除額)=3200万円 |
相続財産総額が基礎控除額を下回るケースもあります。その場合は、課税遺産総額がゼロとなるため相続税はかかりません。
1-4.ステップ4‐相続税額を計算する
課税遺産総額を割り出したら、それを法定相続分で分けて各相続人の相続税額を算出します。本記事のケースの法定相続分は、妻が1/2、子2人がそれぞれ1/4ずつです。まずは法定相続分に応ずる取得金額を、以下のとおり計算します。
| 法定相続人 | 計算式 |
|---|---|
| 妻 | 3200万円(課税遺産総額)×1/2=1600万円 |
| 子1 | 3200万円(課税遺産総額)×1/4=800万円 |
| 子2 | 3200万円(課税遺産総額)×1/4=800万円 |
法定相続分に応ずる取得金額をもとに、相続税の税率をかけて相続税を割り出します。相続税の税率は「法定相続分に応ずる遺産の取得金額」に応じて段階的に定められています。具体的な税率は、下記のとおりです。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | なし |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
(参考:No.4155 相続税の税率|国税庁)
本記事のケースでは、法定相続分に応ずる取得金額が妻1600万円、子2人が800万円ずつです。取得金額に応じて、税率は妻15%、子10%となります。それぞれの相続分に税率をかけた合計額が、相続税の総額です。
| 相続税額 | 計算式 |
|---|---|
| 妻 | 1600万円×15%-50万円(控除額)=190万円(①) |
| 子1 | 800万円×10%=80万円(②) |
| 子2 | 800万円×10%=80万円(③) |
| 相続税の総額 | ①+②+③=350万円 |
相続税の総額を実際の相続割合で按分します。今回は法定相続分で遺産を分割したことにします。
| 相続税を按分 | 計算式 |
|---|---|
| 配偶者の相続税額 | 350万円×1/2=175万円 |
| 子1の相続税額 | 350万円×1/4=87万5000円 |
| 子2の相続税額 | 350万円×1/4=87万5000円 |
配偶者には「配偶者の税額軽減」制度が適用されます。配偶者の税額軽減とは、配偶者の遺産相続で「1億6000万円」と「法定相続分相当額」のいずれか高いほうの金額額にあたる部分まで、配偶者の相続税を控除する制度です。
本記事のケースでは、妻の相続分が1億6000万円に満たないため相続税がかかりません。そのため子2人の相続税額87万5000円ずつが、実際にかかる相続税となります。
| 妻 | 子1 | 子2 |
|---|---|---|
| 0円 | 87万5000円 | 87万5000円 |
2.ビルの相続で利用できる節税対策
ビルの相続時は、土地の評価額や固定資産税評価額によって、相続税が高額になる場合があります。このような場合は、各種制度を活用することで節税可能です。ビル相続の節税対策では、下記の制度を利用できます。
ビル相続における節税対策
- 小規模宅地等の特例
- 相続時精算課税制度
- 生前贈与
これらの制度を利用するためには、規定の条件を満たす必要があります。制度の利用を検討するに当たっては、まず自身のケースが条件を満たすかどうかを確認しましょう。
2-1.小規模宅地等の特例を活用する
被相続人が居住用や事業用として使っていた土地を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用しましょう。相続税を減額できる可能性があります。小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を最大80%減額できるという制度です。
本記事のケース(土地5000万円、家屋等その他の財産3000万円を相続)をもとに、小規模宅地等の特例を適用する場合の評価額を計算します。
相続したビルをすべて賃貸していた場合は、土地はすべて貸付事業用宅地等となり、小規模宅地等の特例により宅地の評価額が50%減額されます。また、ビルの半分を自宅、残り半分を賃貸用として使用していた場合は、自宅部分に係る宅地は特定居住用宅地等として評価額が80%減額され、賃貸部分に係る宅地は貸付事業用宅地等として50%減額されます。
ビルの用途ごとの宅地の評価額は、以下のように計算します(宅地の面積は小規模宅地等の特例の限度面積を超えないものとします)。
| ビルの用途 | 宅地の評価額の計算式 |
|---|---|
| すべて賃貸 | 宅地はすべて「貸付事業用宅地等」として50%減額 5000万円-5000万円×50%=2500万円 |
| 半分は自宅 半分は賃貸 | 宅地の半分は「特定居住用宅地等」として80%減額 5000万円×1/2-5000万円×1/2×80%=500万円 もう半分は「貸付事業用宅地等」として50%減額 5000万円×1/2-5000万円×1/2×50%=1250万円 自宅部分と賃貸部分の評価額を合算 500万円+1250万円=1750万円 |
ビルの半分を自宅、残り半分を賃貸用として使用していた場合、宅地の評価額は1750万円になります。この1750万円に家屋等その他の財産3000万円を足すと、相続財産の総額は4750万円です。本記事のケースにおける基礎控除額である4800万円以下となるため、相続税はかかりません。
2-2.相続時精算課税制度を利用する
将来の値上がりを期待できる不動産がある場合は生前贈与したほうが、相続税を節税できる可能性があります。この場合、「相続時精算課税制度」を活用しましょう。相続時精算課税制度とは、生前贈与において用いられる課税制度の特例です。贈与時に課税される贈与税については、2500万円を限度とした控除枠があります。
相続時精算課税制度を適用した場合、生前贈与財産は贈与者の死亡時に相続税の対象になります。この場合の不動産の評価額は「生前贈与時点での評価額」です。つまり相続の時点で不動産の価額が値上がりしていた場合でも、相続税は特例により生前贈与時点での評価額で計算されるので節税効果があります。
なお控除限度額の2500万円を超えた分については、20%の贈与税がかかります(この贈与税は相続税申告時に精算できます)。また相続時精算課税制度を選択した場合は、相続時に小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなるため注意しましょう。
2-3.生前贈与で特定の人物にビルの権利を取得させる
相続時精算課税制度の条件を満たさない場合は、暦年贈与により相続税を節税できます。暦年贈与とは、毎年の贈与税の基礎控除額110万円を活用して、数年を掛けて自分の財産を子どもや孫などの親族に生前贈与していくことです。生前の間にビルの権利を特定の人物に贈与することで、亡くなったときの相続額が減り、相続税の減額につながります。
注意しておきたいポイントは、相続開始日からさかのぼって一定期間内に生前贈与された財産が、相続財産として計算されてしまうことです。相続財産に加算される対象の期間は相続開始日からさかのぼって「3年以内」ですが、令和9年以降は段階的に「7年以内」まで延長されます。贈与の時期によっては相続財産として扱われてしまうため、生前贈与を考えているならば早めに実施しましょう。
なお、贈与税は基礎控除により「1年のうち1人当たりの贈与額が110万円以内」であれば課税されません。基礎控除の範囲で生前贈与することで、贈与税の負担はなくなります。
3.相続したビルの管理手法は2つに分けられる
相続したビルの放置は管理費用が負担となるため「売却して現金化」「資産価値を向上させて収益化」のいずれかを選びましょう。使用しないビルを保有しても、固定資産税やメンテナンス費用は必要です。お金を無駄にしないためにも、売却または有効活用の判断を早めに検討しましょう。
3-1.売却して現金化する
相続したビルをすぐに手放したい場合や管理する余裕がない場合は、売却して現金化しましょう。売却の方法は、下記のとおりです。
相続したビルを売却して現金化する手順
- 相続人を決める
- 業者を選ぶ
- 売却する
まずはビルの相続人を決めます。ビルを売却する前には、相続人名義の不動産とするために「所有者名義の変更(相続登記)」が必要です。
ビルを売却する場合は、相続や税金に詳しい専門の不動産業者に販売を依頼しましょう。業者を選択できたら不動産売買の「媒介契約」を結びます。媒介契約とは、不動産業者に売却を依頼し、売却が成立したら仲介手数料を支払う契約です。
3-2.ビルの資産価値を向上させて収益化する
相続したビルの固定資産税やメンテナンス費用を支払う余裕がある場合は、ビルの価値を向上させてから収益を得る方法がおすすめです。
よりよいテナントを集めるためにも、専門のコンサルタントに相談するのがよいでしょう。立地条件やビルの状態などから、テナントを集めるコツや長く家賃収入を得るコツについてレクチャーしてもらえます。
ビルの維持にかかる費用を支払う余裕があり、有効活用したいと考えている場合は、資産価値向上と収益化を目指してみてください。
4.ビルを相続する際の注意点
ビルの相続では、被相続人が負っていた義務や遺産の分割方法についても確認しておきましょう。これらのポイントを意識することで、ビルの相続税を節約できる可能性が広がります。
4-1.賃貸人として負うべき義務がないか確認する
相続人は被相続人の財産だけでなく、ビルの賃貸人としての義務も承継します。そのためビルの相続人は、自分に発生する義務の確認が必要です。ビルの管理やメンテナンスの義務は、相続発生時に法定相続人全員が負うことになります。
たとえばビルの管理やメンテナンスのため、相続人の一人に相続分を超える費用の負担が発生した場合です。当該相続人は、ほかの相続人が本来負担すべき分の費用を請求できます。
また被相続人が生前に建てたビルの借金返済の債務が残っている場合も同様です。相続人が複数いる場合は、全員が法定相続分の債務を負うことになります。
このようにビルを相続する場合は不動産だけを引き継ぐのではなく、故人が負っていた義務の引き継ぎも必要です。相続人間の費用負担や借金返済についてはトラブルの原因となりやすいため、相続時点でどのような義務があるか明確にしておきましょう。
4-2.遺産分割方法は代償分割がおすすめ
不動産を複数人で相続する場合は、トラブルを防ぐためにも代償分割による遺産分割がおすすめです。代償分割とは、共有財産である不動産を一人の相続人が取得し、ほかの相続人に対して持分に応じた金額を支払う方法です。
本記事のケース(土地5000万円、家屋等その他の財産3000万円を相続)に当てはめると、法定相続分は妻が4000万円、子2人がそれぞれ2000万円ずつとなります。妻が遺産のすべてを取得した場合は8000万円を引き継ぐことになり、相続額が本来よりも4000万円プラスです。代償分割では妻が多く相続した分の金額を子2人に支払うことで、不動産を保有しつつ公平に相続できます。
代償分割以外の方法には、各相続人の持分で不動産を所有できる共有もあります。共有は管理費用の負担や売却で、相続人同士のトラブルに発展しやすいことがデメリットです。不動産のように持分を物理的に分けられない財産を相続する場合は、公平性を担保できる代償分割がトラブルを防ぐことにつながります。
5.ビルの相続は節税対策を理解することが大切
ビルの相続では、相続税を計算する順序や適用されるルールを理解しましょう。正しい手順で計算することが、相続税評価額の減額につながります。
しかし不動産に関する相続税の計算は、細かいうえに複雑です。節税対策についても、減額できるルールを見極めなければなりません。相続人としての負担やトラブルを軽減するためにも、ビルの相続については早めに相続税の専門家に相談することをおすすめします。
相続税に詳しい税理士法人チェスターであれば、経験豊富な税理士が遺産総額の確定から相続税の計算、最適な節税対策について適切なアドバイスを提供できます。ビルの相続でお困りの場合は、ぜひチェスターへお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編






































