連帯債務者が死亡した場合の相続は?ケース別事例や事前対策も解説
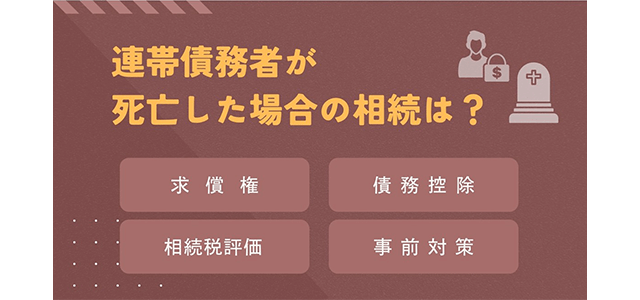
相続の対象となる財産には、現金や不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。また、亡くなった人が連帯債務者となっていた場合、相続人はその地位を引き継ぐことになります。
連帯債務者としての地位を引き継いだ相続人は、債権者から支払いを求められたときに応じなければなりません。連帯債務を相続する場合は、引き継ぎ方や対策を慎重に検討することが大切です。
そこで今回は、連帯債務者が亡くなった場合の相続や対策方法などを相続税専門の税理士がわかりやすく解説します。
この記事の目次 [表示]
1.連帯債務とは?連帯債務者の求償権と相続税
連帯債務とは、1つの債務に対して複数の債務者それぞれがすべてを弁済する義務を負うことです。1人の債務者が債務を弁済したのであれば、他の債務者が弁済をする必要はありません。
一方で、連帯債務者には催告の抗弁権がありません。催告の抗弁権とは、連帯債務者が債権者から債務の履行を求められたときに「まずは主債務者に請求してください」と言える権利のことです。
また、債務の全額を負担した債務者は、他の連帯債務者に対して一定金額の支払いを求めることができます。これを「求償権」といいます。
主債務者と連帯債務者のそれぞれが負担している債務は、個別独立のものとされています。そのため、原則として債務者の各人に生じた事由は互いに影響を及ぼしあいません。
たとえば、債務者の1人が債務の存在を認めて「承認」という行為に該当し、債務の時効が中断(民法第147条)して期間のカウントがリセットされたとしても、他の債務者の時効が中断することはありません。
1-2.連帯債務者の例
たとえば、主債務者のAさんが金融機関から3,000万円を借り、BさんとCさんが連帯債務者になったとしましょう。この場合、3人全員が3,000万円の返済義務を負っており、金融機関は誰に対しても全額の返済を請求できます。
Aさんが3,000万円を金融機関に返済した場合、BさんとCさんは返済する必要はありません。しかし、Aさんが求償権を行使し、BさんとCさんに対して支払いを請求する可能性はあります。
また、金融機関がBさんに返済を請求した場合「まずはAさんに返済を請求してください」と要求することはできません。
1-3.連帯保証との違い
連帯債務とよく似た仕組みのものとして「連帯保証」があります。連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することです。
連帯債務の場合、連帯債務者はお金を借りた人(主債務者)と同じ立場です。一方で連帯保証の場合、連帯保証人は債務者ではなく、あくまで主債務者が借りたお金を返済しないときに肩代わりをするという立場にすぎません。
一方で、連帯保証人にも催告の抗弁権がなく、たとえ債権者から債務の履行を要求されたとしても、主債務者に先に請求するよう求められない点は連帯債務者との共通点といえます。
2.連帯債務者間の求償関係の具体例と相続税評価
連帯債務では、債権者に対する負担割合を相互に定めることができます。負担割合は、求償権を行使したときや連帯債務を相続するときに関係します。
2-1.求償権とは
求償権とは、 連帯債務者間で負担割合を超えて弁済した場合に超過額を請求することができる権利のことです。
債務者の1人が債務を弁済したとき、他の債務者に対して求償権を行使することで、自分自身の負担割合を超えて負担した金額の支払いを求めることができます。
例】Aさんが主たる債務者として金融機関から100万円を借り入れ、Bさんが連帯債務者になるケースで考えてみましょう。負担割合はAさん:Bさん=7:3であるとします。
仮にBさんが100万円を弁済した場合、Aさんに対しては負担割合を超えて弁済したことになる70万円を請求することができます。
ただし、負担割合は債務者のあいだで取り決めているものに過ぎません。そのため債権者に対しては、債務者のそれぞれが独立して100万円を支払う義務を負っています。
なお、連帯保証人にも求償権があります。そのため連帯保証人が代わりに債務を弁済した場合、求償権を行使することで主債務者にも支払いを請求することが可能です。
2-2.連帯債務は債務控除できる場合も
相続税を計算する際、借入金や未払金などのマイナス財産を遺産総額から控除できます。これを「債務控除」といいます。連帯債務者としての義務を負っている場合も、借金を抱えている状態と同じです。そのため被相続人が連帯債務者であった場合、一定金額を遺産総額から控除できます。
ただし、連帯債務者には求償権があることから、負担部分の割合が明らかな金額が債務控除の対象となります。
例】Aさんが主たる債務者として1,000万円を借り入れており、Bさんが連帯債務者になっているとしましょう。負担割合がAさん:Bさん=6:4であるとします。
仮にBさんが亡くなり相続が発生した場合、1,000万円の借り入れに対する負担割合が4割であることが契約書などで明らかになっているのであれば、400万円を限度に遺産総額から控除できます。
3.連帯債務者の一人に相続が発生した場合の抵当権の債務者変更登記
住宅ローンのような借入金をして不動産を取得すると、担保となる物件に抵当権が設定されます。連帯債務で借入をしており連帯債務者の1人が亡くなった場合、他の人が連帯債務を引き継いだのであれば抵当権の変更手続きが必要です。
連帯債務者が亡くなり債務者が1人になったとしても、残された債務者は連帯債務者として登記されます。連帯債務が1人の同じ人に帰属したとしても、もともと負っていた債務と相続によって引き継いだ債務は別個のものであり、お互いに影響しないと考えられているためです。
たとえば、夫Aさんと妻Bさんが連帯債務者となり住宅ローンを組んで自宅を建てていたとしましょう。主債務者はAさんとします。夫Aさんが亡くなったとき、相続人が妻Bさんのみであり夫Aさんの連帯債務を相続した場合、妻Bさんは債務者ではなく引き続き連帯債務者として登記されることになります。
4.連帯債務者の地位の相続についての判例の考え方
連帯債務者の地位は、法定相続分で当然のように分割されて相続人に承継されるというのが判例の考え方です。
たとえば、1,000万円の借入金の連帯債務を負っているAさんが死亡したとしましょう。相続人が妻Bさんと長女Cさんである場合、妻Bさんと長女Cさんは債務の2分の1である500万円ずつ負担することになります。
ここで、連帯債務の相続について実際の判例をご紹介します。
【実際の判例】
登場人物は、次の通りです。
- X:数回にわたってAさんにお金を貸している人
- Y:Xさんから債権者としての地位を承継した人
- A:Yさんから数回にわたって借金をしている人
- 子B:Aさんの子ども
- 嫁C:Bさんの配偶者
- 孫D1〜D4:子Bさんと嫁Cさんの子供、Aさんの孫
昭和26年、AさんがXさんから複数の借金をしていました。そこでAさんは、数回の借金をまとめるために新たな借用証書をXさんに交付。その際に、子Bさんや嫁Cさん、孫D1〜D4さんのすべてを連帯債務者としました。
しかし、孫D1〜D4さんは連帯債務者となった事実を知りません。そのため、実際に連帯債務を負っていたのは、Aさん、子Bさん、嫁Cさんの3人でした。
また、昭和27年には新たな借用証書が交付されて債務はさらに増えました。
しかし昭和28年にはAさんが亡くなり、翌29年には子Bさんも他界。その結果、子Bさんの地位は、嫁Cさんと孫D1〜D3までの計4人が相続しました。
その後も借金は返済されなかったため、Xさんから債権者の地位を引き継いだYさんは、嫁Cさんと孫D1さん〜D3さんのそれぞれに借金の支払いを求める裁判を起こしました。
このケースの場合、亡くなった子Bさんの債務のうち、3分の1は嫁Cさんが、残りの3分の2は孫D1さん、孫D2さん、孫D3さんの3人がそれぞれ6分の1ずつ相続したと考えられます。
嫁Cさんはもともとの連帯債務者である債務の全額を弁済する義務があるのに対し、孫D1さん〜孫D3さんの3人は、法定相続分である債務の6分の1ずつを弁済する義務が負っています。
そのため一審では、債務を負っている人で分担して弁済するよう、嫁Cさんは債務の3分の1、孫D1さん〜孫D3さんは債務の6分の1ずつの支払いを命じられました。その後、最高裁判所に上告されましたが、一審での判決が妥当であるとして棄却されています。
5.連帯債務を相続した場合の注意点
遺産分割協議により相続人同士が合意をすることで、法定相続分とは異なる割合で連帯債務を引き継げますが、それはあくまで内部の取り決めに過ぎません。連帯債務を相続した場合、債権者から法定相続分に応じた請求をされると支払いに応じる必要があります。
例】1,000万円の借り入れの連帯債務を長男Aさんと次男Bさんが引き継ぐとしましょう。
法定相続人はAさんとBさんの2人のみであるため、法定相続分に従って分けるのであれば500万円ずつ連帯債務を引き継ぐことになります。
遺産分割協議の結果、長男Aさんが700万円、次男Bさんが300万円を引き継ぐことになりました。しかし、Bさんはお金を貸している金融機関から支払を求められた場合は、300万円ではなく500万円を支払わなければなりません。
6.自分自身が連帯債務者である場合の事前対策
自分自身が連帯債務者である場合、相続人が相続放棄をするかどうかを判断できるように、債務の内容が明確に記載された書類を残しておきましょう。特に連帯債務の場合は、連帯債務者として負担している割合を示す情報を残すことが重要です。
亡くなった人が負担していた債務の割合を正しく把握できないと、相続人が債権者に弁済をしたとしても、他の連帯債務者に対して求償権を行使できないかもしれません。また、代わりに債務を弁済した他の連帯債務者から求償されたとき、相続人が応じて良いかどうかを判断できなくなる恐れもあります。
そのため、自分自身が連帯債務者である場合は、契約書をはじめとした債務や負担割合がわかる書類を残しておき、相続人となる人に保管場所を伝えておきましょう。
7.連帯債務を免れる方法はある?
連帯債務を相続するとき、相続人同士で話し合いをして法定相続分とは異なる割合を相続したとしても、債権者に主張することはできません。 そのため連帯債務を免れたいときは、相続放棄を検討する方法があります。
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利を一切放棄する手続きのことです。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとして扱われるため、連帯債務を含むすべての遺産を相続できなくなります。
ただし、現金や不動産などのプラスの財産も相続できなくなってしまうため、遺産がいくらあるのかをきちんと調査したうえで相続放棄をするかどうか判断することが大切です。
相続放棄をするためには相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。期限を過ぎると相続放棄ができなくなってしまうため、相続が発生したときは速やかに遺産の内容を調査しましょう。
相続放棄について詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
(参考)相続放棄とは?メリット・デメリットから手続き方法・期限など基礎知識を解説
8.連帯債務を相続した場合「免責的債務引受」をする方法
免責的債務引受とは、 債務者が債務を免れる代わりに引受人が新たな債務者となり、同一の債務を引き受けることをいいます。連帯債務を相続した場合、引受人に新たな債務者となってもらうことで債務が免除されます。
免責的債務引受をする場合、引受人となってくれる人を探さなければなりません。また、債権者の承諾も必要です。
そのため引受人となる人が十分な財産を持っていないと、債権者は免責的債務引受を承諾してくれないでしょう。
9.連帯債務が含まれている場合は専門の税理士に相談を
被相続人が連帯債務者となっている場合、相続人はその地位を引き継ぐことになります。新たに連帯債務者となった相続人は、債権者から弁済を求められる可能性があります。遺産総額から一定金額を控除できますが、被相続人の負担割合が明確でなければなりません。
遺産に連帯債務が含まれている場合は、引き継ぎ方を慎重に決めないと後でトラブルになる可能性があります。そのため、相続税に明るい税理士に相談のうえ慎重に手続きを進めていくことが重要です。
税理士法人チェスターには、相続税に精通した税理士が遺産分割協議や相続税の申告手続きなどをサポートいたします。連帯債務の相続でお困りの方は、ぜひ相続税専門の税理士法人であるチェスターにご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編






































