相続税の控除・特例とは【一覧表付】要件・控除額を税理士が解説
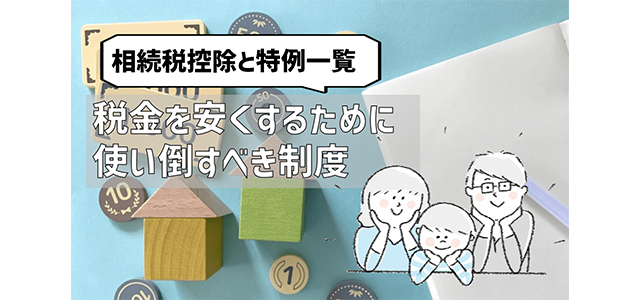
相続税の計算においては、税負担を軽減するための控除や特例が設けられています。
すべての相続で適用できる「基礎控除」の他にも、配偶者の税負担を大幅に軽減する「配偶者控除」や、相続した土地の評価額を下げられる「小規模宅地等の特例」など、さまざまな種類があります。
これらの控除・特例が適用できれば、相続税額がゼロ円になる可能性もあります。
控除や特例を適用するためには、要件を満たし、必要に応じて相続税の申告を行う必要があります。相続が発生したときは、自身が適用できる控除や特例を正しく把握し、相続税を適切に申告することが大切です。
この記事では、相続税の控除や特例について、種類ごとの適用要件や計算方法、申告手続きの流れを、相続税専門の税理士が解説します。
この記事の目次 [表示]
1.相続税はいくらからかかる?まずは基礎控除を理解しよう
相続税がかかるのは、亡くなった人(被相続人)が残した財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合です。そのため、すべての相続で税金がかかるわけではありません。
相続が発生した際は、遺産を漏れなく調査して金銭的な価値(評価額)を適切に求め、その合計額が基礎控除額を超えるかどうかを確認する必要があります。
ここでは、基礎控除の計算方法や計算時の注意点について詳しく解説します。
1-1.すべての相続で適用される「基礎控除」の計算方法
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。法定相続人は、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ人のことです。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外は以下の優先順位にしたがって決まります。
- 第1順位:亡くなった人の子供(子供がすでに亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
- 第2順位:亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子供である甥・姪)
出典:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
先の順位に該当する人物が1人でもいる場合、後の順位に該当する人は法定相続人になれません。
法定相続人の数が多くなるほど、基礎控除額も大きくなり相続税がかかりにくくなっていきます。法定相続人の数に応じた基礎控除額は、以下の早見表でご確認ください。

相続税の基礎控除額について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説
1-2.遺産総額が基礎控除以下なら相続税の申告は不要
遺産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税は課せられず、税務署への申告も必要ありません。
遺産の総額は、各相続人が取得した遺産の課税価格を合計したものです。相続人ごとに以下の計算式で課税価格を求め、それらを合計します。
※令和9年(2027年)以降の相続では7年以内まで段階的に延長
非課税財産に該当するものは、以下のとおりです。
- 墓所、仏壇、祭具など
- 亡くなった後に国や地方公共団体などに寄付した財産
- 生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」で求められる金額まで
- 死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」で求められる金額まで など
たとえば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となるため、遺産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかからず、申告も不要です。
1-3.法定相続人の数え方で注意すべき3つのポイント
基礎控除額を正しく算出するためには、法定相続人の数を正確に把握することが重要です。特に、間違いやすい以下の3つの点に注意しましょう。
- 相続放棄した人も含める
- 養子の数には税法上の上限がある
- 代襲相続人の人数はそのまま数える
1-3-1.ポイント1:相続放棄した人も含める
相続人の中に財産を受け取る一切の権利を放棄する「相続放棄」をした人がいても、基礎控除額を計算するときは、その放棄した人も法定相続人の数に含めます。
民法上、相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされますが、相続税の計算では放棄がなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をした人がいても基礎控除額が減ることはありません。
1-3-2.ポイント2:養子の数には税法上の上限がある
養子は法律上、実子と同じく第1順位の法定相続人として相続権を持ちますが、基礎控除額の計算に含められる人数には以下のような制限があります。

このような制限が設けられているのは、相続税の節税のみを目的として養子縁組を行い相続税の軽減を図ることがないようにするためです。
上限を超える養子も遺産を相続することはできますが、基礎控除を計算する際の人数には含まれません。
1-3-3.ポイント3:代襲相続(だいしゅうそうぞく)は代わりの相続人の人数をそのまま数える
本来の相続人が被相続人より先に亡くなっているときは、その人の子供(被相続人から見た孫、甥、姪など)が代わりに相続人となることを「代襲相続」といいます。
代襲相続が発生した場合、代わりとなって相続する人(代襲相続人)の数をそのまま法定相続人の数として数えます。
たとえば、本来の法定相続人が配偶者、長男、長女であるとしましょう。相続の開始時点で長男はすでに他界していた場合、その人の2人の子供が代襲相続人となります。
この場合、基礎控除額を計算する際の法定相続人は配偶者、長女、孫2人の計4人となります。
ただし、代襲相続人である孫が被相続人と養子縁組をしており、実子としても相続権を持つ「二重相続資格者」である場合、その孫は基礎控除額の計算においては1人とカウントします。
2.【一覧表】相続税の負担を軽くする控除・特例制度
相続税の負担を軽減できる制度には、相続財産の評価額を下げる特例と、算出された相続税の額から一定金額を直接差し引く税額控除があります。
相続税の代表的な特例と税額控除は以下のとおりです。
| 制度名 | 種類 | 概要 |
|---|---|---|
| 小規模宅地等の特例 | 評価額を下げる特例 | 自宅や事業用の土地の評価額を最大80%減額する特例 |
| 配偶者の税額軽減 | 税額控除 | 配偶者が相続した財産のうち「1億6,000万円」または「法定相続分」まで非課税となる特例 |
| 未成年者控除 | 税額控除 | 18歳未満の相続人がいる場合に、成人までの年数に応じた額を控除 |
| 障害者控除 | 税額控除 | 85歳未満で障害を持つ相続人がいる場合に、85歳までの年数に応じた額を控除 |
| 相次相続控除 | 税額控除 | 10年以内に相続が続けて発生した場合、前回の相続税の一部を今回の税額から控除 |
| 贈与税額控除 | 税額控除 | 相続財産に加算された生前贈与財産に課税された納税済みの贈与税額を相続税額から控除 |
| 外国税額控除 | 税額控除 | 海外の財産について外国で相続税を支払った場合に、その税額を日本の相続税額から控除 |
次章から、それぞれの詳細について解説します。
3.相続税の負担を大幅に減額できる控除・特例
遺産を相続したときは、以下の控除・特例を適用すると、相続税額を大幅に抑える効果が期待できます。
上記の制度を適用するためには、相続税の申告手続きが必須です。適用したことで相続税額が0円になる場合でも、必ず相続税の申告書を提出しなければなりません。
3-1.配偶者の税額軽減(配偶者控除)|1億6千万円まで非課税
配偶者の税額軽減は、亡くなった人の配偶者が相続や遺贈で財産を取得する場合に、相続税の負担を大幅に軽減できる制度です。具体的には、配偶者が取得した正味の遺産総額が以下のうちいずれか多い金額まで相続税がかからなくなります。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
たとえば、法定相続人が配偶者と長女の2人、遺産総額が6億円であるとしましょう。この場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。
配偶者の税額軽減を適用すると、配偶者が相続した遺産の総額が法定相続分に相当する3億円を超えない限り相続税はかかりません。
配偶者の相続税が優遇されるのは、基本的に財産は夫婦が協力して築き上げられるものであると考えられるためです。また、残された配偶者が死亡した場合には、同一世代に2回課税されるため、税負担が過大にならないよう配慮されています。
ただし、配偶者の税額軽減を利用できるのは、相続人が亡くなった人と法律上の婚姻関係にある配偶者である場合です。法律上の婚姻関係にない内縁関係(事実婚)にある人は配偶者の税額軽減を適用できません。
配偶者の税額軽減について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説
3-2.小規模宅地等の特例|自宅や事業用の土地評価額を最大80%減
小規模宅地等の特例は、対象の宅地等を相続したときに相続税評価額を最大で80%減額できる制度です。
特例の対象となる宅地は、用途(使われ方)によって以下のように分けられ、それぞれに減額割合や適用できる面積の上限が定められています。
| 相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 被相続人等が住むための家が建っていた土地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 被相続人等が事業を営むために使われていた土地※1 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 一定の法人の事業を営むために使われていた土地※1 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などの賃貸事業を営むための土地 | 200㎡ | 50% |
※1.不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などを除く
たとえば、特例を適用する前の相続税評価額が5,000万円、面積200㎡の自宅の土地(特定居住用宅地等)を配偶者が相続するとしましょう。
相続した土地の面積は、特定居住用宅地等の限度面積330㎡以下であり、評価額のすべてに特例を適用できるため、減少額と特例適用後の評価額は以下のとおりとなります。
- 減少額:5,000万円×80%=4,000万円
- 特例適用後の相続税評価額:5,000万円−4,000万円=1,000万円
小規模宅地等の特例を適用するためには、一定の要件を満たさなければなりません。
たとえば、別居の親族が被相続人の宅地を相続する場合「被相続人に配偶者がいない」「相続人が相続開始前3年以内に自己所有の家に住んだことがない」などの要件を満たす必要があります。
小規模宅地等の特例について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説
4.要件を満たせば使える!5つの税額控除
相続税の税額控除には、配偶者の税額軽減の他にも種類があります。代表的な税額控除は以下のとおりです。
ここでは、代表的な5つの税額控除について、それぞれの内容と計算方法を解説します。
4-1.未成年者控除|18歳未満の相続人がいる場合
未成年者控除は、未成年者の相続人が負担する相続税の額から一定額を控除できる制度です。
令和4年(2022年)4月1日以降に相続が発生した場合、控除額は以下の計算式で算出します。
※令和4年(2022年)3月31日以前に相続が発生した場合は20歳

控除額を計算する際の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。たとえば、相続開始時点で相続人の年齢が15歳6ヶ月であれば、15歳として計算するため、控除額は「(18歳-15歳)×10万円=30万円」です。
未成年者に生じる相続税が控除額よりも少ない場合、控除しきれなかった部分は扶養義務者である親などの相続税から差し引かれます。
(注)扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の人をいいます(障害者控除における扶養義務者も同様です)。
未成年者控除については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説
4-2.障害者控除|85歳未満の障害を持つ相続人がいる場合
障害者控除は、障害を持っている85歳未満の法定相続人がいる場合、その人にかかる相続税額から一定額を控除できる制度です。
控除額は障害の程度によって異なり、相続が発生した時点での年齢に応じて計算します。
- 一般障害者の控除額=(85歳−相続開始時の満年齢)×10万円
- 特別障害者の控除額=(85歳−相続開始時の満年齢)×20万円

特別障害者とは、一般障害者よりも重度の障害を持つ人のことです。特別障害者のほうが、一般障害者よりも控除額が大きくなります。
相続開始時の満年齢は、1歳未満を切り捨てます。たとえば、障害者である相続人の年齢が62歳8ヶ月の場合、控除額を計算する際は62歳とします。
相続人が一般障害者に該当する場合、相続税から考慮される金額は「(85歳-62歳)×10万円=230万円」です。
未成年者控除と同様に、障害者本人の相続税額が控除額を下回っている場合、残額は扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
障害者控除の要件や控除額の計算方法など詳しくは、以下の記事でご確認ください。
(参考)相続税の障害者控除はいくら減額?要件・計算方法・2回目の注意点も解説
4-3.相次相続控除|10年以内に続けて相続が発生した場合
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)は、最初の相続(一次相続)から10年以内に次の相続(二次相続)が発生した場合に適用できる税額控除です。
要件を満たすと、一次相続で課された相続税額のうち一定の金額を、二次相続の相続税から控除できます。控除額は、一次相続から経過した年数1年につき10%ずつ減少していきます。
相次相続控除を受けるためには、二次相続の被相続人が一次相続の際に相続税を納めている必要があります。
二次相続の相続人が一次相続で財産を取得しても、その際に相続税を納めていないのであれば、相次相続控除は適用できません。
また、相続放棄をした人や相続廃除または相続欠格によって相続権を失った人も対象外です。
相次相続控除について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説
4-4.贈与税額控除|相続開始前7年以内の贈与が対象
贈与税額控除は、相続税と贈与税の二重課税を防ぐための制度です。
令和6年(2024年)1月1日以降に生じる相続については、相続開始前の3~7年以内に被相続人から相続人が受けた贈与財産の価額は、相続財産の価額に足し戻して相続税を計算します。この制度を「生前贈与加算」といいます。
生前贈与加算により、足し戻された贈与財産の価額に対して、すでに納めている贈与税がある場合、その税額を相続税額から差し引くことが可能です。


生前贈与加算の対象になる期間は、これまで相続開始前の3年間でしたが、令和9年(2027年)から段階的に延長され、令和13年以降は7年となります。
贈与税額控除について詳しくは、以下の記事もご覧ください。
(参考)暦年課税に係る贈与税額控除の控除不足額は還付なし~令和5年度税制改正で見直しもされず~
4-5.外国税額控除|海外資産に二重で課税されるのを防ぐ
外国税額控除は、海外にある財産を相続した場合に二重課税を防ぐための制度です。
相続や遺贈で財産を取得した人が「無制限納税義務者」に該当する場合、国内にある相続財産だけでなく国外の相続財産も相続税の課税対象となります。無制限納税義務者に該当する人は、以下をご確認ください。

外国に財産を保有している人が亡くなった場合、その国で相続税に対応する税金を支払わなければならない場合があります。
外国と日本の双方で相続税が二重に課税されて税負担が過大になってしまうかもしれません。
このような場合、「外国税額控除」を適用すると外国で納めた税額分を日本の相続税から控除できるケースがあります。
外国税額控除の対象になる人や手続き方法などは、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
(参考)相続税の外国税額控除とは?二重課税を防ぐ手続き・計算方法を解説
5.控除・特例を適用する場合の税額や控除額を計算シミュレーション
相続税は、各相続人が取得した遺産の総額に税率をかけるのではなく、以下の手順で算出します。
ここでは、モデルケースを用いて、税額控除や特例を適用する場合の相続税の計算手順を解説します。モデルケースは以下のとおりです。
- 被相続人:68歳で死亡
- 相続人:妻Aさん(65歳)、長男Bさん(40歳、特別障害者)、長女Cさん(16歳、未成年者)の3名
- プラスの財産
- 自宅:1億円(土地8,000万円、建物:2,000万円)
- 預貯金:1億円
- 生命保険金:3,000万円(受取人は妻Aさん)
- マイナスの財産
- 借入金:1,000万円
- 葬式費用:200万円
被相続人は遺言書を残しておらず、相続人間で遺産分割協議をした結果、以下のとおりに相続することになりました。
- 妻Aさん
- 自宅1億円、預貯金4,000万円、生命保険金3,000万円
- 借入金1,000万円
- 長男Bさん:預貯金3,000万円
- 長女Cさん:預貯金3,000万円
以上の条件で相続税を計算します。
5-1.STEP1:課税遺産総額を計算する
はじめに、相続税の計算対象となる遺産の金額(課税遺産総額)を求めます。
【例】相続税の課税対象となる財産の価額を確定させ、そこから基礎控除を引いて「課税遺産総額」を算出します。
まず、プラスの財産からマイナスの財産と葬式費用を差し引きます。計算の際は、財産の評価額を下げる特例や非課税枠を適用します。
妻Aさんが相続する被相続人の自宅の土地(評価額8,000万円・面積200㎡)が特定居住用宅地等として「小規模宅地等の特例」の対象になる場合、適用後の評価額は以下のとおりです。
- 土地の相続税評価額:8,000万円−(8,000万円×80%)=1,600万円
土地の面積は200㎡であり、特定居住用宅地等として特例を適用できる限度面積330㎡の範囲内であるため、評価額のすべてが80%減額されます。
また、生命保険金に非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用すると、課税対象になる金額は以下のとおりとなります。
- 生命保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
- 非課税枠を適用したあとの課税対象額:3,000万円−1,500万円=1,500万円
次に、各相続人が取得した財産の課税価格を合計します。
| 妻Aさん | 長男Bさん | 長女Cさん | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 遺産 | 7,600万円 (土地1,600万円、建物2,000万円、預貯金4,000万円) | 預貯金3,000万円 | 預貯金3,000万円 | 1億3,600万円 |
| 生命保険金 | 1,500万円 (3,000万円−1,500万円) | – | – | 1,500万円 |
| 債務控除 | 借入金1,000万円 | – | – | 1,000万円 |
| 葬式費用 | 200万円 | – | – | 200万円 |
| 課税価格 | 7,900万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1億3,900万円 |
計算の結果、課税価格の合計額(正味の遺産額)は、1億3,900万円となりました。
最後に、課税価格の合計額から相続の基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。このケースでは、法定相続人は3人のため、結果は以下のとおりです。
- 基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
- 課税遺産総額:1億3,900万円−4,800万円=9,100万円
よって、当該ケースの課税遺産総額は9,100万円です。
5-2.STEP2:相続税の総額を計算する
次に、相続人全員で負担する「相続税の総額」を算出します。
【例】各相続人が法律で定められた相続分(法定相続分)で遺産を取得したと仮定して、相続税の総額を計算します。
STEP1で算出した課税遺産総額9,100万円を法定相続分(妻1/2、子供1/4ずつ)で分けます。
- 妻Aさん:9,100万円×1/2=4,550万円
- 長男Bさん:9,100万円×1/4=2,275万円
- 長女Cさん:9,100万円×1/4=2,275万円
続いて、各相続人の法定相続分に応じた取得金額に、以下の相続税率をかけ控除額を控除して仮の相続税額を求めて合計します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」
計算結果は、以下のとおりです。
- 妻Aさんの税額:4,550万円×20%−200万円=710万円
- 長男Bさんの税額:2,275万円×15%−50万円=291.25万円
- 長女Cさんの税額:2,275万円×15%−50万円=291.25万円
- 相続税の総額:710万円+291.25万円+291.25万円=1,292.5万円
相続税の総額は1,292.5万円と算出されました。
5-3.STEP3:各相続人の相続税額を計算する
相続税の総額が算出できたら、実際に取得する財産をもとに各相続人の相続税額を計算します。
【例】STEP2で算出した相続税の総額(1,292.5万円)を、実際の財産の取得割合に応じて各相続人に割り振ります。
まず、各相続人が実際に取得した財産の価額(債務なども考慮したもの)を計算します。
- 妻Aさん:(土地1,600万円+建物2,000万円+預貯金4,000万円+生命保険金1,500万円)−(借入金1,000万円+葬式費用200万円)=7,900万円
- 長男Bさん:預貯金3,000万円
- 長女Cさん:預貯金3,000万円
取得した財産の合計額「7,900万円+3,000万円+3,000万円=1億3,900万円」です。この合計額に対する各人の取得割合をもとに、相続税の総額を割り振ります。
- 妻Aさんの負担額:1,292.5万円×(7,900万円/1億3,900万円)=734万5,800円
- 長男Bさんの負担額:1,292.5万円×(3,000万円/1億3,900万円)=278万9,500円
- 長女Cさんの負担額:1,292.5万円×(3,000万円/1億3,900万円)=278万9,500円
※計算結果は100円未満切り捨て
上記が、税額控除を適用する前の各相続人の相続税額となります。
5-4.STEP4:税額控除を適用する
最後に、税額控除を適用して各相続人の納税額をもとめます。
【例】STEP3で算出した各相続人の税額から税額控除を差し引いて納税額を算出します。
妻Aさんの納税額
妻Aさんには「配偶者の税額軽減」を適用します。妻Aさんの取得財産は計7,900万円であり、1億6,000万円の非課税枠を下回るため、納付税額は0円となります。
長男Bさんの納税額
長男Bさんは特別障害者であるため「障害者控除」を適用します。控除額は、85歳までの年数1年につき20万円のため「(85歳−40歳)×20万円=900万円」です。
長男Bさんの相続税額は278万9,500円であるため、全額が控除されて納税額は0円となります。また、税額から引ききれなかった部分「900万円−278万9,500円=621万500円」は、扶養義務者の相続税額から差し引きます。
長女Cさんの納税額
長女Cさんは未成年のため「未成年者控除」を適用します。控除額は「(18歳−16歳)×10万円=20万円」であるため、これを差し引いたあとの税額は「278万9,500円−20万円=258万9,500円」です。
また、長男Bさんが使いきれなかった障害者控除の残額621万500円を、扶養義務者である長女Cさんの税額から差し引けるため、最終的な納税額は0円となります。
| 相続税額 (按分後) | 適用できる税額控除 | 納税額 | |
|---|---|---|---|
| 妻Aさん | 734万5,800円 | 配偶者の税額軽減 | 0円 |
| 長男Bさん (特別障害者) | 278万9,500円 | 障害者控除 | 0円 |
| 長女Cさん (未成年) | 278万9,500円 | 未成年者控除 + 長男Bさんの障害者控除の残額 | 0円 |
シミュレーションの結果、配偶者の税額軽減や税額控除を適用することで、各相続人の納税額は0円となりました。
6.相続税の控除・特例でよくある質問
最後に、相続税の税額控除や特例に関するよくある質問に回答します。
6-1.基礎控除や税額控除や特例は併用できますか?
相続税の基礎控除や小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除などは、要件を満たせば同時に適用することができます。
ただし、制度によって適用するタイミングが異なる点には注意が必要です。
- 基礎控除:相続税が課税される遺産の総額(課税遺産総額)を求めるとき
- 小規模宅地等の特例:土地の相続税評価額を求めるとき
- 配偶者の税額軽減・未成年者控除などの税額控除:各人の相続税額から納付税額を求めるとき
6-2.税額控除や特例を使って相続税が0円になる場合でも申告は必要ですか?
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を利用して相続税が0円になった場合でも、相続税の申告は必要です。申告をしないと控除や特例が適用されず税負担が重くなるばかりか、無申告加算税や延滞税の対象となる可能性があります。
| 税額控除の種類 | 申告の可否 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 税額がゼロでも申告が必要 |
| 相次相続控除 | |
| 外国税額控除 | |
| 未成年者控除 | 税額がゼロなら申告は不要 |
| 障害者控除 |
一方で、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内に収まる場合は、そもそも相続税の申告義務がありません。
また、未成年者控除や障害者控除、相次相続控除を適用した結果、納める税額が0円になった場合も申告は不要です。
6-3.配偶者の税額軽減を使うときの注意点はありますか?
配偶者の税額軽減を利用する際には、主に以下の2点に注意が必要です。
- 二次相続で税負担が増加する可能性がある
- 法律上の配偶者であることが条件である
夫婦のどちらかが亡くなって一次相続が発生した場合、配偶者が多くの遺産を取得しても、配偶者の税額軽減を適用すれば、税負担は軽減されます。
しかし、その配偶者が亡くなり二次相続が発生した際に子供が遺産を相続する場合、配偶者の税額軽減を適用できません。また、法定相続人が1人少なくなることで相続税の基礎控除額が減る場合もあります。
配偶者の税額軽減を適用できるからといって、一次相続で遺産のほとんどを配偶者が相続すると、二次相続も含めたトータルの税負担が重くなる可能性があります。そのため、一次相続の時点で子供にも一定の財産を相続させておくことも検討することが大切です。
また、配偶者の税額軽減を受けられるのは、被相続人の法律上の配偶者に限定されます。長年連れ添っていても、婚姻届を提出していない内縁関係の夫・妻や事実婚にあるパートナーは適用できません。
7.相続税の控除を正しく理解して、損のない申告を
相続税の負担を軽減できる控除・特例には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、未成年者控除、障害者控除などがあります。控除・特例を適切に活用することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
ただし、これらの控除・特例は要件を満たしているとしても自動的に適用されるわけではないため、基本的に申告が必要です。要件の確認や申告手続きには、専門的な知識がなければ理解が難しい部分があるため、相続が発生したときは相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
チェスターは、年間3,000件もの相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。
豊富なノウハウで、最大の節税を意識した各種控除や特例の適用や、遺産分割の方法をご提案いたします。
すでに相続が発生されたお客様は初回面談が無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は84名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編






































