相続の流れがわからないときに必見。必要な手続きや期限を確認
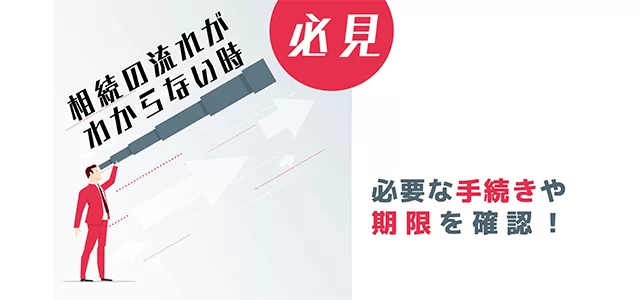
身近な人や家族が亡くなると、財産の相続が発生します。相続人の調査や遺産分割協議など、やるべきことは多岐にわたり、何から手を付ければいいかわからないという状態になることも少なくありません。必要な手続きの流れや期限を確認しましょう。
この記事の目次 [表示]
1.相続とは
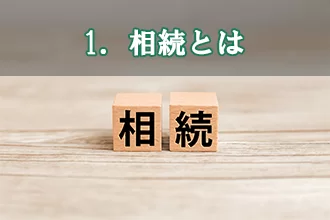
『相続』という言葉の意味はなんとなく理解していても、実際に相続が発生すると『相続では何をするのか』『誰が対象になるのか』と迷ってしまうでしょう。相続の定義や突然の相続に備えるための準備について紹介します。
1-1.故人の財産を引き継ぐこと
『相続』とは、故人の財産をその配偶者や子どもなどが引き継ぐことです。ある人の死亡によって、財産上の権利義務が特定の人に承継されるともいえるでしょう。
ここでいう『死亡』は、自然死だけでなく、不在者の生死が7年間わからない『普通失踪』や、危難に遭遇した後の生死がわからない『危難失踪』も含みます。
「普通失踪」と「危難失踪」については以下の記事も参考にしてください。
失踪宣告の申立方法と流れを解説!相続や婚姻関係はどうなる?
財産を残した故人は『被相続人』、財産を引き継ぐ者は『相続人』と呼ばれます。
1-2.口座凍結に備えた事前準備を
銀行口座の名義人が他界すると、銀行は口座凍結を行います。原則として、相続人が必要書類を準備して解約手続きを行わない限り、払い戻しはできません。
銀行が口座を凍結する理由は『相続財産を守るため』です。凍結をしない場合、一部の相続人や利害関係者が勝手に預貯金を引き出し、遺産の権利が侵害される恐れがあります。
銀行が口座を凍結するタイミングは『相続人が口座凍結手続きを行った場合』や『名義人の死亡を確認できた場合』です。
仮に自分が故人と同居していて、当該口座を家賃や公共料金の支払い口座に設定していた場合は、口座凍結に備えて『支払い先の変更』を早めに済ませておきましょう。自分が口座凍結の手続きを行うのであれば、各変更手続きが完了した後が最適です。
万が一、口座凍結してしまった場合の手続きなどについては以下で解説しています。
口座の凍結解除にかかる費用や手続|ケースごとの必要書類もチェック
2.相続は調査から始まる

相続において最も重要な過程の一つが『相続人の調査』です。遺産相続では、他の相続人と遺産分割協議を行い、財産を分け合う必要があります。相続人が1人でも協議から欠けるとその相続は無効となるため、調査は徹底的に行わなければなりません。
2-1.相続人を確定させる
日本には、被相続人の財産を相続人に承継するためのルールを定めた『相続制度』があり、制度に従って相続を行うのが一般的です。民法によって『相続の権利がある』と認められている人々は『法定相続人』と呼ばれます。
遺産分割の際は、法定相続人を金融機関や法務局に証明しなければ、手続きが進められません。養子縁組を行った場合や前妻・前夫がいる場合、自分たち家族のほかにも、遺産を相続する権利を持つ人が存在する可能性があります。
相続人全員が参加しない遺産分割協議は無効のため、『誰が相続をするのか』を調査して確定しなければならないのです。
調査では、戸籍謄本を取得し相関図を作成します。転籍や離婚歴がある場合、調査に時間がかかるため、弁護士や司法書士に依頼する手もあります。
相関図の作成については以下の記事も参考にしてください。
【テンプレート付】相続関係説明図とは?目的や書き方、記載例を紹介
2-2.遺言書を探し検認
相続手続きの前に、遺言書を探す必要があります。遺言書には時効がなく、遺産相続の後に遺言書が見つかった場合でも内容は有効とされます。遺言の内容が実際の相続と異なる場合、遺産の再分配を行うのが原則のため、遺言書探しを省くことはできません。
遺言書には、遺言者が全文を自筆で書く『自筆証書遺言』と、公証役場の公証人に作成してもらう『公正証書遺言』があります。
自筆証書遺言は、自宅等で保管されているほか、弁護士や司法書士が預かっているケースもあります。また、法務局で保管されている場合は、最寄りの法務局で検索することが可能です。公正証書遺言は、公証役場の『遺言検索システム』を使って検索することが可能です。
遺言検索システムの使い方などについては以下記事もご覧ください。
遺言検索システムとは?使い方・遺言書の見つけ方・利用方法や必要書類を解説
法務局以外の場所で保管されていた自筆証書遺言は、相続手続きの前に検認を受ける必要があります。『検認』とは、遺言書の偽造・変造を防ぐための手続きで、『遺言書の保管者』または『遺言書を発見した相続人』が家庭裁判所に申し立てを行うことで完了します。
3.故人の全ての財産を調べる

相続人が確定したら、故人の全ての財産を調査します。相続財産は必ずしも『プラスの財産』とは限りません。借入金や住宅ローン、税金などの『マイナスの財産』も含まれる点に注意しましょう。
3-1.預金、株式、不動産などプラスの財産
プラスの財産とは、預金・株式・不動産・有価証券・小切手・車・貴金属・借地権などを指します。
財産の調査は、故人の預金通帳や郵便物をチェックするのが基本です。株式があれば預金口座に配当金の受領記録が、土地や物件を持っていれば固定資産税の引き落とし記録が残っている可能性があります。
銀行や証券会社からの郵便物が届いていれば、各所に電話して相続財産を調べてもらいましょう。
不動産を所有している場合、固定資産税の納付書が届くのが通常です。ただし納付すべき税額が発生しない場合や、共有者がいる場合はその限りではありません。市町村の役場で被相続人名義の『固定資産評価証明書』を取得し、詳細を調べる必要があります。
3-1-1.不動産の価値の決まり方
不動産を相続したら、『相続税』が発生する場合があります。相続税は不動産の価値によって決まるため、基準となる課税価格(相続税評価額)を確認しておきましょう。
相続税評価額は、『路線価方式』と『倍率方式』の二つの方法で算出できます。
- 路線価方式:路線価×土地面積
- 倍率方式:固定資産税評価額×一定の倍率
路線価方式は、国税庁のHPにある『路線価図』から、相続する土地の路線価(路線に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額)を調べ、土地の面積を掛けて算出する方法です。
倍率方式は、路線価がない場合に使う方式で、固定資産税評価額に国税庁が場所ごとに定める評価倍率を掛けて算出します。
路線価方式と倍率方式については以下の記事も参考にしてください。
路線価方式と倍率方式
3-2.借金などマイナスの財産
相続人は、被相続人の負債や借金などのマイナスの財産も相続します。銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借金については、以下の『信用情報機関』に問い合わせ、『信用情報の開示』を請求します。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にカード会社の借入
- 株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融からの借入
- 一般社団法人全国銀行協会:主に銀行・金融機関からの借入
マイナスの財産が多い場合、相続人の負担は大きなものになるでしょう。相続人には、以下の三つから相続方法を選択する権利が与えられています。
- 単純承認:全ての相続財産を引き継ぐ
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続する
- 相続放棄:相続を放棄する
限定承認を選んだ場合、相続人は『財産を超える分の借金』に対しては返済義務を負いません。
限定承認と相続放棄を選択する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。
3-3.時価を記載した財産目録を作成
全ての財産を洗い出した後は『財産目録』を作成します。財産目録とは、故人が保有する財産を種類別に記録し、財産の状況を明らかにしたものです。
決まった様式はありませんが、全財産をプラスの財産とマイナスの財産に区別した上で、財産の名称・所在・数量・金額(時価)を記載しましょう。金額は『いつの時点で』『何を基準としたのか』を明確にしておくのがポイントです。
相続税の申告では、被相続人死亡時の遺産の評価額が基準となります。評価時期や基準が統一されていないと、正確な申告ができなくなる恐れがあるでしょう。
4.事業などにより故人に所得があった場合
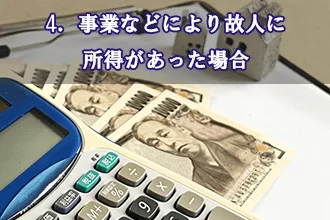
給与金額が2,000万円を超える人や事業所得がある人などは、確定申告を行うのが通常です。被相続人が確定申告を行わずに亡くなった場合、誰がどのような手続きを行えばよいのでしょうか?
4-1.相続人全員で準確定申告
故人に確定申告の必要があった場合は、故人に代わり相続人全員で『準確定申告』を行います。
通常の確定申告は、納税システム『e-Tax』を使ったオンライン申告が可能です。準確定申告でも『e-Tax』を使用できるようになりましたが、令和元年分以前については管轄する税務署に足を運ばなければなりません。
相続人が複数いれば、各相続人の連署で準確定申告書を提出します。各人が別々に提出したい場合は、ほかの相続人に申告内容を通知するのが原則です。
故人に確定申告の必要性がない場合は、準確定申告も不要です。ただし以下のケースでは、準確定申告によって還付金が得られる可能性があります。
- 被相続人が高額な医療費を払っていた場合
- 給与所得者で源泉徴収税額を徴収されている場合(年末調整前)
- 配偶者控除や生命保険料控除などの各種控除を受ける場合
4-2.期限は4カ月以内
準確定申告には期限が設けられています。通常の確定申告期間は2月16日~3月15日ですが、準確定申告は『相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内』です。
例えば、相続の開始を知った日が2月28日であった場合、相続人は3月1日から4カ月以内に前年分・本年分の準確定申告をしなければなりません(うるう年でない場合)。申告が遅れた場合、無申告加算税が加算されます。
ほかに『延滞税』も加算されるため、期限内に申告を済ませるようにしましょう。
5.遺言書がない場合などは遺産分割協議
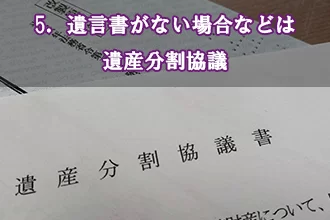
相続人が複数いる場合や遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い、遺産の配分を決定します。遺産分割協議を行った後、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印をする流れです。
5-1.遺産分割協議のやり方
調査によって相続人が確定したら、財産目録を作成した上で『遺産分割協議』を行います。相続人の中から『まとめ役』を選び、まとめ役を中心に話し合いを進めましょう。
協議は相続人全員が一堂に会する必要はありません。日程が合わない、遠方で来られないといった場合には、電話やメール、手紙による協議も可能です。
ただし、最終的には相続人全員が遺産分割協議の内容に同意しなければならないため、できるだけ会って話し合った方がよいでしょう。遺産分割は大きく4種類に分けられます。
- 現物分割:現物で分割する
- 代償分割:特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人には相当する金銭を支払う
- 換価分割:売却してその代金を分割する
- 共有分割:複数の相続人の共有名義で相続する
5-2.遺産分割協議書の作成
どの遺産を誰が相続するかを決めた後は、合意内容をまとめた『遺産分割協議書』を作成します。最後に相続人全員が署名し、『実印』を押印するのが基本です。
遺産分割協議書の目的は、相続財産の帰属を明確にし、後々の紛争やトラブルを防ぐことです。相続税の申告時は遺産分割協議書の添付を求められるケースがあるほか、銀行口座の解約や名義変更の際にも必要です。
遺産分割協議書の作成方法で迷うことがあれば、弁護士や司法書士、行政書士に相談しましょう。専門家に作成を依頼する際は、相続人の間で費用をどう負担するかを話し合います。
下記記事では遺産分割協議書の依頼先をフローチャートで診断できます。
遺産分割協議書を作成できる人は?専門家に頼むメリット、デメリットを解説
6.分け方が決まったら名義変更
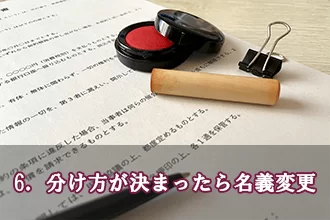
遺産分割協議で分配が決定した後は、遺産の名義変更を行いましょう。名義の変更が必要なのは、『預貯金』や『株式』です。実家の建物や土地を引き継ぐ場合は『所有権移転登記』の手続きを行います。
6-1.預貯金、株式の名義変更
遺産分割協議の終了後、相続人は銀行の窓口に足を運び、口座の名義変更や解約の手続きを行いましょう。
必要書類は『遺言書がある場合』『遺産分割協議書がある場合』『遺産分割協議書がない場合』で異なります。詳細は各金融機関に確認しましょう。
株式の名義変更は、『証券会社』または『株式会社(株式を発行している企業)』で手続きを行います。遺産分割協議を行った際は、相続人全員の印鑑証明書や遺産分割協議書を忘れずに準備しましょう。
名義変更は『上場株』と『非上場株』で必要書類や手続き方法が異なります。
6-2.不動産は「相続登記」
家や土地などの不動産は、所有権を移転するための『相続登記(相続による所有権移転の登記)』を行います。手続き後、不動産の名義が被相続人から相続人へと変更されます。
これまでは、相続人に名義を変更する義務はなく、相続登記をいつ行うかは相続人の自由でした。しかし2024年4月に相続登記が義務化されることになり、正当な理由なく登記を怠った場合にペナルティが課せられます。
相続登記の義務化については下記で詳しく解説しています。
相続登記の義務化はいつから?違反者への罰則/新制度に備える方法も解説
相続登記は不動産の特定や登記簿謄本の取得、戸籍・戸籍附票収集など、複数のステップを踏まなければならないため、時間や手間を省きたい人は司法書士などの専門家に依頼しましょう。
7.相続税申告と納税
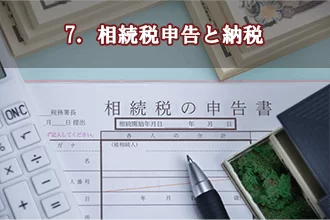
被相続人から財産を相続すると、取得した財産に対し『相続税』が課されます。税金を支払うのは、その財産を相続した『相続人』で、税額は財産の価額から基礎控除額を控除して算出します。
7-1.基礎控除額を超えた場合は相続税が発生する
相続税は、財産の価値が大きいほど高い税率が課せられる『累進税率』です。相続財産の合計額が以下の『基礎控除額』を超える場合、その財産を相続した人は相続税を納めなければなりません。
- 基礎控除額=3,000万円+( 600万円 × 法定相続人の数 )
国税庁のHPにある『相続税の申告要否判定コーナー』では、相続人の数や財産の金額を入力すると、相続税の申告が必要か否かわかります。
国税庁が公開する『令和4年分 相続税の申告事績の概要』によると、相続税が必要な人(課税割合)は9.6%です。相続税の納税対象となる人は少ないといえるでしょう。
相続税の申告が必要な場合は、相続や税金のプロである『税理士』に相談することをおすすめします。
7-2.期限は10カ月以内
相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内に行います。1月25日に死亡を知った場合は、10カ月後の11月25日までに申告を済ませなければなりません。
納税期限が土日・祝日にあたる場合は、その翌日が期限です。納税期限を過ぎると、相続税のほかに『加算税』や『延滞税』が加算される場合があります。
相続税の申告書作成では、膨大な資料を用意しなければならないため、納税の必要があるなら早めに準備を進めましょう。
申告書の提出先は『被相続人の住所地を所轄する税務署』です。相続した人の住所地を所轄する税務署ではない点に注意しましょう。
なお、相続税申告に必要な書類については、「相続税のための必要書類をプロが解説!【一覧表付】」も参考にしてください。
8.相続手続きは期限を意識して進めよう
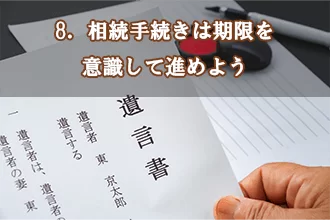
相続が発生すると、相続人の調査や遺産分割協議、相続税の申告など、さまざまな手続きが必要です。
申告や手続きに期限があるものは、期限が過ぎるとペナルティを課せられる可能性があるため、相続人はできるだけ早めに準備を進めるようにしましょう。
「初めての相続で右も左もわからない」「相続税が発生しそうだ」という場合は、実績豊富な『税理士法人チェスター』への相談をおすすめします。
『相続』については以下もご覧ください。
『相続』の手続きと流れ ~必要な知識と実務のすべて~|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































