【生産緑地とは】相続税評価額の計算方法や納税猶予の特例について解説
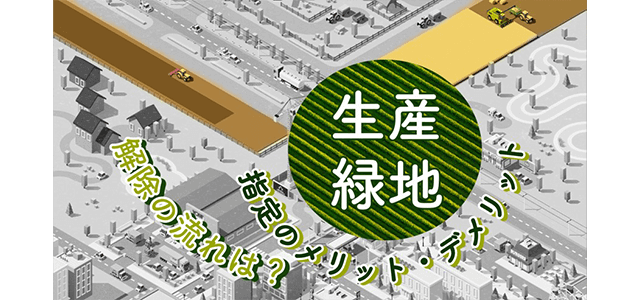
「生産緑地を相続したらどうなるの?」
「生産緑地は相続税が免除されるって聞いたけど本当?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、生産緑地を相続等で取得した相続人が、そのまま農業を継続するのであれば、相続税の納税猶予の特例を適用できるため、納税負担を大幅に軽減できます。
しかし、生産緑地法の規制がなされるため、数十年単位での営農義務が課され、その土地は農地として利用しなければなりません。
生産緑地の指定を解除する手続きをすれば、宅地として売却や活用ができるようになるものの、相続税の納税猶予の特例は適用できず、固定資産税の負担も重くなってしまいます。
本稿で、生産緑地を相続した際の基礎知識や税務についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.生産緑地とは
生産緑地とは、市街化区域内にある農地等のうち、良好な生活環境の確保に効果があるものとして、市町村に指定された農地のことをいいます。

生産緑地に指定されるためには、市街化区域の農地等が以下の3つの要件をすべて満たす必要があります(生産緑地法第3条第1項)。
- 良好な生活環境の確保に役立ち、かつ、公園や緑地など公共施設等の用地として適していること
- 面積が500㎡以上*の区域であること
- 農林漁業の継続が可能な条件を備えていること
*平成29年制度改正により、市町村条例を定めれば面積要件を300㎡まで引き下げることが可能(生産緑地法第3条第2項)
農地には緑地としての機能のほか、災害を防ぐ保水機能や災害時の避難先としての機能もあります。
生産緑地制度は、これらの農地の機能に着目し、市街化区域内においても安全で豊かな居住環境づくりに役立つ農地を計画的に残す目的で制定されました。
1-1.生産緑地に指定されているか否かの確認方法
生産緑地は、相続税評価額の計算方法などが通常の宅地等とは異なります。
そのため、相続財産である土地が生産緑地に指定されているか否か、以下のいずれかの方法で確認しなくてはなりません。
- 管轄する自治体のホームページで調べる
- 現地に「生産緑地地区」という看板が立てられているか否かを確認する
- 固定資産税納税通知書に「生産緑地」の記載の有無を確認する
詳しくは、「土地が生産緑地かどうかを簡単に知る方法:相続税が5%割引に?」をご覧ください。
\\CHECK//
この理由は、生産緑地の相続では、税務・法務・農地特有のルールなど、さまざまな専門知識が求められるためです。
取得した生産緑地の今後の利用方法によって、相続税や固定資産税の負担も変わってくるため、慎重な判断が必要です。
2.生産緑地のメリットは税制上の優遇
生産緑地に指定されると、以下のような税制上の優遇が受けられるというメリットがあります。
この章では、生産緑地に指定されるメリットをご紹介します。
2-1.固定資産税が軽減される
生産緑地に指定される1つ目のメリットは、固定資産税が軽減されることです。
固定資産税を課税するための「評価方法」と「課税方法」は、農地の区分によって以下のとおり異なります。
| 農地の区分 | 評価方法 | 課税方法 | |
|---|---|---|---|
| 一般農地 | 農地 | 農地 | |
| 市街化区域 | 生産緑地 | 農地 | 農地 |
| 一般市街化区域農地 | 宅地並み | 農地に準じる | |
| 特定市街化区域農地 | 宅地並み | 宅地並み | |
生産緑地は一般農地と同様に、「農地として評価・課税」されるため、固定資産税額が低く抑えられます。
農林水産省「農地の保有に対する税金(固定資産税)」によると、固定資産税の負担額は、生産緑地であれば「千円/10アール(1,000㎡)」あるものの、特定市街化区域農地は「十数万円/10アール(1,000㎡)」とされています。

出典:農林水産省「農地の保有に対する税金(固定資産税)」を加工して作成
生産緑地の指定を受けていれば、固定資産税が100分の1程度まで軽減されるのは、所有者にとって大きなメリットといえます。
2-2.農地の納税猶予の特例(免除)が受けられる
生産緑地に指定される2つ目のメリットは、相続税や贈与税に係る農地の納税猶予の特例が受けられることです。
農地の納税猶予の特例とは、農地を取得した相続人や受贈者が今後も農業を継続するなどの一定の要件を満たした場合、一定の相続税額や贈与税額の納税が猶予される特例のことです。

「猶予=先延ばし」とイメージされることが多いですが、納税猶予を取り消す条件にあてはまらなければ、やがて納税は免除されます。
そのため、相続や贈与で生産緑地を取得して営農を継続する場合は、納税負担が大幅に軽減されます(特例の概要や適用要件については後述します)。
3.生産緑地のデメリットは生産緑地法による規制
生産緑地に指定されると税制上の優遇がある一方、生産緑地法による以下のような規制がされるというデメリットがあります。
この章では、生産緑地に指定されるデメリットをご紹介します。
3-1.農業の継続が義務付けられる
生産緑地に指定される1つ目のデメリットは、農業の継続が義務付けられることです。
この理由は、生産緑地に指定されると、農地として管理しなければならないためです(生産緑地法第7条第1項)。
農地の管理について市町村から報告を求められたり、立入検査が実施されたりする場合もあります。
なお、生存中に農業をしなくなると、相続税や贈与税の納税猶予が打ち切られ、相続税・贈与税や利子税を支払う義務が発生します。
3-2.建築や開発は原則として制限される
生産緑地に指定される2つ目のデメリットは、建築や開発が制限されていることです。
生産緑地は農業以外の用途で利用することができませんので、以下のような建築や開発は原則としてできなくなります(生産緑地法第8条第1項)。
×宅地造成など土地の形質の変更
×水面の埋め立て
農業を営むために必要な建築等(温室、農業用倉庫など)で、生活環境の確保を図る上で支障がないと認められるものであれば、市町村長の許可を得て設置できます(生産緑地法第8条第2項)。
平成29年の制度改正では、農業者の収益性を高める施設として、加工施設・直売所・農家レストランも設置できるようになっています。
このように規制は緩和されていますが、農業を継続することが前提であることは変わりません。
3-3.生産緑地の指定を解除するのは難しい
生産緑地に指定される3つ目のデメリットは、指定の解除をするのが難しいことです。
生産緑地の指定を解除できるのは、以下のケースに限定されます。
- 生産緑地地区に指定されてから30年を経過した場合
- 主たる農業従事者が死亡した場合
- 主たる農業従事者が怪我や病気などで農業を継続できなくなった場合
生産緑地制度は良好な生活環境の確保を目的としていることから、簡単に生産緑地の指定を解除することはできません。
解除できるケースに該当する場合は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができるようになっています。
\\平成29年に「特定生産緑地制度」が制定//
生産緑地の告示を受けて30年の営農義務を終えてからでも、特定生産緑地の指定を受ければ、これまでの税制上の優遇をそのまま10年間継続することができます(その後も繰り返し10年間延長可能)。
詳しくは、「生産緑地の2022年問題とは~所有者の3つの選択肢~」をご覧ください。
4.生産緑地を相続した場合の4つの選択肢
生産緑地のメリットとデメリットを踏まえると、相続等で生産緑地を取得した相続人等には、以下の4つの選択肢があるといえます。
どの選択肢にするのかで、相続税の納税猶予の特例が適用できるか否かなどの取り扱いが変わります。
必ず税理士などの専門家に相談し、徹底的なシミュレーションをした上で、どの選択肢にするのかを決めましょう。
4-1.生産緑地の指定を継続して相続人が農業を営む
生産緑地を相続等で取得した場合の1つ目の選択肢は、生産緑地の指定を継続して、取得した相続人自らが農業を営むことです。
生産緑地の指定を継続すれば、生産緑地法による規制が継続されるため、一定の期間は買取りの申出ができません。
しかし、固定資産税や相続税・贈与税などの税制上の優遇を、引き続き受けることができます。
そのため、生産緑地を取得した相続人が農業を継続する意思があり、実際に継続できる状況であれば、生産緑地として保有し続けることをおすすめします。
4-2.生産緑地の指定を継続して第三者に貸付ける
生産緑地を相続等で取得した場合の2つ目の選択肢として、生産緑地の指定を継続して、第三者に貸付けるという方法もあります。
ただし、農地として管理することに変わりはありませんので、他の農業希望者への貸付や、市民農園などの公衆利用としての貸付に限定されます。
また、生産緑地の貸借には、事業計画の認定の基準を満たした上で、市町村長による認定を受けなくてはなりません。認定を受けられれば、相続税の納税猶予の特例を継続できます。
詳しくは、農林水産省「都市農地の貸借がしやすくなります」をご覧ください。
4-3.生産緑地の指定を解除して売却する
生産緑地を相続等で取得した場合の3つ目の選択肢は、生産緑地の指定を解除して売却することです。
生産緑地の指定を解除すると、土地は自由に利用できるようになりますが、それまで受けていた税制上のメリットがなくなります。
生産緑地の指定解除をして、単に農地としての管理義務(行為制限)が解消されただけであれば、収入はないため、納税ができないことも予想されます。
生産緑地の指定を解除する前に、納税額がいくらになるかを見積もることが重要です。
そのうえで、早急に土地を売却するか、あらかじめ納税資金を準備しておくなどの対策が必要です。
思うように土地が売れないリスクもありますので、まずは不動産会社に相談して、宅地としての需要があるかどうか確認することをおすすめします。
4-4.生産緑地の指定を解除して宅地として活用する
生産緑地を相続等で取得した場合の4つ目の選択肢は、生産緑地の指定を解除して、宅地として活用することです。
自己の居住用の宅地として利用しても良いですし、アパート経営などの不動産賃貸を始めても良いでしょう。
ただし、生産緑地の指定を解除すると、固定資産税は宅地並み課税となるため、税負担が100倍以上になることも想定されます。
そのため、税負担を賄えるだけの収入が得られるか否かをシミュレーションして、慎重に計画を立てなくてはなりません。
専門的な判断が必要となりますので、必ず税理士やファイナンシャルプランナーなどに相談をしましょう。
なお、生産緑地の指定から30年を経過して特定生産緑地の指定を受けなかった場合は激変緩和措置があり、5年間かけて宅地並みの税額に引き上げられます。
5.生産緑地の相続税評価額の計算方法
生産緑地は市街化区域内にありながら、利用が厳しく制限されているため、相続税の計算のもとになる相続税評価額も一定額減額されます。
生産緑地の指定を継続する・しないに関わらず、この税務上の取り扱いは同様です。
生産緑地の相続税評価額の計算式は以下の通りで、買取りの申出ができるか否かによって算入する割合が異なります。

買取りの申出とは、課税時期(被相続人の死亡日)において、市町村長に対して行う「生産緑地の指定を解除するための手続き」のことです。
生産緑地における指定の告示の日から起算して30年を経過する日以後、または、その告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。
5-1.相続税評価額は5%減額が一般的
相続等で生産緑地を取得した場合は、「買取りの申出が行われていた生産緑地」または「買取りの申出をすることができる生産緑地」として、相続税評価額の計算を行うのが一般的です。
この理由は、相続の場合は「主たる農業従事者が死亡した状態」に当てはまるため、たとえ生産緑地の指定から30年を経過していなくても、「買取りの申出ができる状態である」と考えられるからです。
そのため、生産緑地の相続税評価額は、【生産緑地でないものとして評価した価額×(1-5%)】で計算することとなります。
わかりやすく言うと、相続税評価額は5%しか減額されません。詳しくは、「生産緑地の相続税評価方法」をご覧ください。
6.生産緑地を相続したら「農地の納税猶予の特例」の適用の検討を
生産緑地の相続税評価額は5%の減額ができるものの、固定資産税評価額ほど大幅な減額はできませんので、相続税額が高くなることが予想されます。
そのため、相続税が課税されるケースにおいては、農地の納税猶予の特例の適用を検討しなくてはなりません。

冒頭でもご紹介しましたが、相続税に係る農地の納税猶予の特例とは、適用要件を満たすことで、農地を相続する相続人における一定の相続税額の納税が猶予される特例のことです。
農地の納税猶予の特例を適用できるのは、生産緑地の指定を継続する場合のみですのでご注意ください。
詳しくは、「【農地の納税猶予の特例とは】相続税免除の要件をプロが解説」でも解説しております。
6-1.納税猶予額の計算方法
納税猶予の特例において猶予される納税額は、以下の計算方法で算出します。

農業投資価格とは、農業に使用されることを前提にした売買価格として、国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」において、定められた価額のことです。
都道府県別に「10アール(1,000㎡)あたり約20~90万円」と、通常の宅地評価額に比べて低く設定されています。
6-2.農地の納税猶予の特例の適用要件
生産緑地を相続等で取得した場合、相続税に係る農地の納税猶予の特例を受けるためには、被相続人・相続人について、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。
被相続人の要件(以下のいずれかを満たす)
- 相続発生日まで農業を営んでいた
- 農地等の生前一括贈与をして贈与税の納税猶予を受けていた
- 死亡の日までに特定貸付けまたは認定都市農地貸付け等を行っていた
相続人の要件(以下のいずれかを満たす)
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、営農を継続する
- 農地等の生前一括贈与を受けた
- 相続税の申告期限までに特定貸付けまたは認定都市農地貸付け等を行った
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限までに相続した生産緑地をどうするのかを決め、相続税の納税猶予の特例を適用するか否かを決めなくてはなりません。
仮に相続税の納税猶予の特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合でも、相続税の申告は必要となりますので、失念されないようご注意ください。
詳しくは、「相続税なしでも申告が必要!?特例適用時の申告要否についてプロが解説」をご覧ください。
6-3.農地の納税猶予の特例を適用する際の注意点
農地の納税猶予の特例を適用した後に、条件を満たすことなく以下のいずれかの行為をすると、相続税の納税猶予が取り消されますのでご注意ください。
- 生産緑地を譲渡した
- 生産緑地を転用した
- 生産緑地での農業をやめた
- 3年毎の継続届出書を提出しなかった
- 生産緑地の買取り申出をした・指定解除された
納税猶予が取り消されると、猶予されていた贈与税・相続税に加えて、猶予されていた日数に応じた利子税も納めなければなりません。
7.生産緑地に係る相続手続き
生産緑地を相続したら、指定を継続するか解除するかに関わらず、以下の2つの相続手続きが必要となります。
生産緑地の指定を解除する場合も、これらの手続きをした後に、市町村に対して買取りの申出を行うこととなります。
7-1.農業委員会に相続した旨を届け出る
生産緑地を相続した場合は、農地の相続と同様に、農業委員会にその旨を届出ることが義務付けられています。
具体的には、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を、生産緑地を所在している市町村の農業委員会に提出することとなります。

なお、相続税申告の関係から、相続開始から10ヶ月以内に届け出る必要があり、怠った場合は過料に科せられることとなります。
7-2.相続登記(相続による所有権の移転登記)
相続登記とは生産緑地の所有者の名義を、被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。

令和6年4月からは相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に、管轄の法務局に相続登記の申請をしなくてはなりません。
放置すると様々なデメリットやリスクがありますので、期限までに相続登記を完了させましょう。
なお、相続登記の際には、必要書類の取得費用や登録免許税、司法書士への報酬が発生します。
詳しくは、「相続登記しないとどうなる?放置する8つのデメリットと申請手続きの流れ」をご覧ください。
8.相続で取得した生産緑地の指定を解除する方法
相続で取得した生産緑地で農業をする予定がないのであれば、生産緑地の指定を解除しなければなりません。
ただし、指定の解除をするためには、以下の手順を踏まなくてはなりません。
生産緑地の指定解除の手続きの流れ
①市町村に買取りの申出をする
②他の農家に買取りの斡旋がなされる
③生産緑地の指定が解除される
①市町村に買取りの申し出をして、必要と認めれば生産緑地は市町村に買い取られますが、実例はほぼありません。
その後は②他の農家に買取りの斡旋がなされますが、こちらも買い手がつかないケースが多いです。
ここで初めて農地としての管理義務(行為制限)は解除され、宅地開発や売却などが可能となります。
9.まとめ
生産緑地を相続等で取得した場合、今後も生産緑地としての指定を継続するのか、指定を解除するのかで、税務対応が異なります。
生産緑地としての指定を継続すれば、相続税の納税猶予の特例を適用できるため、相続税の負担を軽減できるものの、数十年単位で営農義務が課せられる上に、土地の利用に制限が設けられてしまいます。
一方で、生産緑地の指定を解除するのであれば、相続税や固定資産税の税負担が重くなってしまいます。
土地を自由に利用できるものの、売却・宅地活用もできなければ、固定資産税の負担だけが跳ね上がってしまうというリスクがあります。
相続財産に生産緑地が含まれる場合は、税理士やファイナンシャルプランナーに相談をした上で、指定を継続すべきか解除すべきか、最適な選択をしましょう。
9-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの相続税の申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。
生産緑地の申告経験もあり、相続税の納税猶予や今後の対応について税制面でのご相談を承ります。
グループ会社には不動産売却や活用に強い株式会社チェスターがあり、農地の売却のご相談もあわせてお伺いします。
生産緑地をお持ちで今後の対応をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
>>【相続税専門】税理士法人チェスター
>>【相続不動産のご相談】株式会社チェスター
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編






































