相続で残高証明書は必須!取得方法と注意点を銀行別にわかりやすく解説
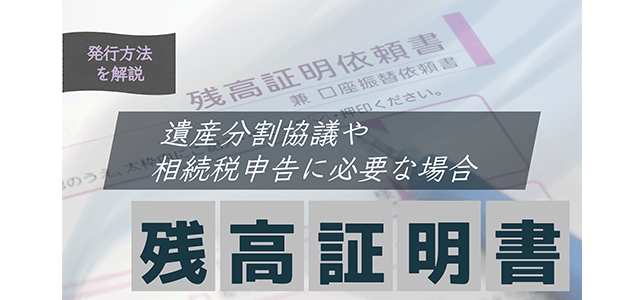
相続が発生した際、相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産をすべて洗い出して、遺産額を確定しなければなりません。その中で重要なことの1つに、被相続人が取引していた銀行などから「残高証明書」という書類を発行してもらうことがあります。
残高証明書とは、文字通り、銀行などの口座残高を証明する書類ですが、相続税申告の際は必須です。
他にも、これを取得しておかないと、後々の相続手続きで困ったり、トラブルの原因になったりする場合があります。
また、相続発生後に故人の残高証明書を発行してもらう際には、金融機関によって定められた手続きが必要になります。
本記事では、相続における残高証明書の必要性や、発行する際に必要となるもの、メガバンクなど、銀行ごとの発行手続きなどについて紹介します。
この記事の目次 [表示]
1.相続における残高証明書の必要性
金融機関が発行する「残高証明書」とは、特定の口座について、指定した日にいくらの残高があるのかを証明する書類です。
相続に伴う手続きをする際、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の金融機関口座残高の確認が必要になることがあります。その場合には相続開始日の残高が記載された残高証明書の発行を、被相続人が口座を開設していた金融機関に依頼します。
残高証明書が必要かどうかを判断するときのポイントは、次の2点です。
- ①相続税の申告が必要か
- ②遺産分割協議が必要か
相続税の申告または遺産分割協議が必要な場合は、残高証明書を入手する必要があります。また、それらが必要ない場合でも、相続開始時点での被相続人の財産がいくらだったのかを知る必要がある場合は、残高証明書を取得しなければなりません。
1-1.相続税の申告をするときに必要となる
相続税の申告が必要な場合、遺産に銀行預金が含まれているのならば、残高証明書を申告書に添付して提出します。銀行預金をまったくしていないという人は、現実にはほとんどいないので、残高証明書の取得は必須だといえるでしょう。
なお、相続税の申告に際して残高証明書の提出が義務付けられているわけではありませんが、残高証明書を添付すれば金額がいくらなのか明確になるため、相続税申告書に添付して提出することが一般的です。
ここで、通帳があるのだから、通帳のコピーでもいいではないか、と思われる方がいるかもしれません。
残高証明書には、被相続人がある金融機関で普通預金や定期預金など複数の口座を持っていた場合に、その金融機関と被相続人とのすべての取引が記載されるので、金額が明確になります。
一方、預金通帳のコピーだけでは、「提出された通帳の口座以外にも口座があるのではないか?」と税務署の職員に疑念を抱かれる恐れがあります。
税務署から余計な問い合わせや調査を受けることがないよう、相続税の申告が必要な場合には最初から残高証明書を取得して、申告書と一緒に提出しておくほうが安心です。
なお、遺産を相続した場合でも、遺産額が基礎控除額以下であれば相続税の申告義務は生じません。相続税の申告義務がなければ、基本的に申告書の提出は不要です。当然、残高証明書の添付、提出も不要です。
(参考)相続税の申告義務あり?なし?要否判定のポイントを解説
1-2.遺産分割協議での信頼性を高められる
相続人が2人以上おり、かつ、遺言書によって遺産の相続方法が指定されていない場合は、遺産をどのようにわけるのかを、相続人の間で話し合って決める必要があります。この遺産の分割方法を決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議で対象となる遺産の金額とは、生前に受けた特別受益などの一部例外を除いて、基本的に相続開始日の金額となります。そのため、遺産に含まれる個々の財産について被相続人が亡くなった日付における金額を把握する必要があります。
預金額を把握する場合は銀行に依頼して残高証明書を取得すれば相続開始日における金額を把握できます。金融機関が発行する正式な書類なので金額に間違いはありません。遺産分割協議で信頼性を高められます。
この場合も、「預金通帳を確認すればよいのでは?」と考える人もいるかもしれませんが、被相続人が最後に記帳した後に、入出金や引き落としがされている可能性があるので、通帳に記載された預金額と相続開始日の預金額が同じとは限りません。
遺産分割という、一生に何度もない手続きをするのですから、財産確認の確実性を高め、無用なトラブルを防止するためにも、残高証明書を取得しておきましょう。
(参考)遺産分割協議書の預金記載例|分割後の払戻手続をスムーズにおこなうコツ
1-3.相続人が勝手に口座の預金を引き出すことを防ぐ
口座の名義人が亡くなったことを金融機関が知ると、原則的に、その人の口座は凍結され、遺産分割協議が済むまで、一切の取引ができなくなります(例外として、一定金額までの「仮払い制度」があります)。
しかし、口座の名義人が亡くなった後でも、そのことを金融機関が知らずに、口座が凍結される前であれば、場合によっては、預金を自由に引き出せます。
たとえば、親が高齢で体が不自由な場合などに、子が親の銀行のキャッシュカードを預かり、生活費を引き出している、といったことはよくあります。このような状況で相続が発生すると、銀行口座が凍結される前に、その子が勝手に預金を引き出してしまう恐れもあります。
そこで、相続が発生したことを銀行に伝えて残高証明書を発行してもらい、口座を凍結してもらうとともに、相続時点での預金残高を確定しておけば、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことはできなくなります。
2.残高証明書はいつ発行してもらうべき?
上で述べたように、被相続人の生前、一部の相続人がその預金口座を管理していたような場合は、不正を防ぐためにも、相続発生後なるべく早くに口座の凍結と残高証明書の発行をしてもらったほうがいいでしょう。
そのような恐れがない場合でも、遺産分割協議前の、遺産にどのような財産が含まれるのかを調べる相続財産調査をおこなうときに、残高証明書を取得しておくとよいでしょう。
一般的には、いわゆる「四十九日の法要」が済んだ後で、相続財産調査や遺産分割の話し合いが始められることが多いようです。
(参考)相続手続きの流れと期限を一挙解説!いつまでにどのような手続きが必要?
2-1.相続放棄、限定承認の期限である3か月に注意
相続財産調査の結果、被相続人の多額の借金が判明するなどして、相続放棄や限定承認を家庭裁判所に申し立てたいことがあります。その場合の、手続き期限は相続発生後3か月以内です。
財産調査には意外と時間がかかることがあるので、3か月の期限に注意しておきましょう。
その際に、残高証明書についても、即日で発行してくれる金融機関もありますが、1~2週間ほどかかる金融機関もあるので、財産調査を始めることになったらすぐに残高証明書の取得手続きを進めましょう。
(参考)相続の限定承認とは?検討すべきケースや手続きをわかりやすく解説
3.残高証明書を発行してもらう方法
残高証明書を発行してもらうための手続き方法は、金融機関ごとに異なる部分もあります。
代表的な金融機関の手続き例は、後でまとめて示しますが、まず、一般的にどのような方法で残高証明書を発行するのか、また費用の目安などを確認しておきましょう。
3-1.残高証明書の発行に必要な書類等
被相続人の銀行口座の残高証明書を発行してもらう場合、金融機関所定の「残高証明書発行依頼書」に必要事項を記入した上で必要書類を添付して提出します。
必要書類として提出を求められる書類は、一般的に以下のような書類です。
- 戸籍謄本など口座名義人の死亡を確認できる書類
- 戸籍謄本など手続きする人が相続人・遺言執行者・相続財産管理人と確認できる書類
(または、法定相続情報一覧図の写し) - 免許証など手続きする人の本人確認書類
- 手続きする人の実印と印鑑証明書(6か月以内に発行されたもの)
- 通帳・証書・キャッシュカードなど被相続人の取引内容が分かるもの
- 代理人が申請する場合、委任状など
(参考)残高証明書の発行依頼の方法
3-2.誰が残高証明書の発行を申請できるのか?
残高証明書の発行は、各相続人が単独で申請することができます。相続人全員の合意が必要になったり、共同で発行を申請したりするものではありません。
また相続人だけでなく遺言執行者や相続財産管理人も残高証明書の発行を申請できます。
3-3.残高証明書は代理人でも申請できるのか?
多くの金融機関では、相続人本人だけでなく、代理人による残高証明書の発行申請を受け付けています。ただし代理人として申請できる人の範囲は金融機関によって異なります。
委任状を託して代理人に申請を任せる場合は、事前に金融機関に問い合わせてその人が代理で申請できるかどうか確認するようにしてください。
3-4.具体的なプロセスは金融機関ごとに多少異なる
残高証明書の発行手続きの具体的なプロセスは、金融機関によって異なります。被相続人が亡くなったことを電話などで伝えてから窓口を訪れなければいけない金融機関もあれば、いきなり直接窓口へ行って手続きする金融機関もあります。
まずは口座のある支店やカスタマーセンターに電話で問い合わせて手続き方法を確認しましょう。
3-5.残高証明書の発行にかかる費用
残高証明書の発行にかかる手数料の金額は金融機関によって異なります。2022年5月時点の主な金融機関の発行手数料は、以下のとおりです。
| ゆうちょ銀行 | 1,100円 |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 770円 |
| 三井住友銀行 | 880円 |
| みずほ銀行 | 880円 |
| りそな銀行 | 880円 |
| 福岡銀行 | 440円または550円(証明日が依頼日から1か月以内の場合は440円) |
| 横浜銀行 | 770円 |
| 千葉銀行 | 770円 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 550円 |
| 三井住友信託銀行 | 220円 |
| みずほ信託銀行 | 880円 |
なお、定期預金の場合は、最後に利息が支払われた日から被相続人が亡くなった日までに生じた利息(経過利息)も相続財産になるため、残高証明書に加えて経過利息計算書も必要です。
経過利息計算書の発行は数千円ほどの手数料がかかる場合があります。(例:三菱UFJ銀行では2,200円)
4.銀行ごとの発行方法
相続の開始に伴って残高証明書を発行する場合、各金融機関が定める手続き方法に従って発行します。
ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行で残高証明書の発行が必要な場合は、以下で紹介する手続き方法の概要を確認の上、各金融機関のサイトで最寄りの支店やカスタマーセンターの電話番号などを確認して手続きを進めるようにしてください。
4-1.ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行で残高証明書を発行してもらう場合は、戸籍謄本や相続人の本人確認書類などを窓口に持参して手続きします。
残高証明書は基本的に即日で発行が可能です。
ただし貯金の種類等によっては即日で発行できない場合があります。また残高証明をおこなう口座の記号番号が不明な場合には即日発行はできません。この場合には被相続人名義の口座があるかどうかを調べる現存調査の手続きが必要になります。
(参考:公式サイト)残高証明書の発行|ゆうちょ銀行
4-2.三菱UFJ銀行
三菱UFJ銀行で残高証明書を発行してもらう場合、最寄りの支店に戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、実印などを持参して手続きをします。
口座がある支店以外の支店でも手続きが可能です。
郵送によって受け取る場合は手続き後1~2週間ほどで残高証明書が届きます。
銀行の窓口が混雑する場合があるので、事前にネットで来店予約をしてから訪問するほうがよいでしょう。
なお口座名義人が亡くなったことを銀行に伝えていない場合は、残高証明書の発行手続きの前にまずは相続が開始したことを銀行に連絡する必要があります。その場合は被相続人の預金口座の通帳やキャッシュカードなどを手元に用意した上で、三菱UFJ銀行の相続オフィスに電話で連絡してください。
(参考:公式サイト)よくあるご質問|三菱UFJ銀行
4-3.三井住友銀行
三井住友銀行で残高証明書を発行してもらう場合も、口座がある支店でなくても最寄りの支店で手続きが可能です。
戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、実印などを持参して手続きをおこないます。事前にネットで来店予約をしておけば待ち時間なく手続きをできます。手続き後、1~2週間ほどすると残高証明書が郵送で届きます。
また相続が開始したことをまだ伝えていない場合にはその旨をまずは銀行に連絡する必要があるので、その場合は被相続人の預金口座の通帳やキャッシュカードなどを手元に用意した上で、三井住友銀行の相続オフィスに電話で連絡しましょう。
(参考:公式サイト)残高証明書・預金入出金取引証明の発行|三井住友銀行
4-4.みずほ銀行
みずほ銀行で預金の相続手続きや残高証明書の発行手続きをする場合、口座がある支店か最寄りの支店に連絡をして手続きをおこないます。
残高証明書を発行する場合は戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、実印などが必要です。
取引店以外の支店で手続きをする場合は、口座がある支店への取次ぎとなるため日数がかかる場合があります。
(参考:公式サイト)(相続用)残高証明書の発行依頼|みずほ銀行
5.残高証明書を発行するときの注意点
残高証明書を発行してもらった後で困らないよう、注意すべき点がいくつかあります。
5-1.名義人の死亡を金融機関が知ると口座は凍結される
上でも述べましたが、被相続人が亡くなったことや相続の手続きで残高証明書が必要な旨を金融機関に伝えると、その口座は凍結されて取引ができなくなります。公共料金や家賃、クレジットカードなどの引落口座になっている場合、口座凍結後は引き落としができなくなります。
引き落としができなくなると困る場合には引落口座の変更などをする必要があります。口座を凍結する前に預金通帳の履歴を確認して、公共料金などの引き落としがされていないかを確認しておきましょう。
(参考)亡くなると預金は口座凍結される?凍結の解除方法と生前の対策を専門家が解説
5-2.残高証明書は亡くなった日付で発行を依頼する
残高証明書の発行を依頼する際には、いつの時点での残高を示すのかを指定する必要があります。
相続の手続きで残高証明書を発行する場合、日付は相続が発生した日=被相続人が亡くなった日で指定します。それ以外の日付で発行してしまうと遺産分割協議をおこなう際の資料や相続税の申告書の添付書類として意味をなさなくなります。
再度発行の手続きが必要になり余計な手間がかかってしまうので、発行の手続きでは日付を間違えないように注意してください。
5-3.経過利息も含めて計算を依頼する
遺産に定期預金が含まれる場合、期間の経過に応じて発生している利息も相続財産のひとつになります。相続財産調査をおこなうときや相続税の申告をする際、残高証明書だけでなく利息額が記載された経過利息計算書も必要になるので、経過利息計算書の発行手続きも忘れずにおこないましょう。
(参考)相続で定期預金はどのように分ける?金融機関で必要な手続きとは
5-4.他に口座を持っていないかも要注意
被相続人が1つの銀行で、複数の支店に預金口座を持っていることもあります。現在では、原則的に1つの銀行に1つの口座しか開設できませんが、昔はそういう制約はなかったので、昔作った口座を複数持っている場合もあります。
この場合、銀行に「名寄せ」という手続きを依頼すれば、その銀行の全支店口座を調べてくれます。
また、それとは別の話ですが、預金通帳やキャッシュカードなどは見つからないけれども、その銀行で取引していた形跡がある(たとえば銀行の名前入りのカレンダーがある、など)という場合は、その銀行に口座の有無を照会してみましょう。
必要な手続きなどは銀行によって異なりますので、問い合わせてみてください。
6.残高証明書を発行して相続財産を把握しよう
遺産に銀行預金が含まれる場合、被相続人が亡くなった日付の残高証明書を取得して残高を確認する必要があります。通帳に記載された預金額が相続開始日の預金額と同じとは限らないので、相続財産調査をおこなう場合や遺産分割協議、相続税の申告をする場合は、金融機関から残高証明書を取り寄せるようにしてください。
残高証明書の発行手続きの流れや必要書類は金融機関によって異なり、手続きに必要な書類を揃えるまでに時間がかかる場合や申請しても発行までに日数がかかる場合があります。残高証明書が必要な場合は早めに手続きをおこないましょう。
相続手続きで必要なものをすべてご自身で準備しようとすると時間も手間もかかりますので、相続のことでお困りの方はぜひ一度税理士法人チェスターにお問い合わせください。税理士法人チェスターでは相続財産調査や相続税の申告など、相続手続きに関するサポートを幅広くおこなっています。
(参考)相続税に強い税理士の選び方 – 失敗しない9つのポイント|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編






































