遺産相続手続きの期限はいつまで?過ぎた場合のデメリット【一覧表あり】
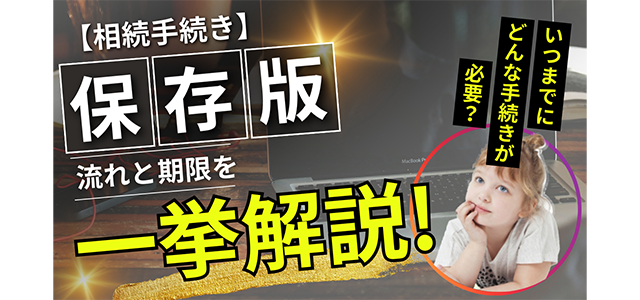
遺産相続が発生した場合、遺族や法定相続人は定められた期限までに、様々な手続きを行わなければなりません。
特に重要なのは、3ヶ月以内の相続放棄、10ヶ月以内の相続税申告・3年以内の相続登記(土地や建物の名義変更)です。

期限までに遺産相続手続きを完了させないと、権利を失う・税金が加算される・罰則が課せられるなどのデメリットがあるのでご注意ください。
この記事では、遺産相続手続きの期限はもちろん、具体的な流れや内容についてまとめました。
相続発生後のみならず、生前対策を考えるときにもぜひお役立てください。
この記事の目次 [表示]
- 1 1.遺産相続手続きには期限が定められている【一覧表】
- 2 2.【7日以内】死亡届や火葬許可申請書の提出
- 3 3.【14日以内】年金・健康保険に係る手続きや世帯主の変更届
- 4 4.【速やかに】法定相続人や相続財産の確定
- 5 5.【3ヶ月以内】相続放棄(限定承認)の申述手続き
- 6 6.【4ヶ月以内】準確定申告や青色申告を引き継ぐ手続き
- 7 7.【10ヶ月以内】遺産分割や相続税の申告・納付
- 8 8.【1年以内】遺留分侵害額の請求
- 9 9.【2年以内】年金や健康保険から支払われる金銭の申請・請求
- 10 10.【3年以内】相続登記や死亡保険金の請求
- 11 11.【5年以内】未支給年金や遺族年金などの請求
- 12 12.【5年10ヶ月以内】相続税の更正の請求
- 13 13.遺産相続の手続きが期限を過ぎた場合のデメリット
- 14 14.遺産相続手続きが楽になる!生前から準備を始めよう
- 15 15.まとめ
1.遺産相続手続きには期限が定められている【一覧表】
遺産相続に係る手続きの中には、期限が設けられているものもあります。
遺産相続手続きをスムーズに進めるためにも、いつまでに・どの順番で手続きを進めるのかを把握しておくことが重要です。
以下は遺産相続に係る手続き期限の一覧表ですので、参考にしてください。

特に重要なのは、相続開始から3ヶ月以内・10ヶ月以内・3年以内と期限が定められている遺産相続手続きです。
実際の手続きは多少前後しても構いませんので、なるべく早く相続手続きを済ませるようにしましょう。
なお、相続手続きの期限の起算点は、相続の開始があったことを知った日(一般的には死亡日)です。
「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」や「【相続手続きの必要書類一覧】効率的な集め方や入手方法を解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。
1-1.遺産相続の手続きを期限までに終わらせるためのポイント
遺産相続の手続きを期限までに終わらせるためにも、専門家にサポートを依頼されることをおすすめします。
専門家に依頼すれば手間が省けるだけでなく、迅速かつ正確に手続きをしてもらえます。
しかし、相続手続きを一手に引き受けることができる専門資格はなく、どの相続手続きのサポートを依頼するのかで、対応できる士業が異なります。
以下は依頼する専門家を見極める状況別フローチャートですので、ぜひ参考にしてください。

詳しくは「相続のサポートはどの専門家に依頼すべき?税理士?司法書士?」や「相続手続きの代行は誰に依頼する?【プロが解説】選び方と費用の相場」もあわせてご覧ください。
\\CHECK//
チェスターグループであれば、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能です。
すでに相続が発生しているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
チェスターグループに相談する
2.【7日以内】死亡届や火葬許可申請書の提出
相続開始から7日以内と期限が定められているのは、死亡届や火葬許可申請など、被相続人の死亡に係る以下のような手続きです。
家族など身近な人が死亡したときは、親族や勤務先への連絡や葬儀の手配などを進めながら、死亡後すぐに必要な手続きを行っていきます。
なお、死亡から7日以内が期限の相続手続きの多くは、葬儀社が代行をしてくれるのが一般的です。故人を見送ることを優先しましょう。
2-1.死亡診断書(死体検案書)を受け取る
家族など身近な人が病院で死亡したときは、医師に死亡診断書を発行してもらいます。
死亡診断書は、故人が死亡したことを医学的・法的に証明するものです。
このあとさまざまな相続手続きで必要になるため、死亡がわかった日の翌日までに発行してもらいましょう。

死亡診断書は、死亡届と1枚の用紙になっています。死亡届を提出すると死亡診断書は手元に残らないため、何枚かコピーを取っておきましょう。
なお、事故による死亡の場合は警察から死体検案書として発行されますが、相続手続きでは死亡診断書と同じ効力があります。
2-2.死亡届の提出・火葬許可の申請
死亡の事実を知った日(死亡診断書を受け取った日)から7日以内に、死亡届を提出する必要があります。
死亡届の提出先は、死亡した場所・死亡した人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。
実際には葬祭業者が死亡届を市区町村役場に提出しますが、死亡届の記入は遺族が自ら行います。
引用:法務省「死亡届」
死亡届は死亡診断書と1枚の用紙になっているので、死亡診断書をもらったら死亡届に必要事項を記入しましょう。
死亡届の提出と同時に、火葬許可の申請をします。遺体を火葬するときは火葬許可証が必要です。
死亡届の書き方について、詳しくは「3分でわかる死亡届の書き方~この通り書けば提出できます!」をご覧ください。
2-3.火葬許可証の提出・埋葬許可証を受け取る
火葬場に火葬許可証を提出し、火葬が終われば埋葬許可証を受け取ります。
埋葬許可証の正式名称は「火葬証明書」ですが、遺骨をお墓や納骨堂に納めるときに必要であることから、一般的には「埋葬許可証」と呼ばれています。
埋葬許可証は遺骨をお墓に埋葬する際に必要な許可証ですので、遺骨のそばで保管するなどして紛失しないようにしましょう。
3.【14日以内】年金・健康保険に係る手続きや世帯主の変更届
相続開始から14日以内と期限が定められているのは、年金や健康保険など、役所で行う以下のような相続手続きです。
これらの相続手続きは葬儀が終わってからでも間に合いますが、役所の開庁時間内に行う必要があります。なるべく早く手続きを行いましょう。
3-1.年金の受給停止手続き
故人が国民年金や厚生年金などの公的年金の受給者であった場合、遺族は年金の受給停止手続きが必要です(基礎年金番号とマイナンバーが結びついている場合は手続き不要)。
具体的には、以下の期限までに、年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
| 期限 | |
|---|---|
| 国民年金 | 死亡日から14日以内 |
| 厚生年金 | 死亡日から10日以内 |
| 共済年金 | 死亡日から10日以内 |
公的年金は過去2ヶ月分がまとめて支給されるため、死亡の直後ではまだ受け取っていない「未支給年金」があります。
また、生計を維持していた人が亡くなった場合、遺族が困らないように支給される「遺族年金」を受給できる可能性もあります。
該当する場合は、年金の受給停止手続きと同時に手続きを行いましょう。
詳しくは「相続発生後の年金手続き!課税対象となる年金は?確定申告は必要?」をご覧ください。
3-2.健康保険の資格喪失手続き
故人が加入していた健康保険の資格喪失届を提出し、健康保険証を返却する必要があります。
なお、故人がどの健康保険に加入していたのかで、資格喪失手続きを行う期限や場所が異なります。
| 期限 | 申請先 | |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 死亡から14日以内 | 市区町村役場 |
| その他の健康保険 (社会保険) | 死亡から5日以内 | 勤務先※ |
※任意継続の場合は健康保険組合に申請
世帯主が死亡したときは、扶養されていた家族も加入資格を失います。
新たに世帯主を決めて国民健康保険に加入するか、会社などに勤めている人の扶養家族として健康保険(被用者保険)に加入しなければなりません。
なお、健康保険からは葬祭費や埋葬料などが支給されますので、資格喪失手続きと同時に請求しておくとよいでしょう。
詳しくは「国民健康保険資格喪失届は死亡から14日以内に届け出を」をご覧ください。
3-3.介護保険の資格喪失手続き
介護保険の被保険者が死亡した場合は、死亡から14日以内に、市区町村役場に介護保険の資格喪失届を提出します。
要介護認定を受けていた場合は、介護保険被保険者証を返却する必要があります。
なお、介護保険の資格喪失手続きでは保険料が再計算されます。保険料が不足すれば遺族に請求され、払い過ぎがあれば還付されます。
3-4.世帯主の変更手続き
世帯主が死亡した場合は、死亡から14日以内に新しい世帯主を決めて、故人の住所の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出します。
ただし、世帯に残った人が1人だけの場合や、親と15歳未満の子供だけの場合など、誰が世帯主になるかが明らかな場合は提出が不要です。
詳しくは「世帯主変更届とは?親から子の変更方法・手続きの流れ・書き方を解説」をご覧ください。
3-5.公共料金や加入サービスの名義変更・解約(落ち着き次第)
葬儀が終わって少し落ち着いたころから、本格的に相続手続きを始めます。
以下の相続手続きに期限は定められていませんが、無駄なお金を払うことがないように早めに手続きをしましょう。
- 電気・ガス・水道・電話・NHKなどの解約や名義変更
- インターネットサービスやSNSの解約
- クレジットカードの解約
- 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返却
- 固定資産税・住民税の請求先変更手続き
4.【速やかに】法定相続人や相続財産の確定
葬儀や市区町村役場での相続手続きが落ち着いた頃から、遺産相続の準備を始めるために、以下のような手続きを行います。
これらの遺産相続の準備をするための手続きは、法律で期限が定められている訳ではありません。
しかし、これらの相続手続きを完了しないと、次のステップに進めませんので、相続開始から3ヶ月以内(四十九日法要が目安)には終わらせるようにしましょう。
4-1.法定相続人を確定する
まずは被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得して、誰が法定相続人になるのかを確定します。
法定相続人とは、被相続人の遺産を相続する権利を有する、一定の範囲の親族のことで、民法で以下のとおり優先順位(相続順位)が定められています。

戸籍調査をした結果、養子・前妻との間に生まれた子・隠し子など、思いもよらない法定相続人が見つかることもあります。
知らない人であっても、法定相続人である以上、その人を除いて遺産相続の手続きをすることはできませんのでご注意ください。
戸籍調査のやり方について、詳しくは「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」をご覧ください。
4-2.相続財産を調査・確定する
戸籍調査と並行して、相続財産がどこにいくらあるかも調査して、その内容を確定しておきます。
相続財産を正確に調べておけば、遺産相続の手続きをスムーズに進められ、相続税の申告漏れを防ぐこともできます。
故人の借金を肩代わりしないで済むように、借金や債務保証の有無も調べておきましょう。

まずは、被相続人の自宅で、預金通帳や不動産の権利証(登記済証・登記識別情報)などを探します。
借金については、借用書や金銭消費貸借契約書を探します。預金通帳に借入や返済の記録があればそれも手がかりになります。
判明した相続財産は、それぞれの相続税評価額を計算した上で、財産目録にまとめておきましょう。
詳しくは「相続が発生したら遺産の調査をしましょう!!」や「財産目録とは?相続における作成目的・書き方【無料Excel書式&記載例付】」をご覧ください。
4-3.遺言書の有無を確認
相続財産を調査するときは、同時に以下のような遺言書があるかどうかも確認します。
| 保管場所 | |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅・貸金庫・法務局 |
| 公正証書遺言 | 原本は法務局(正本は自宅などで保管) |
全国の法務局で、遺言書情報証明書の発行やモニターによる遺言書の閲覧が可能です。
ただし、遺言書の原本の確認は、自筆証書遺言が保管されている法務局に限られますのでご注意ください。
なお、公正証書遺言は、最寄りの公証役場で遺言検索をすることで、原本が保管されているか否かを調べられます。
詳しくは「遺言検索システムとは?使い方・遺言書の見つけ方・利用方法や必要書類を解説」をご覧ください。
4-4.遺言書の検認手続き
自宅や貸金庫など法務局以外の場所で、自筆証書遺言が保管されていた場合は、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをしなければなりません。
検認とは、遺言書が形式的な要件を満たしているかを確認して、偽造や変造を防ぐための手続きです。
検認されていない自筆証書遺言は、このあとの相続手続きで使うことができません。
遺言書の検認手続きは、1ヶ月以上かかることもあるため、できるだけ早く家庭裁判所に申立てをしましょう。
一方、公正証書遺言や法務局で保管されていた自筆証書遺言は、検認手続きの必要はありません。
検認手続きについて、詳しくは「遺言書の検認とは│必要なケースや手続き方法・費用を解説」をご覧ください。
5.【3ヶ月以内】相続放棄(限定承認)の申述手続き
相続開始から3ヶ月以内と期限が定められているのは、相続放棄や限定承認の申述手続きです。
遺産相続の対象となるのは、現金や不動産などのプラスの財産のみならず、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。
つまり、被相続人に借金などの負債がある場合、相続人が引き継いで返済しなければなりません。
ただし、相続放棄を選択した法定相続人は、被相続人の借金を返済しなくてもよくなります。
実例は少ないですが、限定承認を選択できれば、相続する財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続することもできます。
5-1.相続放棄の申述手続き
相続放棄とは、法定相続人が被相続人の権利や義務をすべて放棄することです。
相続放棄をすれば、預貯金や不動産などのプラスの財産を一切相続しない代わりに、借金などのマイナスの財産の返済義務を負うこともありません。

相続放棄をするためには、自己のために相続があったことを知った日(通常は故人の死亡日)から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
相続放棄の申述手続きについて、詳しくは「相続放棄は自分でできる!手続き・費用・期間・注意点を解説」をご覧ください。
5-2.限定承認の申述手続き
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産の返済義務を負うという条件で、遺産相続を承認することです。
限定承認の申述手続きの期限も死亡から3ヶ月以内で、法定相続人全員の同意が必要となります。

限定承認の申述手続きは非常に複雑であるため、選択されるのはごく稀です。
限定承認の申述手続きについて、詳しくは「限定承認は相続したい財産がある時に便利!限定承認の6つのポイント」をご覧ください。
6.【4ヶ月以内】準確定申告や青色申告を引き継ぐ手続き
相続開始から4ヶ月以内と期限が定められているのは、被相続人の所得税に係る、以下のような手続きです。
対象となるのは、被相続人が自営業やアパート経営などをして、生前に所得税の確定申告をしていた場合です。
死亡年の被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)をするほか、相続人が事業を引き継ぐ場合は青色申告を引き継ぐ手続きも行います。
6-1.所得税の準確定申告
所得税の準確定申告とは、被相続人の死亡年の所得税の確定申告を、法定相続人が代わりに行うことです。
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日(通常は故人の死亡日)の翌日から4ヶ月以内です。

相続開始が年末であれば、通常の確定申告の期限(翌年3月15日)が先になりますが、その場合も死亡から4ヶ月以内に提出すれば良いことになっています。
準確定申告について、詳しくは「【準確定申告とは】必要・不要の判断方法、記入例などを解説」をご覧ください。
6-2.青色申告を引き継ぐ手続き
被相続人の事業を引き継いだ相続人が青色申告を行う場合は、税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
申請書の提出期限は、原則として相続開始から4ヶ月以内ですが、被相続人が9月以降に死亡した場合は期限が繰り上げられます。
| 死亡日 | 青色申告承認申請の期限 |
|---|---|
| 1月1日~8月31日 | 死亡の日から4ヶ月以内 |
| 9月1日~10月31日 | その年の12月31日まで |
| 11月1日~12月31日 | 翌年の2月15日まで |
詳しくは「事業を承継した相続人が青色申告者になるための青色申告承認申請書の提出期限」をご覧ください。
7.【10ヶ月以内】遺産分割や相続税の申告・納付
相続開始から10ヶ月以内と期限が定められているのは、相続税の申告・納税です。
これに伴い、申告書を作成するために遺産分割方法を決め、納税資金を確保するために相続財産の名義変更などの手続きも済ませておくのがベストです。
相続税の申告・納付義務があるのは、遺産総額が相続税の基礎控除【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】を超えたケースのみです。
相続税の申告書の作成には時間がかかるため、8ヶ月以内を目安に早めに準備を始めましょう。
7-1.遺産分割協議をする(遺言書がないケースのみ)
被相続人が遺言書を残していない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が・どの財産を・どれだけ・どのように取得するのかを話し合います。
遺産分割協議自体に期限は定められていませんが、遺産の分割方法が決まらなければ相続財産の名義変更も相続税申告もできません。なるべく早い段階で遺産分割協議を始めましょう。

どのように遺産分割するのかという目安として、民法では法定相続分が定められています。
しかし、法定相続分のとおりに遺産分割をする義務はなく、特別受益や寄与分を考慮する必要もあります。
遺産分割の進め方について、詳しくは「遺産分割の進め方を解説。書面に残すときに気を付ける点を把握しよう」をご覧ください。
7-2.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書に法定相続人全員が合意した協議の内容を記録します。
遺産分割協議書は、遺産相続のあらゆる手続きで提出を求められますので、できるだけ早く作成しましょう。

遺産分割協議書はご自分でも作成していただけますが、行政書士・税理士(注)・司法書士・弁護士などに作成を依頼することも可能です。
(注)遺産分割協議書の作成を税理士に依頼できるのは、相続税申告で税務署に提出する必要がある場合に限られます。相続税申告が必要ない場合は、税理士は遺産分割協議書を作成できません。
遺産分割協議書の作成方法について、詳しくは「遺産分割協議書を自分で作成する方法!流れや書き方【ひな形・文例付き】」をご覧ください。
7-3.銀行の預貯金の相続手続き(払い戻し等)
相続税の納付は現金一括が原則ですので、相続税の申告・納付期限までには、銀行の預貯金の払い戻し手続きをして、納税資金を準備しておきましょう。
銀行の預貯金の払い戻し手続きは、銀行側の内容確認がありますので、1週間~1ヶ月程度はかかります。
提出書類に不備があるとさらに時間がかかりますので、なるべく早い段階で手続きを始めましょう。

なお、遺産分割が終わらないものの、一定金額を払い戻ししたい場合は、相続預金の払い戻し制度を利用できます。
銀行の相続手続きについて、詳しくは「【預貯金の相続に必要な手続き】必要書類や期限、リスクを解説」をご覧ください。
7-4.証券口座の相続手続き(口座開設・移管)
証券口座の相続手続きについても、期限は定められていません。
しかし、納税資金が足りない場合もありますし、株式・債権・投資信託などは管理が必要となるため、なるべく早い段階で相続手続きを始めましょう。
株式・債券・投資信託など故人が証券口座で保有していた有価証券は、相続人が開設した口座に移管します。基本的に、故人の口座で直接換金して、払い出すことはできません。
相続手続きの詳細は、取引先の銀行・証券会社などで確認してください。
株式の相続手続きについて、詳しくは「株式を相続する場合のポイントや相続税評価の方法を税理士が解説」をご覧ください。
7-5.自動車の相続手続き(名義変更)
被相続人名義の自動車は、新しい所有者が決まった日から15日以内に、移転登録(名義変更)の申請手続きが必要です。
なお普通車の場合は運輸支局または自動車検査登録事務所で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きを行います。
名義変更をしないで放置すると、車検を受けることができなくなりますし、自動車保険の補償も受けられません。売却も廃車もできません。
所有者が決まった時点で、自動車の相続手続きを始めましょう。
詳しくは「自動車の所有者が死亡した際の手続き│名義変更の期限・相続税も解説」でも解説しております。
7-6.相続税の申告・納税
相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日(死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
ただし、遺産相続をしたからといって、必ずしも相続税が課税される訳ではありません。
遺産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合のみ、相続税を申告・納税する義務があります。

相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りで、法定相続人の数によって変動します。
3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
※法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして数え、養子の人数には制限があります。
相続税の申告書はご自分で作成することもできますが、専門知識を必要とすることが多いため、相続税専門の税理士に作成してもらうことをおすすめします。
相続税の納税は、自分で納付書を作成して、原則として金融機関や税務署の窓口で現金一括納税をします。
詳しくは「相続税申告は自分でできる!手順や必要書類を税理士が解説」や「相続税の申告期限・納税の期限は10ヵ月!間に合わない時の対処法も解説」をご覧ください。
8.【1年以内】遺留分侵害額の請求
相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときと期限が定められているのは、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の申立てです。
遺留分とは、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人に認められた、遺産を最低限相続できる割合のことです(民法第1042条)。
そして遺留分侵害額請求とは、自己の遺留分を侵害されている法定相続人が、侵害している人に対して、その遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度のことです(民法第1046条)。

遺留分侵害額請求は裁判所などに届け出るのではなく、遺産を多く取得した相続人や受遺者に対して内容証明郵便などで請求の意思を伝えます。
相手方が請求に応じないなど、当事者同士で解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てて解決を図ります。
この家庭裁判所に遺留分侵害額請求の申立てができる期限は、原則として相続開始から1年以内となります(死亡から10年経過後に請求権は時効を迎えます)。
なお、遺留分侵害額を請求する権利は必ず行使しなければならないわけではなく、故人の意思を尊重して遺留分を放棄することもできます。故人が死亡した後で遺留分を放棄する場合は、特に手続きは必要ありません。
遺留分侵害額請求について、詳しくは「遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説」をご覧ください。
9.【2年以内】年金や健康保険から支払われる金銭の申請・請求
相続開始から2年以内と期限が定められているのは、年金や健康保険から支払われる、以下のような金銭や給付金の申請・請求です。
条件に当てはまる場合は、早めに申請・請求手続きをしましょう。
9-1.葬祭費・埋葬料などの請求
葬祭費・埋葬料とは、被相続人が加入していた健康保険から支給される給付金のことです。
加入していた健康保険制度ごとの給付金の種類は以下のとおりです。

請求手続きの期限は死亡日または葬儀日から2年以内ですが、健康保険の資格喪失手続きや保険証の返却のときにあわせて手続きをしておくとよいでしょう。
詳しくは「埋葬料の申請方法│給付額や葬祭費との違いもわかりやすく解説」をご覧ください。
9-2.高額療養費の申請
高額医療費は死亡のあとでも申請できますが、期限は診療月の翌月から2年以内とされています。
被相続人が加入していた保険制度ごとの申請先は以下のとおりですので、健康保険の資格喪失手続きをする際に同時に申請しておきましょう。
| 申請先 | |
|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村役場 |
| 後期高齢者医療制度 | 市区町村役場 |
| 健康保険(被用者保険) | 健保組合 |
年齢・所得・受診の状況によって、基準となる医療費の限度額は異なります。
詳しくは、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。
9-3.死亡一時金の請求手続き
死亡一時金とは、被相続人が国民年金の第1号被保険者(主に自営業者)であり、以下の要件を満たしていれば受け取ることができる給付金のことです。
- 国民年金保険料を3年分以上納付している
- 老齢基礎年金や障害基礎年金は未受給
死亡一時金を請求するためには、死亡日の翌日から2年以内に市区町村役場または年金事務所で手続きをします。
死亡一時金の金額は、故人が保険料を納めていた期間に応じて12万円~32万円の範囲で定められています。
故人の妻が寡婦年金を請求できる場合は、寡婦年金と死亡一時金のどちらか一方を選択します。
死亡一時金について、詳しくは「死亡一時金とは誰が受け取れるお金?期限、金額、併給の条件など」をご覧ください。
10.【3年以内】相続登記や死亡保険金の請求
相続開始から3年以内と期限が定められているのは、相続等で取得した不動産の相続登記や、死亡保険金の請求です。
被相続人名義の不動産(土地や建物)を取得した方や、死亡保険金の受取人になっている方は、必ず期限までに手続きを行いましょう。
10-1.相続登記(相続不動産の所有権移転登記)
相続登記とは、被相続人が保有していた不動産(土地や建物)を相続や遺贈で取得した場合、その不動産の名義を相続人や受遺者に変更する手続きのことです。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、「自己のために相続が開始したことを知り」なおかつ「その不動産の所有権の取得を知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなくてはなりません。
なお、施行日前に発生した相続で取得した不動産も、相続登記の義務化の対象となりますので、令和9年3月31日までに申請手続きが必要となります。

相続登記は法務局に届け出て手続きをしますが、さまざまな必要書類の提出を求められます。
相続登記が必要な方は、専門家である司法書士に代行申請を依頼されることをおすすめします。
詳しくは「【相続登記】必要書類を自分で収集・手続きする方法を解説!」をご覧ください。
10-2.死亡保険金の請求
被相続人が生命保険契約の被保険者であった場合は、契約上の保険金受取人に死亡保険金が支払われます。
死亡保険金を請求できる期限は死亡から3年以内ですが、生活に必要なお金を得るためにも、できるだけ早く請求しましょう。
死亡保険金の請求手続きでは、保険証券や死亡診断書のコピーなど必要書類を保険会社に提出します。
なお、死亡保険金は受取人の固有財産であり、遺産相続で分け合う対象ではありません。請求手続きも単独ででき、他の相続人の同意は不要です。
詳しくは「死亡保険金の請求手続きについて」をご覧ください。
11.【5年以内】未支給年金や遺族年金などの請求
相続開始から5年以内と期限が定められているのは、未支給年金や遺族年金など、年金に係る請求手続きです。
これらの請求手続きの期限は、相続開始から5年以内ですが、条件に当てはまる場合は早めに請求しましょう。
11-1.未支給年金の請求
未支給年金とは、相続開始後にまだ支払われていない年金のことです。
国民年金や厚生年金など公的年金をもらっていた人が死亡した場合は、死亡した月の分まで年金をもらう権利があります。
しかし、年金は翌月以降に支払われるため、死亡の直後ではまだ支給されていない未支給年金が必ず発生します。

未支給年金の請求ができるのは、被相続人と同一生計であった遺族です。
死亡日の翌日から5年以内に、年金事務所または街角の年金相談センターに未支給年金・未支払給付金請求書を提出します。
請求期限は5年以内ですが、年金の受給を止める手続きと同時に行うとよいでしょう。
詳しくは「死亡後の年金のほか遺族がもらえるお金と必要な手続き-司法書士が回答」をご覧ください。
11-2.遺族年金の請求
遺族年金とは、家族の生計を維持していた人が死亡したとき、遺族が受給できる年金のことです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、条件によってどちらか一方または両方をもらうことができます。
遺族年金の請求手続きは、死亡日の翌日から5年以内に行う必要があります。
遺族年金がもらえる条件や手続きについて、詳しくは「遺族年金とは?誰がいくらもらえる?条件・手続き方法も解説」をご覧ください。
11-3.寡婦年金の請求
国民年金の第1号被保険者(主に自営業者)である夫が死亡して、妻が遺族基礎年金をもらえない場合は、60歳から65歳になるまでの間に寡婦年金をもらうことができます。
ただし、死亡した夫が国民年金保険料を10年分以上(免除期間も含む)納めていたことや、婚姻関係が10年以上続いていたなどの要件があります。
寡婦年金の請求手続きは、死亡日の翌日から5年以内に、死亡した人の住所の市区町村役場または年金事務所で行う必要があります。
寡婦年金の金額は、夫の死亡までの第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3です。
なお、寡婦年金は死亡一時金とどちらか一方の選択になります。死亡一時金の請求期限は死亡から2年以内であるため、それまでにどちらをもらうか決める必要があります。
12.【5年10ヶ月以内】相続税の更正の請求
相続開始から5年10ヶ月以内と期限が定められているのは、相続税の更正の請求です。
相続税の更正の請求とは、すでに行った相続税申告において、本来よりも相続税を多く申告・納付した場合に、過払いした相続税の還付を求める手続きのことです。
期限を過ぎると更正の請求ができなくなり、相続税を過大納付したままとなってしまいます。
相続税を多く申告・納付したことに気付いたら、相続税に強い税理士に相談をしましょう。
詳しくは、「相続税の更正の請求はいつまで?必要書類・手続き方法も解説」をご覧ください。
13.遺産相続の手続きが期限を過ぎた場合のデメリット
遺産相続に係る手続きが期限までに終わらない場合、罰則を課せられたり手続きが複雑になったりします。
この章では、代表的な相続手続きの期限を過ぎた場合のデメリットについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
13-1.相続放棄の申述が期限を過ぎた場合
相続放棄の申述期限までに管轄の家庭裁判所に申述をしないと、単純承認したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も相続することとなってしまいます。

相続開始から3ヶ月を過ぎても、例外的に相続放棄が認められることもあります。
ただし、期限を過ぎてからの相続放棄は、申述書に期限を過ぎた理由を記載した「上申書」の添付を求められます。
通常の相続放棄の申述手続きよりも複雑になるため、弁護士に依頼することを勧めます。
詳しくは、「相続放棄の期間は3ヶ月!いつから数える?手続きと期限切れの対処法」をご覧ください。
13-2.遺産分割が相続税の申告期限までに終わらない場合
相続税の申告義務があるにも関わらず、遺産分割協議が終わらずに申告期限に間に合わない場合は、未分割申告をしなくてはなりません。
未分割申告とは、法定相続分で分割したと仮定して相続税の申告・納付を行い、その後3年以内に遺産分割をして修正申告を行うことです。
相続税の申告期限を過ぎると、申告要件が設けられている相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用できません。
しかし未分割申告をすれば、修正申告の際にこれらの税額控除や特例を適用することができます。

未分割申告をする際には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付しなくてはなりません。そして分割完了から4ヶ月以内に更正の請求をすることで、納め過ぎた相続税の還付を受けられます。
手続きが非常に複雑になりますので、必ず相続税に強い税理士に依頼をしましょう。
詳しくは「相続税申告期限に分割が間に合わない時は未分割申告!【動画付きで解説】」をご覧ください。
13-3.相続税の申告・納付の期限を過ぎた場合
相続税の申告義務があるにも関わらず、相続税の申告・納付を期限までしなかった場合は、加算税や延滞税という二重のペナルティが課せられます。

加算税には「無申告加算税」と「重加算税」があり、重加算税は税務署の調査によって、申告をしなかった理由ごとに適用される種類が変わります。
本来であれば納めなくて良い税金を納めることとなりますので、相続税の申告・納付期限は必ず守りましょう。
詳しくは、「相続税の申告期限を過ぎたらどうなる?ペナルティ・デメリット・対処法を解説」をご覧ください。
13-4.相続登記の申請が期限までに終わらない場合
相続や遺贈で不動産を取得したにもかかわらず、正当な理由なく相続登記の申請を期限までにしなかった場合、10万円以下の過料に課せられます。
この他にも、相続登記をしないで放置すると、以下のようなデメリットやリスクもあります。
- 相続不動産を売却できない
- 相続人の数が増えて権利関係が複雑化する
- 管理責任や義務を押し付け合うトラブルが発生するリスクあり
- 固定資産税・都市計画税が高額になる可能性あり
相続登記をしないと思わぬトラブルに発展することもありますので、期限までに必ず申請手続きを行いましょう。
詳しくは「相続登記しないとどうなる?放置する8つのデメリットと申請手続きの流れ」でも解説しています。
14.遺産相続手続きが楽になる!生前から準備を始めよう
ここまでご紹介したように、遺産相続では数えきれないほどの手続きを、定められた期限までに行う必要があります。
残された家族が相続手続きをスムーズに進めることができるように、生前に以下のような準備をしておくことを勧めます。
生前整理や終活について、詳しくは「今から始める生前整理 │メリットやデメリット・進め方・業者を解説」や「終活はいつから始める?平均年齢や年代別の注意点を解説」をご覧ください。
14-1.エンディングノート(終活ノート)を作成しておく
エンディングノートとは、自分が死亡した後に、家族や関係者に必要な情報や希望を伝えることができるノートのことです(別名:終活ノート)。
エンディングノートには、遺産相続に係ることはもちろん、加入しているサービスの詳細や、ログインパスワード・ID・暗証番号などを書き込むことができます。
エンディングノートに法的な効力はありませんが、必要な情報が記入されているだけでも遺族の負担を大きく減らすことができます。
エンディングノートについて、詳しくは「エンディングノートとは?作成するメリット・効力│無料おすすめも紹介」をご覧ください。
14-2.遺言書を作成しておく
遺言書とは、自分の遺産の分割方法・遺贈・子の認知等について指示ができる法的な書面です。
生前に遺言書を書いておけば、遺産相続は原則として遺言内容に従いますので、相続人間のトラブルを回避することに繋がります。
遺言書は主に次の3つの種類に分かれますが、中でもおすすめなのは公正証書遺言です。

公正証書遺言であれば、様式の不備によって法的に無効になる心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの恐れもありません。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きをする必要もありませんので、遺族がスムーズに遺産相続手続きを行うことができます。
公正証書遺言について、詳しくは「公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説」をご覧ください。
14-3.家族信託を設定する
家族信託とは、主に高齢の親の財産管理や相続対策を目的に財産を信託するしくみです。
生前に財産をどのようにしたいかを考えてそれを実現するしくみを作っておけば、遺族の相続手続きの手間が軽減されます。

ただし、家族信託を個人だけで設定することは極めて困難で、専門家のサポートが欠かせません。
依頼する専門家は、実務経験などを踏まえて慎重に選ぶようにしましょう。
家族信託について、詳しくは「家族信託は必要?問題点はある?活用事例・仕組みも解説」をご覧ください。
15.まとめ
遺産相続に係る手続きの中には、期限が定められているものも多くあります。
計画的に進めないと期限に間に合わず、罰則が課せられたり手続きが複雑になったりするというデメリットもあります。
専門家に代行サポートを依頼して、期限内に遺産相続手続きをスムーズに終わらせましょう。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。
そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続手続き編







































