二次相続とは?【税理士監修】一次相続との違い・相続税対策のポイントを解説
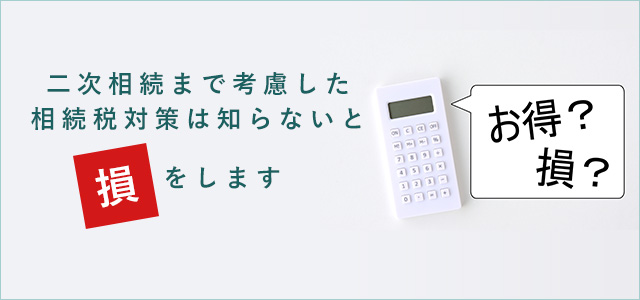
二次相続とは、一次相続の被相続人(亡くなった人)の配偶者の相続のことを指します。
一次相続では、残された配偶者の生活を保障するために、配偶者が遺産の多くを相続するケースが散見されます。
しかし、一次相続の段階で二次相続を見据えた遺産分割をしないと、一次相続と二次相続の両方の法定相続人となる、子どもの相続税の負担が重くなってしまうので注意が必要です。
本稿では、二次相続の基礎知識や問題点はもちろん、一次相続の段階でできる相続税対策や生前対策について、相続専門の税理士が解説します。
この記事の目次 [表示]
1.二次相続とは
二次相続とは、一次相続後に発生する被相続人の配偶者の相続のことです。

例えば、父親・母親・長男・次男という4人家族において、最初に父親が亡くなり、その次に母親(配偶者)が亡くなったとします。
この父親の相続を「一次相続」といい、その後に発生した母親の相続を「二次相続」といいます。
1-1.一次相続と二次相続の違いは何?
一次相続と二次相続の違いは、法定相続人に「配偶者」が含まれるか否かです。
先ほどのシミュレーションモデルにおいて、一次相続(父親の相続)が発生した場合、法定相続人となるのは「配偶者(母親)+子ども2人」です。
しかし、二次相続(母親の相続)において法定相続人となるのは、「子どものみ」となります。
法定相続人に配偶者が含まれているか否かは、相続にさまざまな影響を及ぼします。
しかし、一次相続が発生した時点で対策をしておけば、二次相続における様々な問題を回避することができます。
2.二次相続の問題点は相続税!子どもの税負担が重くなる6つの理由
一次相続では配偶者の生活を維持するために、遺産の大部分を配偶者が相続するケースが多くみられます。
しかし、一次相続で配偶者が多額の遺産を相続すると、一次相続と二次相続の両方の法定相続人となる子どもの、相続税の負担が重くなるリスクがあります。
二次相続において子どもの相続税の負担が大きくなる理由は、以下の通りです。
それでは上記6つの理由について、詳細を確認していきましょう。
2-1.二次相続では相続税の基礎控除額が600万円減る
二次相続では一次相続よりも法定相続人の数が1人減るため、相続税の基礎控除額が実質600万円減ることとなります。
相続税の基礎控除額とは、すべての相続において適用できる控除のことで、相続税が課税されるか否かのボーダーラインとも呼ばれています。
相続税の基礎控除額の計算方法は、【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】です。

相続税は「正味の遺産総額」から「基礎控除」を差し引いた後の、課税遺産総額に対して課税される税金です。
つまり、二次相続において相続人が一人減ると、相続税の基礎控除額が600万円少なくなり、相続税の課税対象額が600万円増えてしまいます。
相続税の基礎控除について、詳しくは「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。
2-2.二次相続では死亡保険金の非課税枠が500万円減る
二次相続では一次相続よりも法定相続人の数が1人減るため、死亡保険金の非課税額が実質500万円減ることとなります。
相続税が課税される契約形態の生命保険契約から支払われる死亡保険金には、相続税が課税されない非課税枠があり、非課税限度額は【法定相続人の数×500万円】で計算します。

二次相続において相続人が一人減ると、死亡保険金の非課税枠が500万円少なくなり、相続税の課税対象額が500万円増えてしまいます。
死亡保険金の非課税枠について、詳しくは「生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。
2-3.二次相続では配偶者自身の財産も加算される
二次相続では、一次相続で配偶者が取得した相続財産に、配偶者自身の財産も加算されます。
つまり、一次相続で配偶者が全財産を取得してしまった場合、二次相続において相続税の課税対象額が増えてしまうということです。
なお、一次相続の時に相続税を納めている場合は、相続税の申告期限から10年以内に二次相続が発生すれば、同じ財産に対して課税される相続税を軽減する効果がある、相次相続控除という税額控除を適用できます(詳細は後述します)。
2-4.相続税の課税対象が増えれば税率もアップする
これまでにご紹介した通り、二次相続では相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠が減る上に、一次相続で配偶者が取得した財産と配偶者自身の財産が合算されます。
つまり、一次相続よりも二次相続の相続税の課税対象の方が、多くなってしまうということです。
相続税の税率は累進課税のため、相続税の課税対象が増えれば増えるほど、適用される税率も高くなります。

相続税の税率は、基礎控除額を差し引いた後の課税遺産総額を、一旦法定相続分で按分した後の価額に応じて適用されます。
課税対象額が増える上に、法定相続人が減って法定相続分が増えるため、適用される税率がアップするリスクがあります。
相続税の税率について、詳しくは「相続税の税率(割合)は10~55%!【税率表付】税額の計算方法も解説」をご覧ください。
2-5.二次相続では相続税の配偶者控除が適用できない
二次相続は一次相続の法定相続人であった配偶者の相続であるため、相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減の特例)が適用できません。
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち課税対象となる額が「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多い方まで、相続税がかからないという税額控除のことです。

相続税の配偶者控除は、相続税の節税効果が高い税額控除ですので、一次相続において配偶者に多くの遺産を相続させれば、相続税を0円にできるかもしれません。
しかし、二次相続は配偶者の相続となるため、この配偶者控除は適用できず、一次相続に比べて相続税が高くなる傾向にあります。
相続税の配偶者控除について、詳しくは「【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。
2-6.二次相続では被相続人の自宅に対する小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなる
二次相続では、被相続人の自宅に対する小規模宅地等の特例の適用要件を満たすのが厳しくなります。
結果として、宅地等の評価額を減額することができず、相続税の課税対象額が増える可能性が高くなります。
被相続人の自宅に対する小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住の用に供されていた宅地の評価額を、最大80%まで減額できる特例のことです。

※国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」を加工して作成
配偶者の二次相続において小規模宅地等の特例を適用するためには、その宅地等を取得する子どもが被相続人と同居していたなどの条件を満たす必要があります。
適用要件を満たさない場合には、小規模宅地等の特例による宅地等の評価額の減額ができず、相続税の課税対象額が高くなってしまいます。
詳しくは「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」をご覧ください。
3.二次相続の相続税計算シミュレーション!分割方法の違いによる税額を比較
二次相続において子どもの相続税の負担を軽減するためには、一次相続でどれだけの遺産を配偶者が相続するかがポイントです。
この章では、以下のシミュレーションモデルにおいて、一次相続の遺産分割方法の違いによる、子どもの相続税の負担額を比較します。

前提として、財産(遺産総額)は基礎控除などを差し引いた後の価額とし、配偶者控除以外の税額控除や特例は考慮しません。
詳細な相続税の計算方法は割愛します。概算の相続税額を知りたい方は、「「相続税の速算表」で相続税を簡単に計算する方法を税理士が解説」や「相続税計算シミュレーション」をご覧ください。
3-1.一次相続で法定相続分のとおりに遺産分割した場合
今回のシミュレーションモデルにおいて、一次相続で法定相続分による遺産分割をした場合、相続税額は以下の通りとなります。

そして二次相続では、一次相続において母親が取得した1億円を、子2人が法定相続分で相続します。

このシミュレーションモデルにおいて、一次相続と二次相続において子どもが負担する相続税の総額は2,120万円です。
3-2.一次相続で配偶者控除を最大限適用して遺産分割した場合
パターン①と同じ条件の家族において、一次相続(父親の相続)で配偶者控除を最大限適用(配偶者が1億6,000万円取得)した場合、相続税額は以下の通りとなります。

そして二次相続では、一次相続において母親が取得した1億6,000万円を、子2人が法定相続分で相続します。

このシミュレーションモデルにおいて、一次相続と二次相続において子どもが負担する相続税の総額は2,680万円です。
3-3.一次相続の遺産分割方法の違いよる相続税額を比較
一次相続において「①法定相続分のとおりに遺産分割した場合」と「②配偶者控除を最大限適用して遺産分割した場合」の、子どもが負担する相続税額を比較してみましょう。

一次相続において法定相続分で遺産分割した方が、配偶者控除を最大限適用した場合よりも、一次相続と二次相続で子どもが負担する相続税が560万円低くなります。
一次相続の相続税が少なくなっても、二次相続の相続税と合算するとかえって多くなる場合もありますので注意が必要です。
4.二次相続の相続税対策!一次相続における遺産分割のポイント
二次相続の相続税は、一次相続で配偶者がどれだけの遺産を相続するかによって変わります。
具体的には、一次相続において以下のポイントを踏まえた遺産分割をすれば、一次相続と二次相続の両方の法定相続人となる子どもの相続税の負担を軽減できます。
この章では、どうしてこれらの方法が二次相続対策に繋がるのかを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
4-1.収益物件・値上がりする資産は子が相続する
一次相続における遺産分割では、賃貸アパートなどの収益物件や、株式などの値上がりが予想される資産は、子どもに相続させるのがおすすめです。
一次相続で配偶者が収益物件を相続すると、物件そのものの金額は変わらないとしても、家賃収入で配偶者の財産が増える可能性があります。
また、値上がりが見込まれる財産を相続した場合、二次相続における評価額が、一次相続時よりも上がっていることが想定されます。
配偶者の財産の増加を抑えることで、二次相続の相続税の課税対象額を下げることに繋がります。
4-2.子どもが小規模宅地等の特例を適用して宅地を相続する
一次相続における遺産分割では、子どもが小規模宅地等の特例を適用して宅地等を相続するのがおすすめです。
配偶者は被相続人の所有する居宅の宅地について、小規模宅地等の特例の適用要件を満たしやすいですが、配偶者は配偶者控除を適用できるため、2つの特例を配偶者に適用させるのは勿体ないです。
一次相続において子どもが小規模宅地等の特例を適用して宅地等を取得すれば、配偶者が相続する遺産総額が減り、結果として一次、二次の相続において子どもが負担する相続税も少なくなります。
ただし、子が小規模宅地等の特例を適用するためには、亡くなった親と同居していたなどの要件や家なき子特例の要件を満たす必要があります。
詳しくは「『家なき子特例』は親と同居しなくても小規模宅地等の特例が使える制度」をご覧ください。
4-3.配偶者は配偶者居住権を取得する
一次相続における遺産分割では、配偶者は自宅の配偶者居住権を取得し、子が自宅の所有権を取得するのがおすすめです。
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が自宅を相続しなくても、引き続き居住できるという権利のことです。
具体的には、一次相続において相続財産である自宅不動産について「住む権利(居住権)」と「その他の権利(所有権)」に分離し、配偶者が居住権(配偶者居住権)を相続して、子が所有権を相続します。なお、居住用建物ついて、配偶者居住権の登記を行うことで、第三者に対しても居住権を主張できるようになり、所有者が変わっても安心して住み続けることができます。
配偶者居住権を保有する配偶者の相続(二次相続)が発生した場合、その自宅不動産は完全に所有者である子のものになります。
配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅するため、所有者である子には価値(居住権)の移転が発生しますが、ここに相続税は課税されません。
つまり、配偶者に配偶者居住権以外の財産がなければ、二次相続において相続税は発生しません。
配偶者居住権について、詳しくは「配偶者居住権とは?活用するべきケースと要件・注意点も解説」をご覧ください。
5.二次相続対策!一次相続の遺産分割後でもできる相続税対策
二次相続の相続税対策は、一次相続における遺産分割方法に工夫をするだけではありません。
一次相続の遺産分割が終わった後でも、以下のような二次相続対策をすれば、一次相続と二次相続の両方の法定相続人となる子どもの相続税の負担を軽減できます。
それでは詳細を確認していきましょう。
5-1.早期に生前贈与を始める
二次相続の被相続人となる配偶者が、早期に生前贈与を始めれば、二次相続で相続税の課税対象となる財産を、計画的に減らすことができます。
以下の方法であれば、贈与税0円で財産を次世代に移転できます。
| 贈与の種類 | 非課税枠 |
|---|---|
| 暦年課税による贈与 | 年間110万円 |
| 相続時精算課税を適用した贈与 | 年間110万円+累計2,500万円まで |
| 住宅取得等資金贈与 | 最大1,000万円まで |
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円まで |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円まで |
暦年課税の基礎控除額(年間110万円以下)を活用した暦年贈与は、気軽に始められる生前贈与の方法です。
ただし、相続開始前3年~7年以内の法定相続人への贈与財産は、相続財産に持ち戻しをして相続税が課税されますのでご注意ください。
孫への暦年贈与を検討したり、相続時精算課税の基礎控除(年間110万円)を活用したりして、相続税の課税対象にならないよう工夫されると良いでしょう。
詳しくは、「贈与税がかからない方法は?親子や夫婦は?非課税になるケースや注意点を解説」をご覧ください。
5-2.生命保険に加入して非課税枠を活用する
二次相続の被相続人となる配偶者が、自己を被保険者とする生命保険に加入して、子どもを受取人に指定すれば、二次相続の相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
この記事の前半でもご紹介しましたが、生命保険の死亡保険金には非課税限度額があるため、現金を生命保険に持ち替えるだけで、相続税の課税対象額が少なくなります。

また、死亡保険金は受取人の固有財産であるため、遺産分割の対象にはなりません。
法定相続人どうしのトラブルが予想される場合でも、生命保険を活用すれば、確実に財産を継がせることができます。
詳しくは、「節税対策として生命保険が優れている理由とは?相続税金対策に注意すべきこと」をご覧ください。
5-3.相次相続控除が適用できないか検討する
二次相続が発生した場合、相次相続控除が適用できないか検討しましょう。
相次相続控除とは、一次相続の申告期限から10年以内に二次相続が発生した場合、二次相続の相続税から一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです。

二次相続の相続税の申告で相次相続控除を適用するには、二次相続の被相続人が一次相続で相続税を納めていなければなりません。
一次相続では多くの場合で配偶者控除を適用するため、二次相続で相次相続控除を適用できるケースは少ないかもしれません。
しかし、夫婦が連続して亡くなった場合に、一次相続で配偶者の税額軽減を適用しないで、二次相続で相次相続控除を適用する方が節税になることもあります。
相次相続控除について、詳しくは「相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説」をご覧ください。
6.二次相続における4つの注意点
二次相続においては、二次相続特有の注意ポイントがあります。
6-1.二次相続は子ども同士の相続トラブルが発生しやすい
二次相続は子ども同士で遺産相続の話し合いをすることになるため、相続トラブルが起こりやすくなります。
間を取り持つはずの親が亡くなっているため、感情的な対立が長期化する懸念もあります。
特に遺産のほとんどを自宅不動産が占める場合などは、遺産の分割方法でもめやすいため、特に注意が必要です。
二次相続の被相続人となる配偶者が、遺言書の作成をしておけば、子ども同士の相続トラブルを回避することに繋がります。
詳しくは、「遺言書が必要な人リスト~なぜ必要?残すべき理由とは?~」をご覧ください。
6-2.二次相続が発生したタイミングによって相続放棄には制限あり
二次相続が発生したタイミングによって、相続放棄の選択には制限がありますので注意が必要です。
一次相続の発生から3ヶ月以内(熟慮期間中)に二次相続が発生することを、再転相続と呼びます。

例えば、2月1日に父親が亡くなり、その法定相続人である母親が承認や放棄をしないまま、熟慮期間中である4月1日に亡くなったとしましょう。
この場合、二次相続の法定相続人である子どもは、再転相続人として、一次相続の法定相続分の相続も承認・放棄する権利を取得することとなります。
しかし、一次相続(父親の相続)を単純承認した場合、二次相続(母親の相続)のみ相続放棄をすることはできませんので注意が必要です。
詳しくは「再転相続とは?相続放棄には制限がある!数次相続との違いまで解説」をご覧ください。
6-3.一次相続が未分割の状態で二次相続が発生した場合は相続手続きが複雑に
一次相続が未分割の状態で二次相続が発生することを、数次相続と呼びます。
具体的には、父親が亡くなってその法定相続人である母親が単純承認をしたものの、遺産分割協議が成立する前に二次相続が発生した場合が該当します。

数次相続が発生した場合、一次相続と二次相続の相続手続きを同時に行うこととなります。
そのため、準備すべき必要書類が通常と異なりますし、相続税申告や税額の計算も通常とは考え方が違いますので注意点が必要です。
詳しくは、「数次相続とは?相続手続き・相続税申告・相続登記における注意点」をご覧ください。
6-4.二次相続では障害者控除や未成年者控除の控除額が少なくなる
一次相続において相続税の障害者控除や未成年者控除を適用した場合、二次相続における控除額が少なくなる可能性があるので注意が必要です。
例えば、障害者控除の控除額は、以下のいずれか少ない方の金額が適用されます。

つまり、一次相続においてすでに控除額を使っている場合、残額が適用されるため、一次相続よりも控除額が少なくなってしまうのです。
二次相続においてこれらの税額控除を適用する場合は、相続税の計算方法が複雑になりますので、必ず専門家である税理士に相談をしましょう。
詳しくは、「【相続税の障害者控除】控除額の計算方法・要件をプロが解説」や「相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説」をご覧ください。
7.二次相続を見据えた相続税対策は専門家に相談を
二次相続の相続税対策として、一次相続の段階で二次相続を見据えた遺産分割をされるのがおすすめです。
また、一次相続の遺産分割後も、生前贈与や生命保険への加入などをすれば、二次相続の相続税対策に繋がります。
二次相続の相続税対策を行うのであれば、まずは相続税に強い税理士に相談をして最適なアドバイスをもらいましょう。
7-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。
一次相続の段階で二次相続を見越した遺産分割はもちろん、生前贈与などの相続税対策についても適切なアドバイスをさせていただきます。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策は「今」できることから始められます
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続対策編






































