兄弟姉妹に遺留分なし!その理由とは?兄弟姉妹が遺産を取得する方法
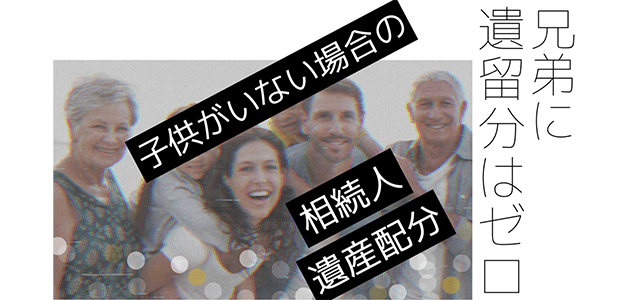
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められた、被相続人の遺産を最低限取得できる割合のことです。
兄弟姉妹は遺留分なしですので、遺言書に名前が記載されていなければ、遺産を相続することはできません。遺留分侵害額請求もできません。
この記事では、遺留分と兄弟姉妹が係る遺産相続における、注意点についてまとめました。
遺言書に名前が記載されていない兄弟姉妹が遺産を取得する方法や、被相続人が行っておくべき生前対策についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.兄弟姉妹に遺留分なし!遺留分侵害額請求もできない
遺留分とは、被相続人の遺言に左右されることなく、一定の範囲の相続人が最低限の遺産を相続できる割合のことです。
民法第1042条では、遺留分が認められていているのは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・父母)のみとされています。兄弟姉妹に遺留分は認められていません。

遺留分について、詳しくは「遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで」をご覧ください。
1-1.兄弟姉妹は遺留分侵害額請求できない
兄弟姉妹に遺留分はないため、遺言書に名前が記載されていないことよって遺産を取得できなくても、遺留分侵害額請求はできません。
遺留分侵害額請求とは、自己の遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している人に対して、その遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度のことです(旧:遺留分減殺請求)。

例えば、相続人が配偶者と兄弟であり、被相続人の遺産が1億円であるとします。
このケースにおいて、被相続人が遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と指定した場合、配偶者は1億円を相続しますが、兄弟は遺産を相続できません。
また、兄弟に遺留分はないため、配偶者に対して遺留分侵害額請求を行うことができません。
詳しくは「遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説」をご覧ください。
2.兄弟姉妹に遺留分がない3つの理由
被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていないのには、いくつか理由があります。
2-1.兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠い
兄弟姉妹に遺留分がない1つ目の理由として挙げられるのは、被相続人との血縁関係が遠いことです。
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人と血縁関係はあるものの、親子関係ではない親族であるため「傍系血族」と呼ばれます。
後ほど解説しますが、傍系血族である兄弟姉妹の相続順位は第三順位です。
兄弟姉妹は被相続人との血縁関係が遠いのが、遺留分が認められない一番の理由といわれています。
詳しくは「傍系親族とは?直系との違い・尊属・卑属まで家系図で解説」もあわせてご覧ください。
2-2.兄弟姉妹以外の相続人の生活を保証するため
兄弟姉妹に遺留分がない2つ目の理由として挙げられるのは、兄弟姉妹以外の相続人の生活を保証するためです。
被相続人の配偶者・子・父母は、被相続人と生計を一にしていることが多く、遺産を相続できなければ生活に困窮することが考えられます。
しかし、兄弟姉妹は被相続人と生計を別にしているケースが多く、被相続人が死亡しても、生活が大きく変化することは少ないと思われます。
仮に兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、遺留分侵害額請求ができてしまうため、配偶者の生活が困窮することも考えられます。
2-3.兄弟姉妹には代襲相続があるから
兄弟姉妹に遺留分がない3つ目の理由として、兄弟姉妹には代襲相続が認められていることも挙げられます。
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続人が死亡した場合等に、その相続人の子(孫や甥姪)が代襲相続人として、代わりに遺産相続することを指します。
仮に兄弟姉妹の遺留分を認めた場合、代襲相続人である甥姪の遺留分も認めることとなります。
つまり、遺言書を作成して配偶者に全財産を相続させようとしても、血縁関係の遠い甥姪に、遺言書の効力を覆される可能性もあるということです。
このような事情から、兄弟姉妹には遺留分が認められていないといわれています。
代襲相続について、詳しくは「【図解】代襲相続とは?孫や甥・姪が代襲相続人になる場合や相続割合を解説」をご覧ください。
3.遺留分なしの兄弟姉妹が相続人になる2つのケース
相続人とは、民法において被相続人の遺産を相続する権利が認められた、一定の範囲の親族のことです。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は、以下のように優先順位が定められています。

被相続人に子がいない場合は、第二順位の父母が相続人となります。
父母及び祖父母もすでに他界している場合は、第三順位の兄弟姉妹に法定相続人として遺産相続する権利が認められています(兄弟姉妹がすでに他界している場合は甥姪が代襲相続)。
この章では、兄弟姉妹が相続人になる、具体的な2つのケースについてご紹介します。
相続人について、詳しくは「法定相続人の範囲を図解で解説!相続割合・複雑なケースも紹介」をご覧ください。
3-1.ケース①兄弟姉妹と配偶者が相続人になる
1つ目のケースは、兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になるパターンです。
配偶者とは、法律上婚姻していると認められた配偶者を指します。内縁の妻のような事実婚のパートナーの立場では、法律上の配偶者とされません。
そして被相続人に子供(孫)がおらず、父母(祖父母)もすでに他界している場合は、第三順位の兄弟姉妹も相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、相続分は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。
そして配偶者の遺留分は1/2、兄弟姉妹の遺留分はなしとして扱います。
「子なし夫婦の遺産相続はどうなる?起こりやすいトラブルや生前対策も解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。
3-2.ケース②兄弟姉妹のみが相続人になる(配偶者なし)
2つ目のケースは、兄弟姉妹のみが相続人になるパターンです。
被相続人に配偶者がいない場合、つまり被相続人が未婚である場合、離婚をした場合、配偶者がすでに他界した場合は、他の相続人のみで遺産を相続します。
被相続人に子供(孫)がおらず、父母(祖父母)もすでに他界している場合のみ、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹のみが相続人になる場合、法定相続分は兄弟姉妹の人数で均等に按分することとなります。
例えば、兄弟姉妹が2人であれば法定相続分は1/2ずつ、3人であれば法定相続分は1/3ずつです。
なお、兄弟姉妹のみの相続であっても、兄弟姉妹に遺留分は認められません。
4.遺言書に名前なし…遺留分なしの兄弟姉妹が遺産を取得する方法
兄弟姉妹に遺留分が認められていないことが問題となるのは、被相続人が生前に遺言書を作成していたものの、相続人である兄弟姉妹の名前が遺言書に記載されていない場合です。
遺言書に名前が記載されてなければ、兄弟姉妹は遺産を相続することができません。遺留分も認められていないため、遺遺留分侵害額請求もできません。
しかしこのような場合、遺留分のない兄弟姉妹でも、被相続人の遺産を取得できる可能性は残されています。
4-1.遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
遺言書が残されていても、相続人及び受遺者全員の同意があれば、遺言内容と異なる遺産分割が可能です。
つまり、兄弟姉妹の名前が遺言書に記載されてなくても、遺産分割協議に切り替えることができれば、兄弟姉妹も遺産を相続することが可能となります。

なお、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意も得なければなりません。
遺留分のない兄弟姉妹が、利害関係者全員の同意を得るのは難しいので、必ず弁護士にサポートを依頼しましょう。
詳しくは「遺言書と異なる遺産分割は可能!遺産分割協議の注意点」をご覧ください。
4-2.遺言書の無効を主張する
遺言書が残されていても、遺言書の無効が認められれば、遺産分割協議や法定相続分による遺産分割が可能となります。
具体的に、遺言書の無効を主張するためには、以下のポイントを満たしている必要があります。
- 法律で定められた形式で遺言書が作成されていない
- 遺言能力なしと認められた(認知症等)
- 無理矢理書かされた遺言書である
- 遺言書が偽造や変造されている可能性がある
- 遺言内容が公序良俗違反に該当する
遺言書を無効にするためには、遺言無効確認訴訟を提起するケースがほとんどですので、必ず弁護士にサポートを依頼しましょう。
詳しくは「遺言無効確認訴訟の提起前に知っておきたいこと。費用、期間など」をご覧ください。
\\CHECK//
チェスターグループには、遺産相続を専門に取扱う弁護士事務所があります。
遺言と異なる内容で遺産分割を行う場合や、遺言無効確認訴訟のサポートを承ります。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
5.兄弟姉妹に遺産相続させたくない場合は生前対策を
兄弟姉妹が係る遺産相続の中には、全財産を配偶者に相続してほしい、ほとんど音信不通だった兄弟姉妹には相続してもらいたくない、といった考えを持つ人もいるでしょう。
また、世話になった一部の兄弟姉妹や甥姪のみに遺産を渡したい…という方もいらっしゃると思います。
このようにお考えの方は、相続トラブル回避のためにも、この章でご紹介する生前対策をされることをおすすめします。
5-1.公正証書遺言書を作成する
兄弟姉妹が係る遺産相続トラブルを回避するためにも、まずは公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言とは、遺言者と証人2名の立ち合いのもと、公証人が作成する遺言書のことです。

兄弟姉妹には遺留分がないため、「配偶者(内縁の妻や夫も含む)に全財産を相続させる」と記載すれば、その遺言内容が実現されます。
公正証書遺言は法的に無効になる可能性が低く、紛失・破棄・偽造・改ざんのリスクがないというメリットがあります。
つまり、遺留分なしの兄弟姉妹が遺言の無効を主張しても、認められる可能性は極めて低いということです。
公正証書遺言につい、詳しくは「公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説」をご覧ください。
5-2.生前贈与する
特定の人に特定の財産を取得させたいという意向があるなら、生前贈与がスムーズです。
贈与は、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)の双方の同意の元で履行される契約ですので、遺留分といった考え方はありません。
ただし、原則として年間110万円を超える贈与には、贈与税が発生するという点には注意が必要です。

税額を計算する際に考慮される基礎控除額や税率の面でも、相続税のほうが優遇されていることも考慮し、相続がよいのか生前贈与がよいのかを検討しましょう。
詳しくは「相続税対策には生前贈与を活用しよう!贈与税の6つの非課税枠って?」をご覧ください。
5-3.家族信託する
家族信託は、信託財産である不動産や預貯金などの管理・処分を家族に任せる制度で、委託者・受託者・受益者の3者によっておこなわれます。
委託者は自分が保有する財産の管理を受託者に依頼し、財産の管理をしていくなかで利益が生じた場合には、受益者がその利益を得ることになるのです。

例えば、複数の兄弟姉妹の中に、配偶者とも関係が良好で信頼できる妹が1人いるとします。
一方、配偶者は軽い認知症を患っており、今後自分で相続財産の管理をすることが難しくなっていく状況です。
このような場合に、信頼できる妹を受託者として財産管理を任せるといったケースが考えられます。
信頼できる親族がいる場合には、ぜひ家族信託も視野に入れてみましょう。
詳しくは「家族信託は必要?問題点はある?活用事例・仕組みも解説」をご覧ください。
6.遺言書を作成する際に知っておきたい4つのポイント
相続トラブルを未然に防ぐためには、生前に公正遺言証書を準備しておくことが有効です。
公正証書遺言を作成する際には、公証人が法的なアドバイスをしてくれますが、遺言内容を決めるのは遺言者本人です。
そのため、以下のような注意点を把握しておかないと、遺言書があることがトラブルの原因になることも考えられます。
6-1.誰に何を相続させるのか明白に記載する
不動産のように分割しづらい相続財産がある場合、相続割合だけでなく、誰に何を相続させるかについて明確に遺言書に記載しましょう。
例えば、相続財産は土地・建物・有価証券があり、公正証書遺言には財産内容を指定せずに「遺産の9割を配偶者に、1割を兄弟に相続させる」と記載したとします。
しかしこれでは、何をどのように9割と1割に分割するのかが指定されていないため、当事者間で話合いをしなければなりません。
もし兄弟が土地・建物・有価証券をすべて1割ずつ相続したいと申し出た場合、配偶者は遺言書を理由に拒否できません。
誰に・何を・どれだけ相続させるのかを明白に記載しておけば、無用なトラブルを避けることができます。
詳しくは「【遺言書の書き方】相続のプロが無効にならない方法を解説」をご覧ください。
6-2.遺言書に記載されていない財産の取扱いを決めておく
公正証書遺言には、必ず「遺言書に記載されていない財産の取扱い」について記載をしておきましょう。
この理由は、公正証書遺言に記載されていない財産については、法定相続人の共同財産として遺産分割協議の対象となり、通常の相続手続きが必要となるためです。

例えば、銀行口座を増やして預貯金を移した場合や、マイホームを購入して新居に引っ越した場合など、公正証書遺言を作成した後にも、公正証書遺言に記載のない相続財産が増えることが想定されます。
将来的にこのような財産があることを想定して、予備的に記載しておくとなお安心です。
詳しくは「遺言書の効力とは?有効期間や無効にしないための注意点を解説」をご覧ください。
6-3.遺言執行者を指定しておく
公正証書遺言では、遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、単独で遺産相続に係る手続きを行う強い権限を持つ人のことです。

遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が単独で相続手続きを進めることができるため、利害関係者同士の関係性によって相続手続きが難航することもありません。
指定しなくても遺言が無効になることはありませんが、実務においては遺言執行者を指定するケースがほとんどです。
詳しくは「遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説」をご覧ください。
6-4.付言事項を活用して遺言の内容に至った想いを記す
公正証書遺言には、遺産相続に係る内容のみならず、付言事項(ふげんじこう)を記載することもできます。
付言事項とは「どうしてそのような相続割合に決定したのか」といったような、遺言内容に至った想いを記載した事項のことです(法的効力はありません)。
法定相続分とは異なる割合で相続財産を分けた場合、特にその相続人を納得させる理由を遺言書に書けば、不要なトラブルを避けられる可能性があります。
予想されるトラブルを未然に防ぐためにも、付言事項を使って被相続人の立場、想いを明確に表しておくとよいでしょう。
詳しくは「遺言書の付言事項とは-記載すべき内容や書かないほうがよい文の具体例も」をご覧ください。
\\CHECK//
相続手続きを専門に取扱う行政書士法人チェスターでは、「公正証書遺言作成サポート」をご提案しております。
相続専門のチェスターに所属している税理士・弁護士・司法書士と共に、円満相続のみならず税金対策も行う公正証書遺言の作成のアドバイスが可能です。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、まずはお気軽にお問合せください。
7.兄弟姉妹が係る相続税申告の注意点
兄弟姉妹が係る相続税申告では、以下のような注意点があります。
7-1.代襲相続が発生している場合は相続人の数に注意
兄弟姉妹が係る遺産相続において代襲相続が発生した場合、相続人の数が増えることがあるので注意が必要です。
相続税を計算する際には、相続税の基礎控除を計算する必要がありますが、この計算式には法定相続人の数を算入する必要があります。

例えば、本来の相続人は、配偶者と兄の合計2人であるものの、兄は既に他界しているため、兄の子供(甥姪)3人が代襲相続人になるとします。
この場合、相続人の数は、配偶者と甥姪3人の、合計4人になるということです。
基礎控除について、詳しくは「【相続税の基礎控除】いくらまで無税?計算式は?税理士が解説」をご覧ください。
7-2.兄弟姉妹が遺産を相続しない場合も相続人としてカウントする
遺言書により兄弟姉妹(甥姪)が遺産を相続しない場合でも、相続人としてカウントします。
つまり、相続税の基礎控除は、兄弟姉妹が遺産相続しなくても変動しないということです。
例えば、相続人が配偶者と兄Aと弟Bの合計3人である場合、相続税の基礎控除は4,800万円です。
仮に遺言書によって配偶者が全財産を取得する場合でも、相続税の基礎控除は4,800万円のまま変動しません。
7-3.兄弟姉妹が遺産を相続した場合は相続税額が2割加算される
兄弟姉妹が遺産を相続した場合は、相続税の2割加算が適用されます。
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の人が遺産を取得した場合、その人の相続税額が2割加算される制度のことです(相続税法第18条)。
これは兄弟姉妹に遺留分がない理由と同じく、相続財産を受け取ることの必然性に差があるためです。
詳しくは「相続税の2割加算の対象者は?【税理士監修】計算方法をくわしく解説」をご覧ください。
\\CHECK//
税理士法人チェスターは、年間3,000件超の相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士事務所です。
兄弟姉妹や代襲相続が係る複雑な相続税申告のサポートはもちろん、1円でも相続税が節税できるよう、各種特例や控除の適用を検討させていただきます。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
8.兄弟姉妹の遺留分でトラブルが発生しそうなら専門家へ相談を
兄弟姉妹に遺留分はないため、遺言書に名前が記載されていなくても遺留分侵害額請求はできません。
そのため、兄弟姉妹に遺産相続をさせたくない場合は、公正証書遺言の作成や生前贈与などの対策をしておくと良いでしょう。
スムーズかつ的確な相続トラブル対策を行うなら、相続に強い専門家に相談をしましょう。
8-1.チェスターグループにご相談を
兄弟姉妹や遺留分に係る遺産相続について不安や疑問がある方は、チェスターグループまでご相談ください。
相続税を専門とする税理士法人チェスターをはじめ、司法書士法人チェスター・行政書士法人チェスターなどと共に、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応が可能です。

すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
【相続税申告】税理士法人チェスター
【相続登記】司法書士法人チェスター
【相続手続き】行政書士法人チェスター
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編






































