相続は認知症の相続人もできる?遺産分割や相続税申告の注意点
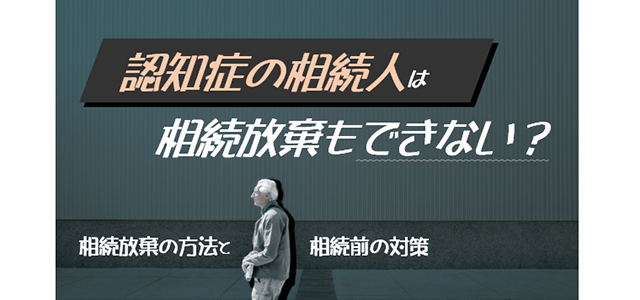
「父母が認知症だけど祖父母の財産を相続できるの?」
「認知症の相続人への財産分与はどうなるの?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論を言うと、認知症の相続人であっても遺産を相続できますが、本人に判断能力がない場合は、遺産分割協議を成立させることが難しくなります。
相続手続きが進まず、思わぬペナルティが課せられることもありますので、下記のような対応を検討しなくてはなりません。
- 成年後見制度の利用
- 法定相続分による遺産分割を検討
この記事では、認知症の相続人がいる場合の、遺産分割や相続手続きについてまとめました。
認知症の家族がいる人の生前対策についても紹介しますので、是非参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.相続人が認知症だと遺産分割協議を成立させるのが難しい
被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が2名以上いる場合は、遺産分割協議によって「誰が・何を・どれだけ・どのように相続するのか」を話し合って決めなくてはなりません。
遺産分割協議を成立させるためには、協議に参加した法定相続人全員の合意が必要です。

法定相続人の中に判断能力が低下している認知症の人が含まれる場合、遺産分割協議の内容を理解できず、意思表示ができない可能性が高いです。
しかし、認知症だからという理由で、認知症の相続人を抜いて遺産分割協議を成立させることはできません。
1-1.遺産分割協議が成立しないと相続手続きが進まない
認知症の相続人がいて遺産分割協議が成立しなければ、様々な相続手続きで提出を求められる、遺産分割協議書を作成できません。
遺産分割協議書には、法定相続人全員が記載された遺産の分割方法に合意していることを、第三者に証明する効果があります。
そのため、以下のような相続手続きをスムーズに進めることができなくなります。
- 銀行の預貯金の払い戻しや解約
- 株式等の名義変更
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 自動車の名義変更
これらの相続手続きが終わらなければ、相続財産の売却や活用はできません。
相続税の納付義務がある場合、相続財産から納税資金を準備することができないため、自己資産から相続税を支払う必要があります。
詳しくは、「遺産分割協議書とは?作成までの流れや提出が必要な相続手続きを解説」をご覧ください。
1-2.相続税の申告・納付が期限に間に合わない可能性も
認知症の相続人がいて遺産分割協議が成立させられないという理由で、相続税の申告・納付期限は延長できません。
相続税の申告・納付期限は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税の申告義務があるにも関わらず、無申告のまま放置すると加算税や延滞税が課せられてしまいますのでご注意ください。

相続税の申告期限を過ぎたら、相続税の軽減に繋がる「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」を適用できなくなります。
これらを適用するためには、申告期限までに一旦法定相続分で分割したと仮定する「未分割申告」を行い、実際の分割割合が決まってから修正申告や更正の請求を行うことで、これらの税額控除や特例を適用することが可能となります。
未分割申告について、詳しくは「【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説!」をご覧ください。
1-3.相続人が認知症であることを隠して手続きをしたら、バレる?
相続人が認知症であることを隠して相続手続きを進めた場合、高い確率で発覚します。
不動産の相続登記や銀行預金の解約など、公的な手続きの際には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必須です。手続きを依頼された司法書士や銀行員は、相続人に対して意思確認を行う義務があり、この過程で認知症による判断能力の欠如は必ず発覚します。
発覚した場合、その遺産分割協議は「意思能力の欠如」が理由で無効となります。名義変更などの全ての手続きをやり直す必要があり、複雑な法的手続きと深刻な相続トラブルに発展します。
認知症の相続人がいる場合は、隠すのではなく、適切に対処しましょう。
\\CHECK//
相続税専門の税理士法人チェスターをはじめ、グループに所属する司法書士・弁護士・行政書士と共に、あらゆる相続ニーズにワンストップで対応させていただきます。
すでに相続が開始されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にごお問合せください。
>>【公式】チェスターグループに相談する
2.認知症の相続人は相続放棄をするのも難しい
認知症の相続人は、相続放棄をすること自体が難しい可能性があります。
相続放棄とは、被相続人のマイナスの財産(債務や未払金)などを相続しない代わりに、プラスの財産(預貯金や不動産など)も相続しないということです。
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱いますので、代襲相続も発生しません。

被相続人が債務超過であることが分かっている場合、相続放棄を選択するのが得策です。
詳しくは、「【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!」をご覧ください。
2-1.そもそも認知症の人が相続放棄の選択をできるのかが問題
相続放棄ができるのは、原則として「自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)」です。
相続放棄をする際は、自らの意思で熟慮期間内に、家庭裁判所に申述するのが原則です。
認知症の人でも判断能力が十分であると判断されれば、自身で相続放棄を申立てることが可能です。
ただし、家庭裁判所が確認をして、本人の意思を明確に伝えられない場合は、申述そのものが無効になることもあります。
3.相続人が認知症である場合は「成年後見制度」の利用を
認知症の相続人がいて、判断能力が不十分である場合は、「成年後見制度」の利用を検討しましょう。
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で正常な判断が困難な人が、日常生活において不利益を被ることがないよう、第三者が財産の管理や契約締結などの法律行為をサポートする制度のことです。

相続人が認知症である場合は、遺産分割協議を成立させたり、相続放棄を代行してもらったりなど、法的な手続きのサポートをしてもらえます。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類がありますが、すでに開始した相続において、認知症になっている相続人が成年後見制度を利用する場合は、前者の「法定後見制度」を利用することになります。
制度の概要について、厚生労働省「成年後見制度」もあわせてご覧ください。
3-1.法定後見制度とは
法定後見制度とは、本人の判断能力が欠如してから、関係者が家庭裁判所に申立てすることで利用できるようになる成年後見制度のことです。
認知症の程度に応じて、補助・保佐・後見の3つの種類があり、家庭裁判所が本人の判断能力等を調査して、適切な後見人を選定します。

詳しくは、「「成年後見制度」の制度をわかりやすく解説!どんな制度?」をご覧ください。
3-2.任意後見制度とは
任意後見制度とは、本人の判断能力が十分にあるうちに後見人と契約を結び、必要になったときに利用できるようにする後見制度です。

任意後見制度では、本人が依頼する任意後見人やサポートしてほしい内容を事前に決め、事前に任意後見契約を公正証書で結びます。
そして、本人の判断能力が低下すると、後見監督人が家庭裁判所に選任の申立てをします。
家庭裁判所による後見監督人の選任手続きが完了後、後見監督人の監督の下に、任意後見人は事前に取り決めた通りにサポートを行います。
4.成年後見制度(法定後見制度)にはいくつか注意点がある
相続人が認知症になっている場合は、成年後見制度(法定後見制度)を利用して、遺産分割協議を行うのが一般的です。
しかし、法定後見制度には以下のような注意点があります。
これらを総合的に判断して、成年後見制度を利用するか否かを決めるべきでしょう。
4-1.法定後見制度の審理期間は1~2ヶ月かかる
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てを行った上で審理を受けなくてはなりませんので、申立ての準備などの手間がかかります。
令和6年の成年後見関係事件において、審理期間が1~2ヶ月程度となったのは全体の72.0%とされていますが、中には6ヶ月超えのケースもあります。
引用:裁判所「成年後見関係事件の概況」
相続放棄の期限は「(原則)自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内」で、相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(応当日)」です。
早めに成年後見制度の申立てをしなければ、これらの期限に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。
詳しくは、「成年後見人のデメリット6つ-親族が望ましいケースや利用しない選択肢も」をご覧ください。
4-2.親族が成年後見人に選任されるケースは少ない
成年後見制度では、親族が成年後見人になることもできます。
ただし、実際に成年後見制度を利用しているケースにおいて、親族が成年後見人として選任されているケースは少数です。
引用:裁判所「成年後見関係事件の概況」
令和6年に成年後見制度の利用を開始した人のうち、親族以外が選任されたのは全体の82.9%で、司法書士や弁護士などが選任されるケースが多くなっています。
仮に親族が成年後見人に選任されても、利益相反関係になる場合は、特別代理人の選任が必要となりますのでご注意ください。
4-3.専門家が成年後見人等に選任されたら報酬の支払いが一生涯続く
成年後見制度において、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任された場合、報酬の支払いが必要になります。
大阪家庭裁判所が公開している基本報酬の目安は月額2万円とされていますが、財産管理額が高価な場合は、以下の通りとされます。
| 財産管理額 | 後見人の報酬 |
|---|---|
| 1,000万円~5,000万円 | 月額3万円~4万円 |
| 5,000万円超え | 月額5万円~6万円 |
成年後見制度は、原則本人が亡くなるまで継続するため、報酬の支払いは一生涯続きます。
なお、身上保護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加することとされています。
詳しくは、「成年後見人の費用は誰が払う?報酬やトラブル防止策も解説」をご覧ください。
4-4.遺産分割協議で柔軟な対応はしてもらえない
成年後見制度を利用して遺産分割協議をする場合、成年後見人が柔軟な対応をしてくれる保証はありません。
成年後見人の任務は、認知症である相続人の利益や財産を守ることです。
そのため、相続税の節税目的の遺産分割をしたくても、成年後見人は法定相続分を重視することが多いです。
遺産分割が終わった後も、取得した財産の売却などについて、柔軟な対応をしてくれる保証もありません。
5.法定相続分による遺産分割もできるがデメリットも多い
相続人の中に認知症の人がいる場合、成年後見制度を利用せずに、法定相続分で遺産分割をするという選択肢もあります。
法定相続分とは、民法第900条で定められた「法定相続人が有する相続分の割合」のことで、遺産分割の際の目安として用いられます。

法定相続分による遺産分割をする場合、成年後見制度を利用しなくても良いというメリットはあるものの、以下のようなデメリットがありますので専門家へ相談することをおすすめします。
法定相続分について、詳しくは「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。
5-1.寄与分や特別受益を考慮できない
法定相続分で遺産分割をするということは、当然のことながら、寄与分や特別受益を考慮した遺産分割はできません。
例えば、被相続人が父、法定相続人が母(認知症)・長男・次男であるケースにおいて、長男が父と母と同居をして世話や介護をしていたとします。
次男は父から生前贈与を受けていたものの、介護などには一切協力していないとします。
この場合、母(相続人)が認知症であるからといって、法定相続分で遺産分割をすると、長男と次男の相続分は同じ1/4ずつとなり、寄与分も特別受益も考慮されず、不公平な遺産分割になってしまう懸念があります。
詳しくは「特別受益とは?時効・相続分の計算方法・持ち戻し免除規定について」や「相続における寄与分とは?認められる要件・計算方法を解説【判例付き】」をご覧ください。
5-2.不動産(土地や家屋など)は共有名義となる
法定相続分で遺産分割をするということは、財産の種類ごとに法定相続分で分割するということですので、土地や家屋などの不動産はすべて共有名義となります。
不動産が共有名義になる場合、相続登記自体は特に問題ありませんが、将来的に以下のようなデメリットがあります。
- 売却や活用をするためには全員の合意が必要
- 管理責任を巡ってトラブルになる可能性がある
- 共有者の相続が発生すると権利関係が複雑になる
- 第三者に持分を譲渡されて差し押さえられるリスクがある
共有名義人の誰かが認知症である場合、売却や賃貸に出すための同意ができませんので、どちらにせよ成年後見人の選任が必要となります。
仮に売却や賃貸に出さない場合でも、誰が管理責任者になるのかでトラブルになる可能性もありますし、共有名義人の相続が開始すれば権利関係がさらに複雑になります。
詳しくは「共有名義の土地(共有財産)の相続について知っておきたいこと」をご覧ください。
5-3.小規模宅地等の特例を最大限に活用できない
法定相続分で遺産分割をすると、土地はすべて共有名義になりますので、小規模宅地等の特例を最大限に活用できない可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住用や事業用に供していた宅地の評価額を、最大80%減額できる特例のことです。
引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
宅地を共有名義で取得する場合でも、小規模宅地等の特例は適用できます。
しかし、法定相続分で分割すると小規模宅地等の特例を最大限適用させることが難しくなり、全体的な相続税額も高くなってしまう懸念があります。
詳しくは、「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」をご覧ください。
6.推定相続人が認知症になった場合にすべき3つの生前対策
推定相続人(相続人になるだろうと推定される親族)が認知症になった場合、将来被相続人となる人は、生前対策をされることをおすすめします。
日本では認知症やその前段階であるMCI(軽度認知障害)の高齢者は、約1,001万人いると推計されています。
この数値は高齢者の4人に1人は認知症やその前段階であることを示していますので、身近な家族が認知症になる可能性は高いといえます。
推定相続人が認知症になっていないケースでも、早めに対策をすることで将来安心できるはずです。
6-1.遺言書を作成しておく
推定相続人が認知症の場合、被相続人になりうる人が生前に遺言書を作成されることをおすすめします。
法的に有効な遺言書があれば、遺言書で指定された内容に沿って遺産分割がなされますので、遺産分割協議は不要です。成年後見制度の利用も必要ありません。
一般的な遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があり、それぞれ以下のような違いがあります。

公正証書遺言は法的に無効になるリスクが低く、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクもありません。
家庭裁判所での検認も不要なので、確実に遺言を執行してほしい人には公正証書遺言の作成をおすすめします。
詳しくは、「公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説」をご覧ください。
6-2.生前贈与をしておく
推定相続人が認知症の場合、被相続人になりうる人の財産を、生前贈与しておくのも有効です。
例えば、父・母・長男・次男という4人家族で、母が認知症を発症したとします。
被相続人となる父が、所有している不動産などを、長男や次男に生前贈与しておけば、相続発生時に遺産分割をする必要はなくなります
贈与税には以下のような非課税特例が設けられているため、上手に活用すれば税負担なしで財産を移転できます。
詳しくは、「贈与税は誰が払う?いくら払う?計算方法・非課税の特例も解説」をご覧ください。
6-3.家族信託を利用する
推定相続人が認知症の場合、家族信託を利用するのも良いでしょう。
家族信託とは、財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に任せるための仕組みです。
本人(委託者)が財産を特定の家族(受託者)に託し、その財産を将来のために管理・運用します。信託財産の管理方法や受益者(利益を得る人)を柔軟に設定でき、委託者本人が受益者になることもあります。

家族信託は、本人(委託者)が認知症になった場合でも、信頼できる家族が財産の管理や処分をできるため、認知症対策として注目されている制度です。
家族信託で財産の分配方法や管理方法を事前に信託契約で決めておけば、遺産相続時のトラブルも防ぐことができます。
ただし、家族信託においては事前に定める信託契約が重要になり、専門的な知識が求められますので、税理士や司法書士など信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
詳しくは、「家族信託は必要?問題点はある?活用事例・仕組みも解説」をご覧ください。
7.被相続人が認知症だった場合は遺言書が無効になる可能性あり
認知症であった被相続人の遺言書が見つかった場合、裁判などで「遺言者に遺言能力がなかった」と判定され、その遺言書が法的に無効になる可能性があります。

遺言能力とは、満15歳以上の遺言者が有していなければならない意思能力のことです(民法第963条)。
以下の判定基準を総合的に考慮して、遺言能力(意思能力)の有無が判定されます。
- 精神上の障害の有無・内容・程度
- 遺言書を作成する前後の状況
- 遺言書を作成するに至った経緯
- 遺言内容の合理性
- 相続人や受遺者との関係性
なお、被相続人が生前に認知症と診断されていたからといって、必ずしも意思能力なしと判定される訳ではありません。
過去の判例では、医師の診断や遺言内容の合理性などから、認知症を発症していた当時に作成された遺言書であるものの、遺言者は十分な意思能力を有していたと認めた事例もあります。
重要なのは、遺言能力の有無が問われる前に、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。
詳しくは、「遺言能力とは?満たすべき要件・判断基準・対処法について【判例あり】」をご覧ください。
8.認知症の人が関わる相続…こんなケースはどう対処する?【Q&A】
相続人の中に認知症の人が含まれるケースにおいて、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。
8-1.相続人が認知症なら絶対に遺産分割協議は成立しない?
相続人が認知症と診断されていても、本人に判断能力があり、遺産分割協議の内容を理解して意思を表明できるのであれば、遺産分割協議を成立させられることもあります。
認知症には軽度から重度まで症状に違いがあるため、認知症=判断能力がないとは断言できないためです。
判断能力がある旨が記載された医師の診断書があれば、認知症と診断されていても、遺産分割協議を成立させられる可能性はあります。
8-2.遺産分割協議書に代筆してもバレないのでは?
認知症により遺産分割協議の内容を十分理解できていない状態では、遺産分割協議書に署名・押印があったとしても、意思能力を欠くものと判断され、遺産分割協議書が無効になる可能性があります。
遺産分割協議書への自力での署名・押印が難しい相続人に関しては、署名の代筆もやむを得ないとされています。
しかし、代筆が認められるのは、あくまでも相続人が記載されている内容を理解している場合に限定されます。
8-3.認知症の相続人には特別代理人も必要なの?
認知症の相続人が関わる相続において、特別代理人が必要となるのは、成年後見人も相続人で利益が相反する場合に限定されます。
特別代理人は家庭裁判所が一時的に選任し、一定の手続きが完了するとその任務も終了するという違いがあります。
成年後見人の申立てをして親族を選任してもらい、その後遺産分割のみ特別代理人を選任してもらえば、専門家への報酬を1回だけにできるため、成年後見人の報酬を支払い続けることもありません。
報酬面でのメリットはありますが、手続き内容が非常に複雑になりますので、必ず弁護士や司法書士に相談をしましょう。
8-4.唯一の相続人が認知症の場合は?
唯一の相続人が認知症である場合は、その人が単独相続をしますので、遺産分割協議は必要ありません。
原則としては、被相続人との関係性が分かる戸籍謄本等のみで、相続手続きを進めることができます。
ただし、本人の委任が必要となる専門家への相続手続きの代行サポート依頼や、同意が必要となる相続財産の売却・活用などはできません。
遺産分割ではなくその後の相続手続きの時点で、成年後見人の選任を検討することとなります。
9.相続人に認知症の人が含まれる場合は専門家に相談を
相続人が認知症である場合、遺産分割協議の成立が難しくなり、相続手続きをスムーズに進めることができません。
家庭裁判所に成年後見人の選任申立てをするのが一般的ですが、専門家が選任された場合は費用が一生涯発生するなどのデメリットもあるため、慎重に検討を進める必要があります。
相続財産の種類や内容をもとに、必ず相続に強い弁護士・司法書士・税理士に相談した上で、どのような方向性で相続手続きを進めるのかを決めましょう。
9-1.煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!
相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。
例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
相続に関する様々な手続きにおいてプロの力を必要とされる人はそれぞれの専門家を探してこれだけの対応をしなければなりません。
でも、相続に関することならまずはチェスターへご相談頂ければもう安心です。
税理士法人チェスターでは、グループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。
相続手続き周りでお困りの人は、まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
>>【公式】税理士法人チェスターに相談する
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続法務編









































