遺産総額5000万円の相続税はいくら?早見表や計算方法を解説
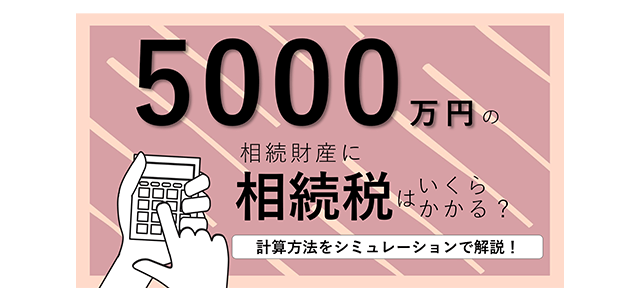
この記事をご覧のみなさんは、「遺産総額5000万円の相続税はいくらかかるの?」とお悩みかと存じます。
結論を言うと、遺産総額5000万円だから相続税は○○万円…と単純な計算はできません。
同じ5000万円であっても、「法定相続人の数」や「遺産の分割方法」などで相続税額は大きく変わります。
ただし、相続税の早見表やシミュレーターを活用すれば、5000万円の相続税は概算でいくらなのかを知ることはできます。
この記事では、「遺産総額5,000万円の相続税はいくらなのか」をテーマに、相続税の計算方法や税負担を軽減できる制度などを、相続税専門の税理士が解説します。
この記事の目次 [表示]
1.5000万円の相続税はいくら?早見表で概算の税額を確認
遺産総額5000万円の相続税はいくらなのか、相続税の早見表で確認してみましょう。
相続税の早見表は5種類あり、法定相続人の組み合わせによってパターンが異なります。
前提条件として、法定相続分で相続すると仮定し、さらに配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という税額軽減を適用した後の相続税額を計算しています。
そのため、早見表に記載されている相続税額は、配偶者以外の法定相続人が納付する相続税額の総額(配偶者は相続税額0円)となります。
実際の相続税額は早見表とは異なりますので、正確な相続税額の計算は、必ず税理士に依頼してください。
1-1.法定相続人が配偶者+子どもの場合
法定相続人が配偶者と子どもの場合、遺産総額5000万円の相続税は以下の通りとなります。
| 正味の 遺産総額 | 配偶者と子どもが相続人の場合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |||||
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 | ||||
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 | ||||
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 | ||||
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 | ||||
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 | ||||
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 | ||||
| 1.5億円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 | ||||
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 | ||||
| 2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 | ||||
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 | ||||
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 | ||||
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 | ||||
※法定相続分「配偶者1/2」「子ども1/2」で分割したと仮定
※「基礎控除」と「配偶者控除」を適用させた後の相続税の総額(子どもの納税額の合計)
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず
法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、5000万円の相続税は10万円、これは子ども2人が納付する相続税額です(配偶者は相続税0円)。
仮に法定相続分で遺産分割をする場合、子どもはそれぞれ5万円ずつ相続税を納付することとなります。
1-2.法定相続人が配偶者+父母の場合
法定相続人が配偶者と父母の場合、遺産総額5000万円の相続税は以下の通りとなります。
| 正味の 遺産総額 | 配偶者+父母が法定相続人の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 父母1人 | 父母2人 | |||
| 5,000万円 | 27万円 | 7万円 | ||
| 6,000万円 | 63万円 | 40万円 | ||
| 7,000万円 | 108万円 | 81万円 | ||
| 8,000万円 | 157万円 | 126万円 | ||
| 9,000万円 | 210万円 | 170万円 | ||
| 1億円 | 271万円 | 222万円 | ||
| 1.5億円 | 660万円 | 583万円 | ||
| 2億円 | 1,131万円 | 1,004万円 | ||
| 2.5億円 | 1,742万円 | 1,544万円 | ||
| 3億円 | 2,353万円 | 2,100万円 | ||
| 5億円 | 5,158万円 | 4,662万円 | ||
| 10億円 | 1億3,231万円 | 1億2,333万円 | ||
※法定相続分「配偶者2/3」「父母1/3」で分割したと仮定
※「基礎控除」と「配偶者控除」を適用させた後の相続税の総額(父母の納税額の合計)
※「障害者控除」などの税額控除は考慮せず
法定相続が配偶者と母である場合(父は他界)、5000万円の相続税は7万円、これは母が納付する相続税額です。
配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を適用しているため、配偶者は相続税0円です。
1-3.法定相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺産総額5000万円の相続税は以下の通りとなります。
| 正味の 遺産総額 | 配偶者+兄弟姉妹が法定相続人の場合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 | |||||
| 5,000万円 | 24万円 | 6万円 | 0円 | 0円 | ||||
| 6,000万円 | 59万円 | 36万円 | 18万円 | 0円 | ||||
| 7,000万円 | 101万円 | 76万円 | 51万円 | 30万円 | ||||
| 8,000万円 | 142万円 | 117万円 | 92万円 | 67万円 | ||||
| 9,000万円 | 195万円 | 161万円 | 133万円 | 109万円 | ||||
| 1億円 | 251万円 | 213万円 | 181万円 | 150万円 | ||||
| 1.5億円 | 626万円 | 563万円 | 510万円 | 465万円 | ||||
| 2億円 | 1,089万円 | 999万円 | 923万円 | 855万円 | ||||
| 2.5億円 | 1,620万円 | 1,505万円 | 1,429万円 | 1,354万円 | ||||
| 3億円 | 2,183万円 | 2,016万円 | 1,936万円 | 1,860万円 | ||||
| 5億円 | 4,757万円 | 4,422万円 | 4,246万円 | 4,125万円 | ||||
| 10億円 | 1億2,119万円 | 1億1,457万円 | 1億1,045万円 | 1億747万円 | ||||
※法定相続分「配偶者3/4」「兄弟1/4」で分割したと仮定
※「基礎控除」と「配偶者控除」を適用させた後の相続税の総額(兄弟姉妹の納税額の合計)
※「障害者控除」などの税額控除は考慮せず
法定相続が配偶者と兄弟姉妹1人である場合、5000万円の相続税は20万円、これは兄弟姉妹が納付する相続税額です。
なお、兄弟姉妹は相続税の2割加算が適用されるため、納税額は上記表のとおり、24万円となります。
配偶者には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」を適用しているため、配偶者は相続税0円です。
1-4.法定相続人が子どものみ・父母のみ・兄弟姉妹の場合
法定相続人が子どものみ・父母のみ・兄弟姉妹のみの場合、遺産総額5000万円の相続税は以下の通りとなります。
| 遺産総額 (相続財産) | 子どものみ・父母のみ・兄弟姉妹のみが法定相続人の場合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |||||
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 | ||||
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 | ||||
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 | ||||
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 | ||||
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 | ||||
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 | ||||
| 1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 | ||||
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 | ||||
| 2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 | ||||
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 | ||||
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 | ||||
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 | ||||
※「基礎控除」を適用させた後の相続税の総額
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず
※第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)における相続税の2割加算は考慮せず
相続人に配偶者が含まれるケースと比較して、全体的に相続税額が高くなっています。
これは、相続人が子供のみであると、配偶者の税額軽減が適用されないためです。一方で、相続人の数が増えるほど、税負担が軽減される点は同様です。
1-5.法定相続人が配偶者のみの場合
法定相続人が配偶者のみの場合、遺産総額5000万円の相続税は0円です。
この理由は、法定相続人が配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分100%すべてに配偶者控除を適用することができるためです。
遺産総額に関わらず、すべての財産に対して配偶者控除が適用されるため、相続税は0円になります。
1-6.相続税計算シミュレーションツールをご利用ください
税理士法人チェスターでは、「相続税計算シミュレーションツール」を無料で公開しております。
おおよその遺産総額や法定相続人の情報を入力するだけで、概算の相続税総額を計算していただけます。

相続税の早見表に該当しないパターンの法定相続人である場合や、配偶者の取得分が法定相続人と異なる場合は、ぜひご利用ください。
>>【チェスター公式】相続税計算シミュレーション
2.相続税の早見表にある法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利を有する一定の範囲の親族のことです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、その他の法定相続人には優先順位(相続順位)が定められています(民法第886条~890条)。

例えば、被相続人に配偶者と子ども(長男と次男)がいれば、法定相続人は配偶者・長男・次男の合計3人です。
仮に被相続人の父母や兄弟姉妹が健在であっても、法定相続人にはなりません。
なお、内縁関係の人は法定相続人に含まれず、相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
詳しくは「法定相続人とは?【図解あり】範囲・順位・相続割合まで解説」をご覧ください。
2-1.法定相続人には法定相続分が定められている
法定相続分とは、民法第900条で定められた、各法定相続人が有する相続分の割合のことです。
遺言書がなく法定相続人が複数人いる場合に、「誰がどの割合で遺産相続するのか(具体的相続分)」を決めるための目安となります(必ずしも法定相続分で遺産分割する義務はありません)。
なお、相続税額を計算する際には、一旦法定相続分で取得したと仮定して税率や控除を適用させる必要があるため、誰がどれだけ法定相続分を有しているのかを確認しておきましょう。

同順位の法定相続人が複数人いる場合は、定められた法定相続分を人数で均等に按分する必要があります。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども(長男と次男)であれば、法定相続分は配偶者1/2・長男1/4・次男1/4です。
詳しくは、「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。
3.遺産総額は本当に5000万円?相続税額を計算する前に確認を
遺産総額5000万円の相続税はいくらかを知るためには、相続税の早見表の利用が便利です。
しかし、相続税額を知る前に、「本当に遺産総額は5000万円なのか」を再確認しておきましょう。
相続税の課税対象となる財産(遺産総額)を知るためには、プラスの財産(不動産・株式・預貯金・現金・貴金属・宝石・書画・骨とう・自動車)を、国税庁「相続税財産評価に関する基本通達」を参考にしてそれぞれの評価額を計算しなくてはなりません。
さらに、相続時精算課税制度による贈与財産やみなし相続財産も加算し、マイナスの財産(債務・借入金・未払金)・非課税財産・葬式費用などを差し引き、生前贈与加算の対象となる一定範囲の贈与財産の持ち戻しをする必要があります。

つまり、遺産総額5000万円と思っていても、正味の遺産総額は5000万円以下であることも十分あり得るということです。
詳しくは「遺産の相続税はいくらから?税額の計算方法や税負担の軽減方法をプロが解説」や、国税庁「財産を相続したとき」をご覧ください。
3-1.相続時精算課税制度による贈与財産は相続財産に持ち戻し
相続時精算課税制度を適用した贈与財産は、特定贈与者の相続財産に持ち戻しをする必要があります。
相続財産に持ち戻す贈与財産の価額は、贈与時の時価となります。
また、令和6年1月以降は基礎控除(年間110万円)が創設され、基礎控除以下の贈与財産は持ち戻しの対象外となります。
詳しくは「【相続時精算課税制度とは】メリット&デメリット、手続きまで解説」をご覧ください。
3-2.みなし相続財産は相続税の課税対象
みなし相続財産とは、相続財産ではないものの、相続したとみなして相続税が課税される以下のような財産のことです。
- 死亡保険金
- 死亡退職金
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
被相続人が被保険者=契約者であり、法定相続人が受取人である死亡保険金は、被相続人が相続開始時に保有していた財産ではありません。
しかし、被相続人の死亡を事由として支払われる金銭ですので、みなし相続財産として相続税が課税されます。
みなし相続財産について、詳しくは「【相続税】みなし相続財産とは?課税対象になる種類と非課税枠の計算方法」をご覧ください。
3-3.非課税財産は相続税の課税対象にならない
非課税財産とは、相続税法第12条で定められている、相続税の課税対象にならない以下のような財産のことです。
②墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
③一定の公益事業を行う者が取得した公益事業用財産
④条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人が取得した生命保険金等のうち一定の金額
⑥相続人が取得した退職手当金等のうち一定の金額
⑦相続税の申告書の提出期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に贈与(寄附)した財産
②はいわゆる祭祀財産のことで、お墓や仏壇などが該当します。
⑤死亡保険金や⑥死亡退職金は、受取人が法定相続人である場合、非課税枠(法定相続人の数×500万円)が非課税財産となります。
例えば、みなし相続財産である死亡保険金が2,000万円で、法定相続人が3人、その中の誰かが受取人である場合、1500万円が非課税財産となります(500万円のみがみなし相続財産)。
詳しくは、「相続税の非課税財産(相続税法12条)について解説」をご覧ください。
3-4.債務や未払金は債務控除できる
債務控除とは、遺産の総額から差し引くことができるマイナスの財産のことです。
債務控除の対象となるのは、相続開始時点で確実と認められる、以下のような債務のことを指します。
- 金融機関や個人からの借入金
- 亡くなった後に支払う公租公課
- 病院に対する未払医療費
- 公共料金等の未払金
- 賃貸不動産の借主から預かっている敷金
- 買掛金などの事業上の未払金
被相続人が生前に購入したお墓や仏壇などの祭祀財産の代金で、未払いの部分など非課税財産に関する債務は、相続財産から控除できません。
また、被相続人が亡くなった後に発生する費用についても、債務控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
詳しくは「相続税の債務控除とは?葬式費用は控除の対象となる?条件について解説」や、国税庁「相続財産から控除できる債務」をご覧ください。
3-5.葬儀費用は相続財産から控除できる
葬儀にかかる費用は喪主が支払うことが一般的ですが、負担した葬儀費用は「葬式費用」として相続財産から控除できます。
葬式費用とは、故人を弔うための儀式や埋葬にかかる、以下のような費用のことです。
- 通夜や告別式のために葬儀会社に支払った費用
- 通夜や告別式に係る飲食費用
- 葬儀を手伝ってもらった人などへの心付け
- 寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
- 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
- 火葬、埋葬、納骨にかかった費用
- 遺体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用
- 死亡診断書の発行費用
ただし、初七日や法事などの費用や、香典返しは葬式費用に含まれません。
詳しくは「相続税から葬儀費用は控除できる?該当するもの・注意点や申告方法も解説」や、国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」をご覧ください。
3-6.相続開始前3年~7年以内の暦年贈与財産は持ち戻し
相続開始前3年~7年以内に、被相続人からなされた暦年贈与による贈与財産は、相続財産に持ち戻して相続税の課税対象となります。このルールを「生前贈与加算」といいます。
暦年課税における基礎控除(年間110万円以内)の贈与財産も、遺産を取得した人に贈与されていたのであれば、生前贈与加算の対象です。

生前贈与加算はこれまで相続開始前3年以内でしたが、税制改正に伴い、令和6年1月以降に行われる贈与から持ち戻しの期間が順次延長されています。
生前贈与加算について、詳しくは「生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説」をご覧ください。
4.遺産総額5000万円の相続税の計算シミュレーション
相続税は、以下の5つのステップで計算します。
ステップ2:基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算
ステップ3:法定相続分で按分して仮の相続税の総額を計算
ステップ4:各相続人の相続税額を計算
ステップ5:税額控除を適用して実際の納付税額を計算
この章では、遺産総額が5000万円(自宅不動産と預貯金)で、法定相続人が配偶者と子供ども1人と仮定した、相続税額の計算シミュレーションを行います。
前提条件として、遺産分割協議で決定した実際の相続分は、法定相続分と同じ配偶者1/2・子ども1/2とします。
相続税の計算方法について、詳しくは「相続税の算出方法」をご覧ください。
4-1.ステップ1:正味の遺産総額を計算
まずは相続税が課税される対象となる、正味の遺産総額を計算します。
このシミュレーションモデルの相続財産の内訳は、以下の通りとします。
| プラスの財産 |
|
|---|---|
| みなし相続財産 |
|
| マイナスの財産 |
|
| 生前贈与 |
|
不動産3000万円+預貯金2000万円+死亡保険金1000万円ですので、遺産総額は6000万円です。
そのうち、死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」ですので、1000万円全額を非課税財産として差し引きます。
さらに、葬式費用200万円を控除して、相続開始前3~7年以内の暦年贈与財産を相続財産に持ち戻します。
このシミュレーションモデルでは、①正味の遺産総額は5000万円となります。
4-2.ステップ2:基礎控除を差し引いて課税遺産総額を計算
次に、①正味の遺産総額5000万円から基礎控除を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
相続税の基礎控除は【3000万円+(法定相続人の数×600万円)】で計算します。正味の遺産総額が基礎控除額以下である場合、相続税はかかりません。

法定相続人の数が多いほど基礎控除額は増えていくため、相続税額は少なくなっていきます。
このシミュレーションモデルでは、法定相続人は2人ですので、基礎控除は4200万円です。
正味の相続財産額5200万円-基礎控除額4200万円=②課税遺産総額800万円となります。
4-3.ステップ3:法定相続分で按分して仮の相続税の総額を計算
次に、②課税遺産総額800万円を法定相続分どおりに取得したものと仮定し、相続税の税率を適用して各法定相続人別に計算します。
子ども:課税遺産総額800万円×法定相続分1/2=400万円
ここに相続税の税率や控除を当てはめて、仮の相続税額を計算します。

上記をもとに配偶者と子どもの仮の相続税額を計算すると、結果は以下の通りです。
子供:400万円×税率10%-控除0円=40万円
さらに、仮の相続税額を合計して、家族全体の相続税の総額を計算します。
このシミュレーションモデルでは、配偶者40万円+子ども40万円=③仮の相続税の総額80万円となります。
4-4.ステップ4:各相続人の相続税額を計算
次に、各相続人の相続税額を計算します。
具体的には、③仮の相続税の総額80万円を、各相続人(受遺者・相続時精算課税を適用した人も含む)が実際に取得した正味の遺産額の割合で按分します。
子供:80万円×実際の分割割合1/2=納税額40万円
今回のシミュレーションでは、法定相続分と同じ割合で遺産を相続するため、各人の相続税額は仮の税額と同じです。
4-5.ステップ5:税額控除等を適用して実際の納付税額を計算
最後に、税額控除等を適用して、実際の納付税額を計算します。

このシミュレーションモデルでは、被相続人の配偶者は「配偶者控除」を適用できるため、相続税額は0円となります。
子どもは成人しているため未成年者控除は適用できず、その他の税額控除も対象外であるため、相続税額は40万円です。
\\CHECK//
仮に税額控除を適用できれば、各相続人の納税額を引き下げることが可能です。
5.相続税の計算時に利用できる税額控除
各相続人の相続税の納付税額を計算する際には、属性や状況によって以下の税額控除が適用できます(併用可能)。
各種税額控除について、詳しくは「相続税の控除・特例を一覧で解説|知らないと損する節税制度とは」でも解説しております。
5-1.贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税お二重課税を回避するために、すでに納付した贈与税額を、贈与者の相続に係る相続税額から差し引くことができる税額控除のことです。

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の課税方法があり、どちらの課税方式を選択したのかによって、贈与税額控除を計算する際の贈与財産の考え方が異なります。
贈与税額控除について、詳しくは「暦年課税に係る贈与税額控除の控除不足額は還付なし~令和5年度税制改正で見直しもされず~」をご覧ください
5-2.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈によって取得した正味の遺産額が、1億6,000万円(もしくは法定相続分)までは相続税が0円となる税額控除のことです。
配偶者控除を適用すれば、配偶者は相続税がかからないケースがほとんどです。

ただし、配偶者控除を適用するためには、法的に婚姻関係が成立していることや、期限までに相続税申告をすることなどの要件が定められています。
遺産分割ができないなどの理由で、期限までに相続税申告ができない場合は、一旦法定相続分で分割したと仮定する「未分割申告」をしなくてはなりませんのでご注意ください。
また、配偶者控除を利用し配偶者に全財産を相続させて、相続税を全額控除する事例がありますが、配偶者が亡くなった際の相続財産が膨らみ、相続税が多額になってしまうというデメリットがあります。
配偶者控除について、詳しくは「【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。
5-3.未成年者控除(未成年者の税額控除)
未成年者控除(未成年者の税額控除)とは、相続開始の時点で18歳未満(2022年3月31日以前は20歳未満)の未成年者である法定相続人に適用される税額控除です。
未成年者控除を適用できれば、未成年者である法定相続人が満18歳になるまでの年数1年につき10万円が、相続税の納付税額から控除されます。

例えば、相続の時点で相続人が15歳である場合、相続税額から控除される金額は(18歳−15歳)×10万円=30万円です。
未成年者控除額が相続税額より大きい場合、余りについては未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
未成年者控除について、詳しくは「相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説」をご覧ください。
5-4.障害者控除(障害者の税額控除)
障害者控除(障害者の税額控除)は、相続開始の時点で障害者である法定相続人に適用される控除です。
障害者控除を適用できれば、障害者である法定相続人が85歳になるまでの年数1年につき、10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から控除されます。

例えば、相続の時点で一般障害者である相続人が60歳であった場合、相続税から控除できる金額は(85歳-60歳)×10万円=250万円です。
障害者控除額が余った場合は、未成年者控除と同様に、その法定相続人の扶養義務者の相続税額から差し引くことが可能です。
障害者控除について、詳しくは「【相続税の障害者控除】控除額の計算方法・要件をプロが解説」をご覧ください。
5-5.相次相続控除
相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した際に、二次相続に係る相続税額から、一次相続の相続税の一部を差し引くことができる税額控除のことです。

相次相続控除には様々な要件が設けられており、控除額の計算方法も非常に複雑です。適用要否については、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。
相次相続控除について、詳しくは「相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説」をご覧ください
5-6.外国税額控除
外国税額控除とは、すでに海外で相続税を支払っている場合に、日本で支払う相続税の中から、海外の財産割合を控除できる税額控除のことです。
具体的には、以下のいずれか少ない方の金額を、相続税額から控除できます。

国際相続は専門性が高いため、国際相続の取扱いがある、相続税に強い税理士に必ず相談してください。
外国税額控除について、詳しくは「相続税の外国税額控除とは?二重課税を防ぐ手続き・計算方法を解説」をご覧ください。
6.相続税の計算でミス連発!5つの注意ポイント
相続税の計算は非常に複雑で、相続税専門の税理士に依頼せず、相続人自身で税額を計算すると、さまざまなミスが起こりやすいです。
この章では、相続税の計算で間違いやすいポイントを解説します。
6-1.5000万円×税率-控除で相続税を計算しない
遺産総額が5000万円だからといって、相続税は「5000万円×20%-200万円=800万円」と単純な計算はできません。
正味の遺産総額を計算した上で基礎控除を差し引き、一旦法定相続分に按分して相続税の税率を乗じ、合計した後に実際の取得割合に応じて案分しなくてはなりません。
さらに税額控除や特例などを適用すると、相続税額も大きく異なります。
正しい相続税額は、相続税に強い税理士に計算してもらいましょう。
6-2.土地は相続開始日の相続税評価額を計算
相続財産に土地が含まれる場合は、相続発生日の土地の相続税評価額を計算しなくてはなりません。
土地の相続税評価額は、路線価方式または倍率方式で計算をします。
土地の評価額の基となる路線価と倍率は、毎年1月1日時点を基準日とし、その年の7月上旬に国税庁が「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」にて公表します。
つまり、相続開始日が1月~6月末である場合、その年度の路線価が公表されるまで土地の評価額が計算できないということです。
間違えて前年度の路線価や倍率を使って、土地の評価額を計算しないようご注意ください。
詳しくは「【相続税路線価とは】調べ方・計算方法をわかりやすく解説!」をご覧ください。
6-3.土地は小規模宅地等の特例を適用した後の評価額を用いる
正味の遺産総額を計算する際の土地の評価額は、小規模宅地等の特例を適用した後の評価額を用いて計算しましょう。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や、業を営んでいた土地などを相続したときに、一定の要件を満たすことができれば、土地の評価額が最大80%減額される特例のことです。

出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
小規模宅地等の特例は節税効果が高く、適用できれば相続税が0円となるケースもあります。
ただし、相続税が0円になるケースでも、相続税申告は必要となりますので、失念しないようご注意ください。
詳しくは「小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう」や、国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」をご覧ください。
6-4.団体信用生命保険により返済が免除される住宅ローンは債務ではない
相続人が団体信用生命保険に加入していた場合、住宅ローンの残債は債務控除の対象になりません。
団体信用生命保険に加入していると、住宅ローンの契約者が亡くなったときに、保険金が支払われることで残債が0円となります。
団体信用生命保険によって住宅ローンが完済されているにもかかわらず、相続が開始された時点の残債をプラスの相続財産から控除してしまうと、相続税の計算を誤ってしまいかねません。
相続税を計算するときは、被相続人の残したローンが団体信用生命保険で完済されるかどうかを、よく確認することが大切です。
6-5.相続税の2割加算が適用されていない
相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者と一親等の血族以外の人が遺産を相続・遺贈した場合、その人の相続税額に2割の金額が加算される制度のことです(相続税法第18条)。

例えば、代襲相続人ではない孫や養子縁組している孫、兄弟姉妹や甥姪などは相続税の2割加算が適用されます。
相続税の2割加算が適用される場合、相続税額の計算のみならず、申告書に加算金額を記入しなければなりませんので失念しないようご注意ください。
相続税の2割加算について、詳しくは「相続税の2割加算の対象者は?【税理士監修】計算方法をくわしく解説」をご覧ください。
7.遺産総額5000万円の相続税はいくらか知るには税理士に相談を
遺産総額5000万円の相続税はいくらかを知るには、相続税の早見表やシミュレーターを活用すれば、概算の税額を把握していただけます。
しかし、誰がどの財産を取得するのか、また、どのくらいの割合で遺産を取得するのかによって、各相続人納税額は大きく異なります。
また遺産総額5000万円でも、法定相続人の人数によって相続税が課税されるケースとされないケースもあります。
正確な相続税額については、相続税に強い税理士に計算してもらうことを強くおすすめします。
7-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件超の相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。
各種特例や税額控除を適用させた正確な相続税額の計算はもちろん、相続税の負担を軽減させる遺産の分割方法のアドバイスなどもさせていただきます。
すでに相続が発生されたお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は84名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編






































